窓際にてるてるぼうずを飾ってからあまり日も経たずして、季節は確かに変わりを見せていた。あれほど雨が降って困ると思いきや、今ではすっかり日照り、日照り、日照りの日々。扇風機がなければ一日を過ごせないほど、小暑というにはやけに暑い日が続いている。 朝のまだ涼しいうちに、とカカシがを連れて散歩に出れば、店も開かぬ時分の街並みを、同じように犬を連れた人々が歩いていた。みな考えることは一緒らしい。眠たげな表情を浮かべる人々とは裏腹に、犬たちは元気いっぱいだ。漏れずしても毎日飽くことなく同じ電柱や雑草の塊をチェックしては、今日も異常なしとでも言いたげな顔で、尻尾を振りながら小さな足で闊歩している。ルーティーンをこなすというのは人だけじゃなく、犬にとっても重要なことなのかもしれない。 楽しげな声の上がる井戸端会議の横を通り過ぎ、しばらく進めば、行き着いた先は火影邸の前だった。カカシはおもむろに立ち止まって、小さな首をぐいと建物の上に向ける。すると、リードに引っ張られ、急に前に進めなくなったの喉が鳴った。何事だと飼い主の方を振り返るも、その表情は瞳には映らない。それが不安だったのか、はカカシの足元に寄り添うように距離を縮めた。「まあできた犬ねえ」と通りすがりの老婆がつぶやくも、その声は少年の耳には入っていないようだった。 「ねえ、この中に父さんもいるのかな」 建物の中を忙しなく行き来する人々の姿。夜に寝て、朝起き一日の準備を始める、そういう普通の暮らしと比べ、ここは随分と時間の概念が狂っているよう感じられた。 アカデミーにも入っていない少年には、火影邸はまだまだ遠い存在だ。けれどもこの少年の父は違う。この場所で任務を言い渡され、この場所から外の世界へと旅立っていく。任務さえなければ一緒にいる時間が増えることを思えば、幼心に憎らしい気持ちが芽生えなくもなかったが、この生き方を生業としているのを理解できるには、カカシは忍の家の人間だった。 「大きくなったら、俺もここで働くんだ」 早く父の隣に立てるようになりたかった。それだけじゃない。向日葵のように笑う、あの金髪の男の隣にも。今はまだ、チャクラも思うように練れないひよこだけれど。 カカシはに微笑みかけ、「行こう」とリードを引き出した。馬の手綱を引くかの如く指先には力が籠り、重たげな瞼から覗く双眸には光が差している。飼い主の足取りの軽さにも跳ねながら着いていくと、生命力に溢れた一人と一匹は、不思議なことに家を出た時よりも世界を広く感じたのだった。 * 「カカシ?」 耳に馴染む声が聞こえてくる。この声は。カカシの鼓動がどくんと大きく鳴るやいなや、彼は立ち止まって辺りをきょろきょろと見回し始めた。目の届く範囲にその姿を認めることができずにいると、足元から短い一吠えが上がった。見つけた、という気持ちと、それをカカシに伝えたい気持ちからか、立て続けには声を張り上げる。甲高い犬のそれは、朝の澄んだ空気によく響いた。小刻みに尻尾を振った犬の目線はとても高く、カカシもそれを追う。すると、建物の屋上から「おーい」と声の主が呼んでいるではないか。 「父さん!」 カカシの声が上がるのと、サクモが地面に着地するのはほぼ同時で、二人の周りに軽く砂埃が舞い上がる。任務帰りなのだろう父の身なりは、お世辞にも綺麗とは言い難かった。 「散歩に出ていたんだな」 「おかえり、任務終わったの?」 「ああ、そうだよ。ただいま」 中腰になったサクモが息子の頭を優しく撫でると、少年はくすぐったそうに、けれども嬉しさを隠しきれないといった風に肩をよじらせた。父親の手は自身のそれより何倍も大きく、節くれ立ってもいない自分のものとは全然違う。骨ばっていて、まさにかっこいい大人の男のものだ。けれども力強い男らしさとは裏腹に、己に触れる時はとてもやさしく、とても温かいのをカカシは知っている。そういう手を、自分もいつか持ちたかった。 「もおはよう、朝から元気だなあ」 サクモはさらにかがんでをありったけ撫で回す。力の限り尻尾を振ったは我慢しきれずその場に勢いよく倒れると、体をひねって腹をむき出しにしてみせた。もっと撫でてと言っているのは明らかで、愛らしい犬を前に、任務で溜まった疲労が消えていくのを感じずにはいられない。 「甘えん坊だなあほんと」 「あーあってば背中が汚れちゃうよ」 「洗うこっちの身にもなってよね」とカカシが続けると、サクモは笑って「まあそう言うな」となだめに入った。どうせ自分も汚れているし、風呂のついでに一緒に洗ってやるからと告げれば、少年は腕を組んで「それぐらいよろしく」と鼻を鳴らす。 こんな皮肉めいたことを言いながらも、きっと息子は自分と一緒に家でを洗うのだ。その光景がサクモには容易に想像された。変なところで素直じゃなくて、すこし皮肉屋なところ―もちろんそこが可愛らしいのだけれど―は、亡き愛しい人のそれを彷彿とさせる。自分はどちらかといえば大らかな性格で、本音が言えなくて気持ちを隠してしまうことがあまりないだけに、彼女が見せる時々素直になれない部分がとてもいじらしかった。どっちの血もちゃんと引いているのだと改めて感じたサクモは目を細め、小さな手に握られたリードを掬い取る。 「ほら、父さんが持つよ」 「いいのに」 「いつもカカシに任せっきりなんだ、たまには父親らしいことをさせてくれ」 「え〜父親って犬の散歩をすることなの?」 「そうだな、それもそうか」 歩き出す気配を感じ取ったはすぐさま立ち上がり、体についた砂を払うためにブルブルと全身を震わせる。 「わあっちょっと!!」 飛んだ砂が背丈の低いカカシの方にばかり飛んでいくものだから、彼は急いで父親の後ろへと身を隠す。はは、とサクモは笑って、ぎゅっと自分にしがみつく息子の頭をひと撫でした。今度はこの攻撃を全部避ける修行でもするか、と頭に浮かべながら、空いている側の手で息子の手を引いて歩き出す。 「朝ごはんはもう食べたのか?」 「ううん、まだ」 「それじゃあ朝市で何か買って帰ろう」 「いいの?夜ご飯の残りもあるよ」 「それは昼に温め直して食べよう、そうだな、タワラ屋さんの朝限定おにぎりなんてどうだ?」 「タワラ屋のおにぎり?」 「この時間でもないと買えなくてね」 どうやらタワラ屋のおにぎりが最近忍たちの間で噂になっているのだとサクモは続けた。オープンしてまだ半年ぐらいの店だが、朝ごはん専門店という名の通り、朝しか営業していない、このあたりでは珍しいタイプの店らしい。 メニューに並ぶのは至ってシンプルで、日によって違う具材の入ったおにぎりと、その具材に合わせて作られた味噌汁、そして秘伝のぬか床に漬けられた漬物の三種類。米問屋だからこそできる飾らない、けれども贅沢な朝ごはんというわけだ。 任務明けでへとへとになって帰ってくる忍にとって、ありがたい店であるのは間違いないし、里の人々からしても、朝起きて数分足をのばすだけで食べられる絶品朝食とあり、常に繁盛している店だった。 「どうやらちょっと前から焼き鯖おにぎりがあるらしくて、父さんそれが気になるなあ」 「焼き鯖・・・、おいしそう、お腹空いたかも」 食事の話をすると、不思議とお腹が空いた気持ちになるのは何でだろう。そんなことを考えては、期待に二人の胸が膨らんでいった。 「父さん、あるといいね焼き鯖」 「なかったら魚屋で鯖を買って家で再現しよう」 「再現ってあのね、まだ見たこともないのに」 「それなら父さんのオリジナル焼き鯖おにぎりだな」 心を躍らせながら道なりに歩くと、ちょうどアカデミーの前に差し掛かった。まだ早い時間だというのに、入り口の近くで講師らしき人物たちがあちらこちらへと動いている様が見て取れる。一体何事だろうとサクモが目を凝らすと、彼らはどうやら笹の木を運んでいるようだった。それで合点がいったらしい。そういえば、もうそんな時期か。意識して辺りを見渡せば、確かに色とりどりの吹き流しが街のそこここに飾られているのが分かった。 仕事が忙しくて季節の行事を忘れてしまうのは、それはそれでさみしいものがあると彼はしみじみ思ってしまう。 「もう七夕の時期か」 「たなばた?」 「去年は特に何もしなかったなあ」 任務のせいで正確には「しなかった」のではなく、「できなかった」のだけれど。 「あの木が関係してるの?」 「ああ、そうだよ」 七夕と笹の木がいまいち結びつかないカカシの瞳と、そもそもを理解していないの瞳。それらはよく似ていた。サクモが説明がてら入口に近寄ると、丁度校舎から見知った顔が段ボールを手にやってきたのだった。 「これはこれははたけさん、おはようございます」 「おはようございます先生、朝から精が出ますね」 「まあ、この子があの白い牙の息子さんなのねえ。今度の入学試験、みんな期待してるのよ」 「ははは、期待にこたえられるよう頑張らないとですね」 講師の視線がカカシへと降りた瞬間、彼は繋がれた父親の手をスッと振りほどいた。子供の張る精一杯の見栄はなんて可愛いのだと、大人たちは笑みを浮かべている。ほらカカシも挨拶しなさい、とサクモが息子の背を押すと、臆することなく少年は前に出て言った。 「次の春からお世話になります。よろしくお願いします」 幼さに宿る凛々しさからは、忍になると志す熱意が感じられる。この年の子供にとって、大人と相対することはとても勇気のいることだ。けれどもカカシは一人の人間として、一人の人間と向き合っている。そういう精神の強さはやはり忍の一族に共通するところなのだろう。しかも父親が木の葉の白い牙ときたものだから、それは一層そうだ。 「ふふ、頼もしいこと。はたけさん、願書だけは忘れないでくださいね」 「もちろんですよ」 「そうそう、良かったら短冊書いていきません?」 「いいんですか?」 「ぜひ!あ、でも子供限定なんですけどね」 * 家に帰って、父とシャワーを浴び、犬を洗って乾かした。報告書を出してくるからと家を出る父を見送ったあと、がクッションに飛び込むのに合わせて、カカシも一緒に沈み込んだ。そうして心地よい疲労に身を任せながら、彼は朝の出来事をゆっくり味わい直すかのように、脳裏で思い起こしていた。 タワラ屋の焼き鯖おにぎりは絶品だった。皮目はパリっと焼けていて、それでいてふっくらとした身が粒の立った米に包まれていて、味噌汁と一緒に喉を通るあの幸福さ。それに食べている最中からすでに、次もまた来ようと話す父の楽しそうな表情。 それからおにぎりを頬張りながら耳を傾けた父の話。店の主人が気を利かせて作ってくれた犬用の食事をものの数秒で平らげたは、満足気に二人の足元で丸くなっていた。すぐには動く気配のない二人の様子を窺いながら、次第に退屈になったのか、顎を地面にぴたりとくっつけていたのが可愛かった。 「なあ、七夕がなにか分かった?」 「くぅん?」 あの時サクモは言った。七夕というのは、簡単に説明すると7月7日の夜にだけ織姫と彦星が会うことができる日なんだ、と。色々言い伝えはあるけれど有名なのは、と続いたのはその織姫と彦星の話だった。分からなければ図書館で本を探すと良いと、都合よく締めくくられた気がしないでもないカカシだったが、とにかく笹の葉に願い事を書いた短冊を飾ると二人の力で願いが叶ったり、悪いものから守ってくれたりするらしい。 実在するかも分からない二人が、どうして何の関係もない人たちの願いを叶えてくれるのか、カカシにはよく分からないことだった。けれど何かの力にあやかろうとするものが、この世の中には沢山あることを少年はそこはかとなく感じていたし、それが下心からくるものでもないというのも、分からないでもなかった。季節の移ろいを感じるには彼はまだ幼いが、春夏秋冬どの時期にも何かしら意味を持った催しがあることに、心が弾むのは間違いないのだった。 「短冊を見て、父さんは喜んでたけど・・・」 はやく一人前になって、父さんと一緒に任務をすること。がちゃんと大きくなってくれること。そのどちらにも偽りはなかった。ずっと抱えてきた大事な気持ちだ。それを聞いた時のサクモの顔はとても誇らしげで、カカシは思ったのだ。きっとこの先ずっと、あの父の顔を忘れはしないだろうと。 「・・・でも」 もぞりと体を動かして、カカシは定位置でもあるの、横腹と腰骨の間の窪みに顔をうずめた。洗ったばかりの良い匂いが鼻をくすぐる。心なしかまだ毛が乾ききっていないものの、空気を含んで一回り大きくなった愛犬の毛はとても気持ちが良い。 「本当はもう一つ書きたかったことがあったんだ」 ひくひくと揺れ始めたの手足。どうやらいつのまにか眠りに落ちていたらしい。けれど本音を漏らすにはこのぐらいがちょうど良いか、とカカシは深く息を吐いて、揺れるの肉球をそっと撫で始めた。起きる気配は全くなく、自分の手足にはついていないクッションをふにふにと押しながら、一人吐露し続ける。 「一人前になりたいのに、矛盾してる気がして」 だからカカシには書けなかった。書こうとして、ふと手が止まってしまった。 「・・・父さんと、もっと一緒にいたい、なんて」 |
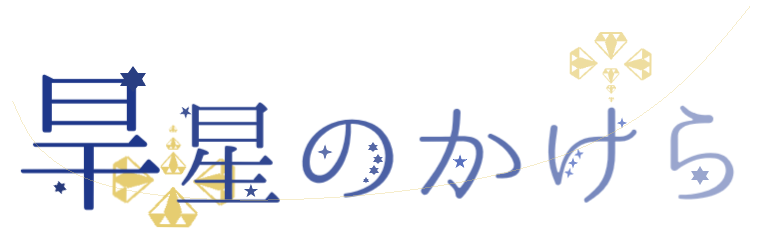
|
いつの間に息子は自分の隣に立ちたいなんて言うようになったのだろう。それを成長と人は呼ぶのだろうか。あまりに傍にいてやれないものだから、知らぬ間に、本音を隠すようになってしまったのではないか。 考えるのはいつも息子のことばかりだ、とサクモは思った。この調子ではいつか任務で大きな失敗をやらかしかねないという危惧もあるが、己の息子のことだ。どれだけ考えようと悪いものではないし、誰に文句を言われる筋合いもない。幸い三日間は休みが保障されていることだし、帰ったらみっちり修行に付き合おう。 肩の力を抜いて、サクモは近道で帰ろうと家屋の屋根へと飛び上がった。開けた視界のいたるところで、七夕飾りが揺らいでいる。耳を澄ませば風で笹の葉が互いにこすれる音がほのかに響いて、それは、夏を迎えた里にやわらかな音色を運んでいた。 「おだやかな朝だ」 この景色を守ること。人々が安心して眠りにつき、希望を持って朝を迎えられること。この一秒を、この一瞬の連続を絶やさないこと。そのために、自分は生きている。忍であろうとなかろうと、そんなものは関係ない。ただ守りたいのだ。 争いのない世界で、誰もが笑ってそれぞれの時間を育んでいく。そういう毎日のために、刃を磨き、肉を割き、死臭を嗅いで、朽ちた魂から生えた大地を日々踏んでいる。 「どうか、全ての願いが叶わんことを」 そしてサクモは胸の内で願った。 息子が書くのをためらった祈りも、どうか叶うようにと。 (2020.9.22) CLOSE |