「!晩ごはんだぞ」 新しい家族を迎えてから早ひと月、という名前を与えてもらったあの仔犬は、すっかりとはたけ家の暮らしに慣れたようだった。 来たばかりのころは終始鼻先をひくひくと揺らしながら家の中を冒険したものだが、今はもう自分の定位置をいくつか見つけたらしい。その中の一つが窓際に置かれた自分専用のふかふかのクッションであり、今もカカシに呼ばれるまではその場所で、春の暖かな夕風を感じながらすやすやと夢の中にいた。「ごはん」の三文字に耳をぴくりと動かせ、パチリと目を開けば、一日の中で最も楽しい時間がやってきたのだということに気が付く。胸を躍らせて尻尾を左右に振りながら飼い主の元へと走ってくれば、胃袋を満たす宝がすぐ目の前に。はやくちょうだい、とでも言いたげな視線は、もはやカカシというよりはその手に持たれた器に注がれていた。 「よしよし、おすわり」 期待に胸を膨らますがしっかりと座ったところを確認すると、カカシは頭を撫でながら「オッケー」と許可を出す。 時々パックンが通訳として間に入ってくれることを抜きにしても、はとても利発だった。最初に覚えた言葉は自分の名前。名前という概念が元からあった訳ではないが、小さい生きものにしろ大きい生きものにしろ、なにかとその言葉を発するので、よくよく観察したらば食事を持ってきてくれたり、外へ連れて行ってくれたり、身体を撫でてくれたりするではないか。そこから「」という言葉が、自分にとってなにか良いことを齎してくれる一番の合図だということに気が付いた。 そして次に覚えた言葉は「ごはん」だった。「」とともに「ごはん」が続くと、それは食事の知らせであり、そのあとに「おすわり」が続くといよいよ待ちかねた時間が始まる。そうやって自分の身に起こる良いことだけを拾っていくことで、はどんどん言葉を覚えていった。もちろん、小さい生きものが「カカシ」であり大きい生きものが「父さん」という区別らしいということも。 「ほんといい食いっぷりだなあ、」 まだ暮らし始めてひと月ほどではあるにしろ、飼い犬の胴体が一回りは大きくなったように感じた。足の太さから見てもサイズは中型犬から大型犬ほどの大きさのようで、その成長がとても待ち遠しい。 未発達な消化器官を助けるためにドッグフードはふやかされていたのだが、その分容器一杯になったそれはにとってたいそうなご馳走に見えていたことだろう。ガツガツと口の中に入る分だけフードを詰め込む仔犬を、カカシはその横にしゃがんで頬杖をつきながら微笑ましそうに眺めていた。 そんな折、後ろでドアの開く音がした。父が帰ってきたのだと喜ぶカカシが立ち上がると、急いでいたのか息を切らしているサクモが施錠することもそのままに、靴を脱ぎ捨ててこちらへやってくる姿が目に映る。普段の父の所作ではないその異様さに、一体何事かとカカシとちょうど食事を終えたが視線で追えば、相当な速度で走って帰ってきたのだろう彼の頬は赤くなっていて、さらには髪の毛も乱れていた。しかしその風貌から不安は感じられない。それどころか、荒い呼吸を繰り返しながらも口角が上がっていることから高揚が窺えた。 「カカシ、、花見に行こう!」 |
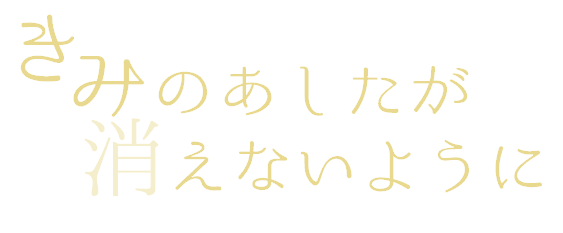
|
サクモとカカシが手を繋ぎながら道をゆく。もちろん、首輪とリードを付けたも一緒に連れて。つい先日犬塚動物病院にてワクチン接種を終えてから、はめでたく散歩が解禁となったのだが、初めて訪れる場所では物珍しさやその匂いを覚えようとしているからか、まだ短い鼻先を懸命揺らして念入りにチェックしながら歩くので、それにともなって親子の歩みもまた愛犬同様やおらかになっていた。 しかしそのゆっくりとした感じがまた良い。普段足早に通り過ぎて行く町中を、こうして時間をかけながら歩くのは中々貴重なものだとサクモは思った。忙しさにかまけていると大事なものを失うとはよく言ったもので、彼は家族と過ごす時間の大切さを噛み締めながら、繋いだ手から伝わる息子の温もりをより一層感じようと力を強める。すると、なんだろうと小さな頭がこちらを向くものだから、彼は何も言わずに優しく微笑んだ。 途中店に立ち寄って酒やつまみなどを軽く買い込んだせいもあり、目的地である第九演習場に到着したころには、濃い朱色だった夕方の空がすっかり濃紺に変わっていたのだった。 「ほら、桜が綺麗だろう、すっかり満開だ」 演習場のさらに奥地にある目当ての場所。その少し前からサクモはカカシからのリードを受け取り、「素晴らしい景色を見せたいから」と息子の両目を後ろから大きな手でそっと覆っていたのを解放する。 「わ・・・す、ごい・・・!」 瞼を開く瞬間が、スローモーションのように感じられ、現れた世界に思わずカカシは息を呑む。そこは、二人の立つ位置を中心軸にして三百六十度全てが桜の木で覆われた場所だった。柔らかな淡い桃色の花びらが幾重にも重なって風景に溶け込み、そのどれもが大地から栄養を吸収し巨木となった太く立派な枝から、扇を描くように満開に咲き乱れている。留紺色の夜空が桜を一層鮮やかにし、月明かりがこの季節の花の持つ独特の侘しさを含んだ美しさをひき立てている。時折緩やかな風が吹けば、その方向に従って枝がざわめいた。すると雪を想い起こさせるようにひらひらと花びらが舞い降り、それを何度も繰り返したのだろう、地面はすっかり桃色にでき上がっていた。 カカシの両の目に映ったパノラマは、まるでいつか見た芝居の世界のようだった。 「こんなところがあったなんて・・・」 幼いながらもその美しさに心を奪われたカカシが、景色を目に焼き付けようとくるりと回りだす。その様子が面白かったのか、は尻尾を振って一吠え上げている。 そんな一人と一匹にサクモが目を細めその場に腰を降ろして胡坐をかけば、すぐさま「くぅん」と鼻を鳴らしながら足の間に飛び込んでくる柔らかな肢体。その背中を撫でていると、ひらりと一枚の花びらが黒い鼻の尖端―好奇心からしっとりと濡れていた―に落ちてきたので、はぶるりと顔を震わせて異物を取ることに執心し始めた。 「実はね、さっきミナトくんに教えてもらったんだ」 「ミナトくんって、あの金髪の?」 「ああ。ばったり出くわしたと思ったら、凄く嬉しそうにここの桜が綺麗だと言っていてね」 ミナト―それはサクモの友人でもある自来也の教え子の波風ミナトのことだった。時々家にやってくるこの少年―いや、もう青年と呼ぶべきだろうか―とはもちろんカカシも面識があり、数えるほどしかないとはいえ一緒に食事をしたこともあった。そんな彼と任務の帰りに偶然出くわしたらしい。久方ぶりの青年はサクモを見つけるなりすっとんでくると、とても興奮した声音でこの演習場の桜のことを話をしたのだそうだ。 「一面桜なんです、でも凄く穴場なんです」と手振りもつけて力説されたのでは行ってみるしかあるまいと一人で来てみれば、なんと素晴らしい景色が待っていたことだろう。彼が興奮するのも頷けるとサクモはぐるりとその場を一周しながら、次第にこの景色を息子に見せることで頭が一杯になっていた。都合が良いことに今日はもう任務は入っていなかったし、それで思い立ったが吉日と急いで家に戻ってきたのだ。 「カカシ、ご飯にしようか」 そう言うとサクモはビニール袋からさきほど店で買ったものを取り出した。おにぎり、おでん、冷奴、桜餅、鮭とば、酒、緑茶、仔犬用ミルク―そこそこのものが集まったのではないだろうか、と彼は並べながら思った。 袋の上に乗せられる品々にカカシもも興味津々だ。その姿を横目にサクモはおでんの蓋を受け皿に仔犬用のミルクを開けると、それを手前に置いてから足の間にちょこんと居座る仔犬の尻をぽんぽんと叩いてやる。するとは甘く香り立つ匂いに誘われて地面に降り、くんくんと一嗅ぎしてから思わぬご馳走にありつくのだった。 「おにぎりの具材は梅と高菜と昆布にしたんだがカカシはどれがいい?」 「父さんは?」 「そうだな、お前が選んだやつ以外かな」 はは、と笑ってサクモはカップ酒の蓋を開けた。アルコールの匂いがカカシの鼻にもほのかに届く。 息子がおにぎりを選ぶのを見守りながら酒を一口含めば、それは任務の後の身体を癒すようにじんわりと染み渡っていった。一人で飲む酒もいいものだが、今日はなんといっても隣に息子がいる。しかもこんなに美しい空間の中で二人一緒に。 いつかこの子が二十歳を迎えたら、そのときは一緒につまみを囲んで酒を楽しみたい。そういう楽しみが未来に待ってると思えば、親というのはなんと希望に溢れ楽しいことだろう。 「高菜か、渋いな」 「父さんのチョイスが全部渋いんだよ」 もしかしたら父は最近はやりの「ツナマヨ」なんて言葉知らないのかもしれない、とカカシは思った。 「ま、でも全部好きな味だけど」 「はは、酒に合う基準で選んじゃったかな」 ぽん、とカカシの頭にサクモの手が乗せられる。節くれだった父の手から感じる、温かな体温。普段より少しだけ高いだろうか。きっと酒のせいに違いない。それに走って帰ってきた父の顔に浮かんでいた赤よりも、酔いで浮かぶそれの方が濃く感じられる。肌の白さと月明かりでカカシには余計そう見えてしまった。そんな父をじっと注視すれば、彼は陽気に微笑を返す。 (父さん、たのしそう) 子供の目に酒という飲みものは不思議に映った。大人はたいていこれを好んで飲んでいて、体内へと流し込めば途端花が咲いたかのように明るくなる。酒とはそういう不思議な飲みものだ。時折過剰に怒ったり泣いたりするタイプの人間もいるものの、父にその気はなかった。頬も耳も赤くして、緊張の糸が途切れてしまったみたいに笑い出す様からはかっこよさは見出せないものの、けれどもどこか微笑ましい。 酒を含んだ父のゆるやかさが自分との距離を近くするような気がしたカカシだった。 * 最近はこんな任務をしてきただとか、新作の自分の料理の味はどうだったかとか、今日はどんな一日を送ったのかとか、次から次へと話をするうちに、気付けば話題はのことになっていた。 「すっごくお腹が空いてたのか、今日なんかご飯食べきるの三十秒もかからなかったんだ」 「へえ、こりゃ大きくなるなは」 「・・・あ、そうだ、この前パックンがのこと教えてくれたんだけど」 刹那、息子の瞳に翳りが差したのを父は見逃さなかった。その一方で自分の名を発する音に、すっかり空になった器を名残惜しそうに舐めていたが耳をピクリと動かし顔を上げる。 「もしかしたら、育児放棄だったのかもって」 ふとやってきた重たい話に、サクモのカップを持つ手が止まる。それが口元まであがることはなかった。そして、酒を横手に置き、話題の主を一瞥すれば。 こちらに向けられたきらきらとした瞳が、「かまってちょうだい」と言っていた。それを助長させるかのように、は桜の絨毯の上で腹をむき出しにして体を捩って転がり出す。 愛犬の姿を眺めながらカカシは続けた。 「こいつ好奇心旺盛だから、里の近くまで来ては人に触られていたみたいで」 パックンの話によれば、沢山人に触られたことで人間の匂いが染み付いてしまい、母親がその匂いを恐れて育児放棄をしてしまった可能性がある、とのことだった。 そんなこともあるのか、とその時カカシは感じたが、サクモにとっては納得のいく話だった。例えばアカデミーで飼育されているウサギがそうだ。折角子供が生まれても、そこに人の手が加わってしまうことで、出産後感覚が鋭敏になった母親が自身の匂いと異なる匂いを嫌って一切育児をしなくなってしまうのだ。その状況に陥ってしまってもアカデミーだからこそどうにでもなるが、自然界ではそうもいかない。自分の子供であるにもかかわらず、そうした匂いの元から離れるために巣を変えてしまう動物だっている。 きっとは自分たちに出逢う前に何度か人間を目にし、良くしてもらった経験があるのだろう。だからこそあの時自分たちの前で平気な顔でじっと座っていたのだろうし、また、こちらが離れればその後を追いかけてもきたのだろう。そのことを思えば一緒に暮らすことにしたのは、良い選択だったのかもしれない。息子の笑顔を増やしたいというエゴからだったとはいえ、結果から見ればきっと双方にとって良いことだったのだ。 「そうだったのか・・・」 「・・・こんなにきらきらした目をしてるのに」 好奇心旺盛がゆえに生きていく環境が厳しくなってしまうこともあるのだな、とカカシは目の前で転がるをそっと抱き上げた。まだ短い手足、短いマズル、もこもことした子供っ毛。こんなにも愛らしいのに。そんなカカシの気持ちを知ってか知らずか、は尻尾を振って彼の鼻頭を一舐めした。 「もしかしたら、きっとうちに来る運命だったのかもしれないね」 「え?」 「・・・そう考えたら、つらいことはもう昔話だ」 目を細めたサクモを見上げれば、月光が彼の髪をきらきらと輝かせていた。その輝きが父の話に説得を持たせるかのようにカカシの瞳に映る。つらい過去はもうおしまい、これから一緒に楽しい思い出を作っていけばいい。魔法のような言葉が胸に広がる。 「うん、そうだね」 「しっかり守ってやりなさい」 強めに息子の髪を撫でたその瞬間、横から強風が吹きつけた。葉や桜の擦れる音が二人の耳に響いては抜けていく。大地を覆っていた花びらが風に乗って宙へと浮かべば、粉雪のように見事な桜吹雪が作り出されて。 舞い上がる淡紅色の嵐を追いかけようと、はカカシの腕から脱走を試みた。しかしその温もりを逃がすまいと少年も負けじと力を込める。そんな息子の姿を目に焼き付けながら、サクモは思った。このひと月でが大きくなったように、息子もまた成長しているのだと。そして、大切な者を守りたいと思う心はこの世に存在するどんな宝石よりも美しいと。 横手に置いたガラス瓶を再び持ち上げてみれば、そこには花びらが水面に浮いていて、さらに上弦の月がゆらゆらと映りこんでいた。 (これまた粋な飲みものに) 花びらごと水面をごくりと口に含んで、膨らむ華やかな香りに酔いしれる。ピリリとした辛味と旨味が舌を滑って流れていくその喉越しの良さは、まるで淀みのない小川のようだ。 そんな風に、これから時が流れていけばいいのに―…。 まだ当分は終わらないだろうこの時間を堪能しながらサクモは、隣でじゃれ合って体に花びらを無数にまとうカカシとを愛おしんだのだった。 (2016.3.15) CLOSE |