まだ寒さの残る季節だというのに、その墓には数えきれないほど多くの青々とした雑草が根を生やしていた。それは同時に最後にここへ訪れた時からの期間も表していて、一本一本丁寧に引き抜くサクモの顔はどこか申し訳なさそうだ。そんな彼の顔を横目に、カカシもしゃがみこんで雑草を抜く。「木の葉の白い牙」と他国から恐れられる男の息子だけあって、彼は草むしりも器用にこなしていた。そう、根を残さないよう深くからごっそりと。 その姿を今度は反対にサクモが墓石の端から捉える。きっと妻が生きていたなら、こうして草をむしる姿ですら喜んだことだろう、と彼は目を細めるのだった。 |
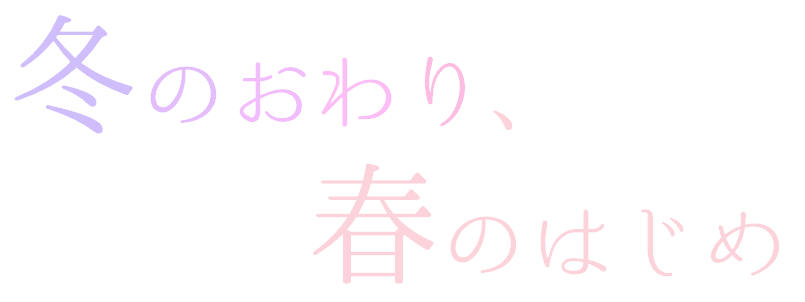
|
「今これを片付けてくるから、ここで待っていなさい」 「うん」 墓参りを終えたあと、桶を片付けるからとサクモはカカシに共同墓地の入口で待つよう指示し、なるべく早く戻ろうと急ぎ足でその場を去っていく。普通の子供ならば、里の外れのこんな場所に一人で放りだしでもすればそれこそ非難轟々といったものだが、忍の一族に生まれた子供はどちらかといえばその行動を見守られがちである。もちろんそれは信頼からであったし、アカデミーに入る前とはいえ、一人で待つぐらいできねば忍として生きていくなどお話にもならない。だからといって尽きることのない心配の波が後を絶たないのだから、その気苦労もひとしおだ。 そんな父の心などまだ分からぬカカシは、サクモが桶置場のある無人の建物へと向かうために角を曲がってしまうのを確認すると、百八十度向きを変えて辺りの景色に目をやった。かなり近い距離間で埋めれらた、見渡す限りの梅の木々。幼いカカシが梅と桜の違いを知ったのはほんの最近のことであった。 つい先日サクモが任務から帰宅した晩に、梅の花びらがきれいな状態で落ちていたのだと見せてくれたことがあった。五枚の花びらがきれいにそろったそれで、父はどうやら栞を作るらしい、部屋着に着替えることもそのままに彼は書棚から分厚い辞書を取り出すと、その中ほどのページにそっと入れ込んだのだ。父がとても嬉しそうな顔をするものだから、カカシはそんな父と話がしたくて「梅と桜って何がちがうの」と質問すると、そういう何気ない問いが嬉しかったのか、はたまた梅を無事に持ち帰れたことに満足していたからなのか、彼は息子が眠りにつくまで非常に饒舌にその両者の違いを語り続けたのだった。 そんなことを思い出しながらカカシが梅並木と化した、墓地から里へと続く一本道を手前から順に眺めれば、これは佐橋紅だとか、あれは水心鏡だとか、こっちは残雪でそっちは日月だとか、それはそれは様々な梅が花を咲かせていることに気が付いた。中でも花びらの先が尖っているものを見つけた時、彼には再び父との会話が想起された。梅と桜の基本的な見分け方は、花びらの尖端が丸みを帯びているのか尖っているのかのどちらかなのだが、とはいいつつもだ、どうやら花びらの尖端が尖っている梅もあるらしい。紅筆や古金欄といった種類のものがそれに該当するとのことで、それに注意しておくようにとカカシは聞かされたのだ。花の名前を全て覚えることはかなわずも、そういう普通から外れたものもいるのだというぐらいのことは頭にまだしっかりと残っている。 (てことはこれも梅なのかな) 任務で忙しく、あまり家にはいない父との数少ない思い出。それを噛み締めるように、カカシはより花の咲いている高いところへと視線を移した。早春の空がひらひらと舞う花びらを鮮明に映し出し、もう春何番目だろう風がそれらの木々から香り立つ梅特有の馨香を遠くまで運んでいく。それはまるで、冬の終わりを告げに来た春の精のようだった。 風に乗って目の前に落ちてくる花びらを視線で辿って顔を下げる。すると、ふと背後に感じる何かの気配。くるりと振り返ればそこには、どこからやってきたのか一匹の犬―マズルや足の短さ、頭と胴体のアンバランスさからそれが仔犬であるとわかった―がちょこんと「おすわり」をしていたのだった。 (なにこのもふもふ・・・) 柔らかそうな毛並みのなんと触りたい衝動に駆られることか。 円らな瞳が一心に自身へと注がれるものだから、その愛らしい瞳にカカシの胸がざわざわと揺れはじめる。可愛さの魅力に取り付かれてしゃがんでみれば、何かしてくれるとでも思ったのだろうか、期待に満ちた仔犬が口を開いて、はっはと呼吸しながら桃色の舌をぺろりと出す。 「どこからきたの?おまえ」 そう言うとカカシはついぞ我慢できずに手を仔犬へと伸ばした。ああ、このもふもふでわふわふがもうすぐ手に。少年の瞳もまた仔犬と同様、期待で揺れていたのだった。 「おまたせ、カカシ」 あと数センチ。そんなところで桶を片付けたサクモが小走りでやってくる。父親の声に気付くや否や、カカシは伸ばしかけた手をさっと引いて立ち上がる。そんな少年とは反対に、仔犬は動じることなく座ったまま新たに登場した人物を見上げた。少年に向けたあの期待を含んだ眼差しと同じように。 「おかえり、父さん」 「ただいま。この犬は?」 「後ろ向いたら、急にいたんだ」 「へえ。まだ仔犬だ、かわいいね」 柔らかく目を細めるとサクモは屈んで仔犬の頭をそっと撫でた。力を入れていないのに彼の手が仔犬特有の細い毛に沈んでいく。頭を数回全体的に撫でられたかと思えば眉間を親指が上下に這っていくので、まるで溶けていくみたいに子犬の表情が緩んでいった。 「ほら、お母さんの元へおかえり」 その気持ちよさからとうとう欠伸が出てしまった頃合を見計らって、サクモは仔犬の尻を軽く叩いて家へ帰るよう促す。ぱっと見たあたりまだ生後二、三ヶ月といったところだろうか。となればきっと母犬が心配しているに違いない。どんな将来を歩むとて、親といられる時間は人生のうちで非常に少ないのだから、少しでも一緒にいられる方が良い。 それはまるで妻に想いを馳せる自身の、そして残された子供に対する愛情と重ねるかのようであった。 「・・・父さん、動かないね」 「動かないな」 仔犬はくぅん、と二人を見つめたまま動く気配がない。その円らな瞳には大小の人間二人が目を合わせる様が映る。 「・・・」 「・・・」 そして再び二人の視線が仔犬に戻されると、自然と左右に動き出す尻尾、尻尾、尻尾。 感情を素直に表現するからこそ、そんな仕草が二人の心を鷲掴みにする。うっ、と内心息を詰まらす二人。特にカカシは陥落寸前だ。そんな息子の横でサクモは揺れる思いをなんとか断ち切り、再度尻を叩いてやるがしかしそれでも仔犬は動かない。それならば仕方がない、こちらから離れるしかないとすっくと立ち上がって息子の手を引けば、哀愁漂うそのまなこ。また別の思いで息の詰まるサクモであったが、情に流されて命を拾ってやることはできなかった。 「カカシ、行こう」 「・・・うん」 後ろ髪を引かれる思いでくるりと踵を返して歩き出す。段々と小さくなっていく仔犬を尻目に帰路に着けば、寂しさもひとしお。儚げな色を浮かべる息子の気を逸らそうと、サクモが夕食の話を持ち出した、のだが。 「ねえ父さん、着いてくるよ」 「え?」 「あいつ、追っかけてくる」 言われるがままに立ち止まって振り返れば、先ほどの仔犬が後を追いかけてくるではないか。小さな歩幅で必死に前へと駆けるその姿は人の目になんと健気に映ることか。ぴょこんぴょこんと耳も揺らしてくるのだから可愛さも相俟って、またも心が揺さぶられてしまう。 母犬はどうしたのだろうか。兄弟姉妹はいるのだろうか。それとももしかしてひとりぼっちなのだろうか。そんな不安がサクモの胸を襲うが、それでも鬼の心で再び歩き出す。けれどどこまでも仔犬は二人の背中を追っていく。そうして振り返っては歩き出しを何回か繰り返しているうちに、すっかり家の前まで来てしまったのだった。 (困ったな・・・) そんなサクモの心を知らない仔犬は、出会った時と同じきらきらとした眼差しで二人の前にちょこんと座っている。仔犬の愛くるしさにとうとう我慢が効かなくなったカカシは、父の手からするりと逃れるとそのまましゃがみこんで仔犬に触れようとするも、どうやら仔犬の方が一歩早かったらしい。次の瞬間にはカカシの懐に勢いよく飛び込んできたのだった。 想定外の行為に思わずカカシは尻餅をつく。するとその動きが新鮮で嬉しかったのか、仔犬ははち切れんばかりに尻尾を高速に振り続けながら、自身の下にある少年の顔をぺろぺろと舐め倒した。 「わっ、ぶっ、ちょっと、息できっ・・・っはは、こら、」 くすぐったいと漏れる息子の笑い声と、嬉しそうにじゃれ続ける仔犬の姿は至極楽しそうで、すっかり薄暗くなった時分にも関わらず、彼らの姿はサクモの瞳に色鮮やかに映ったのだった。 (・・・カカシがこんなに笑ってくれるのなら) 情には流されぬと心に決めたけれど―…。 妻を失くしてからというもの、任務だからと家を出て行く時に息子はどんな表情をしていただろうか。小さいくせに出来た子供だから、気丈に振舞いつつもきっと寂しい思いをさせていたにちがいない。普段忍犬であるパックンをお守りに置いているとはいえ、任務内容によっては彼もまた連れて行かねばならない。外で活発に遊ぶタイプではないから、家で一人の時はどうやって過ごしていたのだろう。 その思い出が、いつだったかの晩をサクモに思い起こさせる。あれは夕飯までには帰ると言った日のことだった。思った以上にてこずって、結局帰宅したのは真夜中だったのだ。万が一のことを考えて、温めればすぐに食べることのできる食事を冷蔵庫にしまっておいたが、それに手はつけられておらず、肝心の息子はといえば居間で自分を待っていたのだろう本を片手にぐっすり夢の中にいて。すまないことをした、と寝室へ連れて行こうとした時、思わず落としてしまった息子の本を拾い上げて気が付いたのだ。ページの角がしわしわになっていたことに。さらによく見れば指先が当たる部分だけ手垢や手汗で変色していて、何度も何度も読み返していたことが窺えた。 サクモにとってこんなにも辛いことはなかった。愛しいわが子だというのに。なに不自由なく過ごさせてやりたいというのに。まだ乳呑み児だった息子の世話に奔走する日々が、そう、妻の死を悲しむ暇を与えてくれなかった日々が自身にとっては逆に良かったかもしれない。けれどカカシは?人肌に温めたミルクを飲ませ、げっぷをさせるとけらけらと笑う顔は自分にとって大きな救いだった。どんなに血みどろの任務だって、息子がいるから耐えてこれた。家に帰ってきて安らかに眠る顔を見れば、こちらの疲れも吹き飛ぶというものだ。けれどカカシは?つまるところ、光を与えてやらねばならない身でありながら、自分は与えてもらう側にいたのだ。だからこそ苦しかった。息子に中々構ってやれないことが。 「カカシ、今日からこの仔を家族にするのはどうかな」 「え!いいの?」 その言葉を聞いた少年の目は今日一番にきらきらと輝いていた。抱え上げた仔犬を胸にぎゅっと寄せると、彼もまた嬉しそうに尻尾を振りながらカカシの首元を舐める。 そんな一人と一匹に目を細めたサクモは、そのまますっかりと顔を出した月を見上げ、今はもう遠いところにいる愛しき人に思いを馳せるのだった。 (2016.3.13) CLOSE |