「あのさ、いくらなんでも働かせすぎじゃねーの?」 「お前は・・・。これで三度目だぞ」 火影の執務室にて数え切れない程の書類に目を通す傍ら、綱手はナルトを前に盛大にため息を吐いた。彼女は片側の頬をひくひくと引き攣らせながら、眼光鋭く金髪を射すくめたのだが、苛立ちはそこで治まらなかったのか、手中にある資料に幾重にも皺ができていくのが見て取れる。その光景を前に、窓辺に立つシズネはトントンを抱えながら苦笑いを浮かべていたのだった。 「たまに帰ってきても死んだみたいに寝込むし、ほんと辛そうなんだってばよ」 「そんなことは分かっている!こっちだって休ませてやりたいがにしかできない案件が溜まってるんだよ」 「だーかーら、ねーちゃんにしか駄目ってどういうこと?」 「守秘義務だ、喋る訳にはいかん」 ずんむくれたナルトに綱手は再びため息を吐く。彼女とて彼の言い分が分からぬほど鬼では無い。むしろ任務に送り出す身だからこその過酷さを十分に理解している。少なくとも目の前でああだこうだと喚き散らす、図体ばかり大きい子供よりも。 しかしいくら様々な特性を持つ忍がいるとはいえ、任務の性質上誰にだって向き不向きはある。現に目の前にいる金髪の青年は戦闘力はずば抜けて高いが、かつての彼の師であるはたけカカシが、意外性ナンバーワン且つ目立ちたがり屋と称していたように、暗部のように影に身を隠すタイプではない。諜報にまわすより野党退治の方が向いている。反対にはナルトほどの戦闘力は無いものの、暗部の人間として長年生きてきたためか、戦況を読むことに非常に長けている。判断力に優れる彼女には当然単純な任務よりも、複雑な戦術を必要とする任務が宛がわれる。オールマイティに動ける忍ほど任務遂行には欠かせない存在だ。 さらに言えば多くの忍に里の重要な機密を語らぬためにも、信頼のおける僅かな側近に負荷がかかってしまうのは致し方の無い話で、しかしそれは誰が指示を出す側だろうと一緒だ。硬い言い方をするならば密な主従関係といったところか。 「お前ももう大人なんだから好い加減我慢を覚えろ」 「なあ、ねーちゃんの任務を俺に回してくれよ」 「あいつには医療忍術で少しは疲労を回復してやっている。死にはしないよ、ほら、さっさとお行き、私は忙しいんだよ」 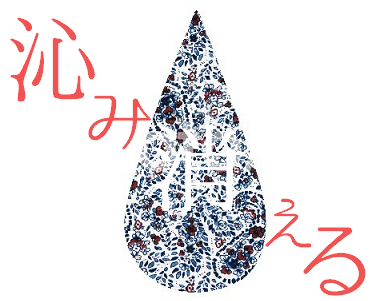 落ち着かない。昨日も、今日も。いや、そんな数日の問題ではない。なにせかれこれもう三週間だ。 そんなナルトの心を掻き乱すのは言わずもがなのなのだが、その彼女はといえば何日ぶりかに帰ってきたかと思えばすぐに出て行くか、または布団に入って寝入ってしまうかのどちらかで、ナルトとまともに会話が出来る状況にいなかった。原因が日々舞い込む任務であることも言を俟たない。びっしりと隙間無く敷き詰められた石のように、この三週間彼女は休む暇も無く働かされていたのだ。平生ならば視野も広く人の気持ちにも敏感な彼女だが、こうも任務漬けの状態が続くとそれも中々ままならい。とにかく疲労を減らすために身体が自然と他の事柄に無気力になるのだろう、睡眠(最早仮眠だが)と任務というこの二つだけが今の彼女の精神を動かしているのだった。 ナルトが声をかけようとも叩こうとも全く気が付く気配は無く、彼は彼女を、そう、忍という自覚があるのかというぐらい深い眠りに落ちる彼女を眺める度に、胸が締め付けられる思いに襲われていた。手を伸ばせば触れることのできる距離に想い人はいるのに、まともに目が合うこともなければ声を交わすことも出来ない。自分をいざなうあの美しい瞳や声はとても遠かった。行かないでくれ、俺と一緒にいてくれよ、なんて口が裂けても言えるものではないし、そんなくだらないことを言いたいのでもない。 ただ里の為に働く彼女を、一緒に暮らす身として労いたいだけなのだ。なのに心がどうしても彼女を求めてしまう。勿論それは任務だということを十二分には理解していても、だ。笑ってほしいし、名前だって呼んでほしい。抱きしめたいし、キスだってしたい。しかしそのような考えの一つ一つは、所詮は自分勝手な欲望に過ぎない。子供じみているとすら思ってしまう。だって彼女は今は自分を押し殺して必死に生きているのだから。 煩悩じみたことを思ってしまう申し訳なさと、一緒に暮らしているのに何一つ力になれない自分の非力さと。けれどその気持ちを抱くのと同じくらい、自身の欲求を叶えたいと感じる心と。今までに経験したことのない様々な感情の織り交ぜに、ナルトはに何を言ったら良いのか解からなくなってしまったのだった。 (あ・・・) 時折、夜明けに風呂から聞こえるシャワーの音に目を醒ましてはナルトは頭まですっぽりと布団を被り、暗い空間の中で外界から聞こえる音にしかめっ面と共に耳を欹てる。 新たな任務へ向かうために、前日の汚れを落しているのだろう。ただその時間は酷く短い。ものの数分だ。浴室のドアの音の数分後にドライヤーの風が吹き出し、さらにその数分後には家の鍵が閉められる音がする。ちゃんと朝食は取っているのだろうか。いや、取っているはずがない。携帯食料か兵糧丸で済ませているに違いない。ナルトはそのようなことを思うと、心の奥底からやるせない気持ちが込み上がってくるのを感じた。 そうしてひとたび眠りに付けば、次に彼が目覚めた時にはもうそこにはいないのだ。温もりすら残っていないベッドには、人肌を失ってすっかり冷えてしまったシーツと布団があるだけ。ぽかりと空いた心を抱えながら、無心で着替えて己も任務に就く。アカデミーの子供たちに特別講師として体術を教える時も、仲間と共に里外へ飛び立つ時も、どこか遠い目で寂しい心を紛らわそうと必死になる瞬間が生まれる。すれ違い、とは少々違うが、彼女と気持ちが通じ合わないばかりの日々に、青年の精神は砂漠のように干からびていくのだった。 * そんなことを何度も繰り返し、今日もそれは訪れる。 陽が昇り始めて間もない頃、扉の開く音でナルトははっと目が覚めた。勢いよくベッドから飛び降り玄関へ向かうとそこには四日ぶりのの姿。傷こそ負っていないものの、溜まりに溜まった疲労が前面に出ているのは明らかで、その憔悴は彼女の顔からつややかな血の気を消し去っていた。 「ナル、ト」 虚ろな彼女の瞳が青年を捉えた。 時間にして一秒にも満たなかったとはいえ、しっかりと目が合ったのは一体いつ以来だろう。ナルトの心に一滴の温かさが落ちるのも束の間、意識を失ったの身体が力なく前に倒れ込む。 「ねーちゃ、っととと」 それをナルトはしっかりと受け止め、大丈夫だろうかと顔を覗き込んだ。規則正しい呼吸にほっと一息つくも疲労困憊した彼女の姿に心がざわついてしまう。とにかく身体を休ませるべく腕の中の恋人を横抱きにする。そして、何日も触れられなかった彼女の肌や重さを一気に感じながら、寝室のベッドへとそっとおろしたのだった。 少しでも安眠できるようにとベストの前を寛げる。些か細くなってしまっただろうか、苦い思いを胸にその腕を引き抜いた。するとアンダーの袖も一緒に捲れてしまい、彼女の白い素肌が腕の中ほどまで露になる。久々に現れた、服の下に隠れている肌をナルトはじっと見つめた。 白さは時にそれだけで色香を放つのだから厄介だ。彼は彼女を起こさないように(といっても例によって全く起きる気配はないが)細腕に指を滑らせる。自身の指の重さだけ沈む皮膚は冷たかった。そのまま甲を通り、力なく折りたたまれた彼女の指のその間を一本一本ほどくように指で絡め取っていく。早く愛しい温もりを、身体一杯に抱きしめたい。優しく力を込めてやれば恐らく無意識なのだろうが、ピクリとの指先が動くのがナルトは無性に嬉しかった。 「・・・ん?」 握っている手の角度を変えると、彼女の手首の内側に何か色の濃いものが付いているのにナルトは気が付いた。 「・・・これって」 指を引き抜き彼女の手を裏返せば、そこにはなんと渦巻模様の、そう、ラーメンのトッピングには欠かせないあの「鳴門」のマークが、黄枯茶色で小さく描かれていたのだった。それが何を意味しているかナルトに分からぬはずはないだろう。 言葉をまともに交わせない日々のことを彼女も心のどこかで気にしていたのだろうか。任務に追われながらも自分のことを少しでも思っていてくれたのだろうか。自惚れでもかまわない。だってそうでなければこんなマーク、描きはしないはずなのだから。子供が宝物を前に目をきらきらと輝かせるみたいに、彼の眼にも明るさが浮かび、そして頬の筋肉も緩みはじめている。 普段は中々気付けぬ些細なことも、こういう非日常的な状況に陥らねば気が付けぬなんて何とも皮肉たっぷりだが、それでも気が付けないよりはましだ。 「ねーちゃん・・・」 小さなマークがもたらした大きな喜びを胸に閉じ込めて。 ナルトはの額に唇を落とし、毛布と布団をそっとかけてやると寝室を後にした。そして彼はどうにかして違う角度から綱手を攻めれないかと、腕を組み台所に立ちながら湯を注いだカップラーメンができ上がるのを待ちつつ、寝巻きはおろかナイトキャップもそのままに、ああでもないこうでもないと思考をめぐらるのだった。 「どうにかできねーもんかな」 これまでに自分がしてきたことといえば、彼女がいつでも食べれるように簡単な食事を作りおいたり、ぐっすり眠れるように布団カバーやシーツを取り替えたりといったところか。 前者の方は虚しくも手が付けられることはなくナルトの胃袋に収まってしまったし、後者の方も「おはよう」や「おやすみ」といった簡単な会話すらないのだから、それについて言及されたこともなかった。心の内ではマッサージの一つもしてやりたいとは思えど、いかんせん帰ってきてすぐ倒れこんでしまうためにそれも叶わない。だからこそ綱手の元に嘆願という名の愚痴を何度か零しに行ったが、強気な彼女を前に勝手な願いが通ることもなく。任務と任務の間に火影の元へ報告にやってくる彼女に医療忍術で疲労回復を施しているとは言っていたものの、目に見えて足りていない。 「任務がなきゃねーちゃんだってゆっくり休めるのに」 ものを考えながらカップ麺の準備をしていたせいか、先端の折り曲げ具合が足りなかったようで、湯気の熱気に耐えられなかった蓋が曲線を描きながら捲れ上がっている。しかしそれに気が付く様子もなくナルトは只管頭を働かせ続けた。 「ん〜・・・」 にしかできない任務が溜まっているとはいえ、体調が万全でない以上いくら優秀な忍と言えども能率は下がってしまうことだろう。彼女は三週間も日夜働き詰めたのだ。急を要する任務程順序は繰り上がるのだから、そろそろそういった類の物は減ってきたと考えても良いのかもしれない。そうやって根拠の無い筋立てをしながらナルトは唸り声を一つあげた。まだまだ任務が残っていたとしても、とにかく一度うんと彼女を休ませたい。自分に課せられるであろう仕事の数々を忘れられるぐらいに。急な呼び出しを食らう里内にいたのではおちおちゆっくりもしていられない。となれば里の外に出るしか術はない。 「・・・里の外・・・って、あ!!!」 それはまるで天啓に導かれるかのようだった。閃きを得たナルトが、青い目を見開かせて口を開く。 「そうだ・・・これだ・・・、これならきっといけるってばよ」 そうと決まれば思い立ったが吉日、行動あるのみ。目にも留まらぬ速さで寝巻きを脱ぎ捨て、ベランダに干してあった服に着替えると、彼はわんぱく坊主のように目を輝かせながら家を飛び出していってしまう。 すっかりと忘れ去られた、それも三分を大幅に過ぎ伸び切ってしまったカップ麺が、ぽつりと勝手台の上で寂しげに置き去りにされていたのだった。 (2015.1.5 まだ綱手様に火影を頑張ってもらってる体で) CLOSE |