「西日きっつう・・・」 「あー調子乗り過ぎたーー!でもお肌つるつるってーの?生き返った〜」 「この体力馬鹿・・・」 昼過ぎに起きて、風呂のついでに身体を重ねて。気が付けば、部屋の中には眩しいぐらいの西日が差し込んでいて。 「時間もらえるなら俺ってばもう一回ぐらいは」 「いいです遠慮しときます」 気だるい疲れに身を包まれながらも、ナルトとは啄ばむようなキスを何度も繰り返し布団の上でくすくすと笑い合った。 「私もう一回温泉入ってこよ〜っと」 「俺も俺も」 「だめ、今度は一人でゆっくり入るんだから」 「さっき誘ったのはねーちゃんだろ」 「そうだっけ?」 「あ、ずっりーの」 布団から起き上がるの腕をナルトが掴もうとする。だがそれをするりとかわすと、彼女は備え付けのタオルを持って露台へと歩いていった。ならば入る姿をじっくり拝むとするか、とナルトは上体を起こして胡坐をかくも、窓枠に設置された簾の紐を解かれて視界をシャットアウトされてしまう。 その抜かりなさに「へっ」と悪態づきながらも、先ほどまで自分の腕の中にいた温もりを確かめるように彼女が寝ていた布団の匂いをスンと嗅いでみれば。ニシシ、と笑みを浮かべてナルトは枕に顔を埋め、嬉しさ一杯に足をばたつかせたのだった。 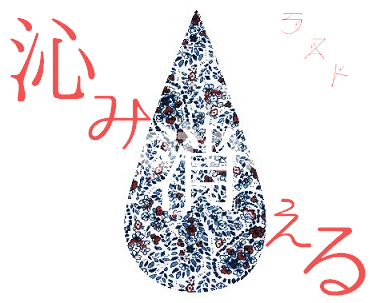 「お食事のお時間でございます」という声がしてナルトが出迎えれば、数名の仲居が入ってきて、食事は洋室と和室どちらにするかと尋ねられた。折角の旅館なのだからなにも洋室で食べなくても良いだろうと和室を選ぶと、一人だけ着物の色が違う―恐らくは仲居頭であろう―女性が笑顔で「かしこまりました」と頭を下げ、彼女の指示に従ってその他の者たちが一斉に食事の準備に取り掛かる。 一枚板で作られた机を布巾でさっと拭いてる間に、露台の温泉から上がったが部屋に入ってきた。彼女に先ほどの色違いの着物の仲居が温泉の感想を尋ねると、彼女はとても満足した顔で最高だったと伝える。それが我々にとって一番嬉しいことだと仲居は微笑み返し、着々と夕食の準備を進めていけば、「お待たせしました」と二人は席へと案内された。そして料理を持った仲居が襖を開けて入って来ては、次から次へと華やかな料理が運ばれてきたのだった。 ナルトももこれでもかというほど目をキラキラと輝かせる。二人は感嘆のため息とともに、宝石みたいに輝く料理にあまりに釘付けになるので、仲居の料理の説明も半分ほどしか耳に入っていないようだ。目を細めながら「ごゆるりと」と彼女たちが下がっていけば、嬉しさで尻尾をぶんぶん振る犬のように、二人は顔を見合わせて「いただきまーす」と箸を手に取った。 「ん〜〜っおいしい!」 「うっまー!もう俺どうなってもいい・・・!」 海老豆腐と湯葉の釜盛りに、鱧と三つ葉の椀物、地魚と伊勢海老の造里に山菜の蕪蒸し、銀鱈と茸の包み焼きに硝子町特産の牛ステーキ、さらには取れたて野菜の天婦羅や香の物に押し寿司と部屋のグレードならではの豪華な品々。頬が蕩けるとはまさにこのことで、これが美味しいあれが美味しいとそのどれもに舌鼓を打ちながら二人は食事を堪能した。 「ほんと幸せ・・・」 からしてみればまともな食事は本当に久しぶりだった。ただ生命を維持するだけの簡素なものよりも、五感全てを楽しませてくれるものの方が断然良い。もちろんそれは一緒に食べる相手がいてこそで、ナルトが居ればその喜びもひとしおだ。 「飯食う度にさ、ねーちゃんてば今何食ってんのかな〜とか、どうせロクなもんじゃないんだろうな〜って思ってた」 「う、間違いじゃないから言い返せない・・・」 「もう家で一人ぼっちでぼそぼそした握り飯食うのごめんだってばよ」 お互いの気持ちが通っているなら我慢のしようもあるが、そうでなければたとえどんなに豪華な食事も味気ないというものだ。 「ご、ごめんって・・・。でもね、ナルトと美味しいもの食べたいって思ってたから、今凄く嬉しいし、ご飯も余計に美味しい」 「ねーちゃん・・・!」 「ふふ。はいナルト、あーん」 「えっなになに良いの?」 「もちろん」 はくしゃりと笑みを浮かべながら、茶碗蒸しの乗る匙をナルトの口元に近づけた。世のカップルたち憧れのシチュエーションじゃないですかこれは、と頬の筋肉が緩んでいくナルトが勢いよく匙に食いつく。(ただその姿は恋人に食べさせるというよりはむしろ、魚が餌に食いつくといった方が正しいかもしれない。) 「ん〜卵がとろけてしあわ・・・ん?っげ!銀杏!!!」 「あっわかっちゃった?」 「ねーちゃんそりゃねえぜ、げーっにが!えぐ!」 「銀杏ってどうも苦手で・・・えへへ」 「ぐっ・・・」 首を傾げて笑った彼女の姿をナルトはずるいと思った。やってることは口内に放り込まれた銀杏のように可愛くないというのに。自分より年上なのに、子供のような「えへへ」がなんて似合うのだろう。その笑顔のせいで反撃する気を削がれてしまい、目の前の汗をかいたグラスに入ったお茶で銀杏を流し込む。 「う〜」 しかししぶとく残る独特の味に顔を顰めていると、自身の視界にまたも何かが差し出されたことに気が付く。訝しげに見てみれば、そこには先ほどのトラップとは違い、今にも肉汁が零れ落ちそうな一口サイズのステーキが。それはナルトが絶賛し、早々に食べ終えてしまったものだった。 「はい、今度こそ、ね?」 「ねーちゃあああん」 あんぐりと大きな口で炭火の香りのするステーキにありつけば、じゅわりと口内に広がる肉の旨みとほのかな甘み。 「うめえ・・・脂が染み渡るってばよォ・・・うっうっ」 「もー大袈裟ねえ」 「あ、そうだあのさ、飯食い終わったら連れて行きたいところがあるんだ」 「連れて行きたいとこ?」 「そ!」 * 米粒一つ残さず夕食を平らげた後、胃を落ち着かせるための休息もあまり取らずに、ナルトはをこの宿に連れて来たように横に抱きかかえて夜の世界へと飛び出した。そんなに急いだら脇腹が痛くなるぞと彼女は思いながらも、振り落とされないように彼の服をぎゅっと掴み、されるがままに吹き付ける風を感じていた。 まだまだ春の到来を待つこの日としては、陽が沈むと、去っていく冬が惜しんでいるかのように寒さを運んでくる。加えて今はかなりの速さで駆け抜けているのだから、その寒さはより一層厳しい。浴衣のまま来ないで良かったと思うも、一度風が吹けばぶるりと身を震わせずにはいられない。ナルトとの隙間を埋めるように身を寄せると、彼はそれを感じたのか彼女を抱く腕に力を込めた。 「ねーちゃん、空見て空」 「え?」 肩を縮こませていたが言われるがまま視線を空へと向けたらば。 「わあ・・・いつのまにこんな」 視界に映るはまるで金平糖が一面に鏤められたかのような星空。 ランタンの灯りがあった町から少し離れただけだというのに、別世界にでも飛び込んだように澄み渡る空を光が埋め尽くしている。多くの人が集まる観光地とはいえこの硝子町、地図で見れば周りを森に、背を山に囲まれたところに位置しているため、町を照らす人工的な明かりさえなければ殊の外星空が見やすいのかもしれない。 「ここって硝子も有名だけど星空も有名らしくてさ、でも俺もここまではっきり見たの初めて」 「前はこんな風じゃなかったの?」 「確か月が結構出てて、それで見えなかった気がすんだよな」 「そうだったんだ・・・。良かったね、今日こんなに綺麗に見れて」 「俺のねーちゃんへの愛かな!へへ!」 「ばっか」 なにを言ってるんだとくすくす笑ったのも束の間、ナルトは急降下してとある小高い丘に降り立った。そこは目の前を何に邪魔されるでもない、一等星が真正面に見える特等席。衝撃を与えないように膝を使って柔らかく降りてくれたのだろう、風が草原を撫ぜるように丘を滑っていくその草花を臀部に感じると、その隣にナルトも座り込んだ。 「えい!」 「きゃっちょっと!」 夜空を見上げるために寝転がろうとしたナルトが、倒れるついでにの肩も一緒に持っていくと、咄嗟のことに驚いた彼女は反応できずにそのまま同じように後ろへ倒れていく。 「一言言ってよ〜」 「ごめんごめん。でも寝っころがった方が綺麗だろ?」 軽く頭を打ったがむすっとした表情を浮かべるも、それが稚拙に思えてしまうほど目の前に広がる星空は荘厳だった。 「・・・うん、すごくきれい」 宝石のようでもあり、ビーズのようでもあるきらきらと煌く星の数々は、人間の瞳を永遠に奪ってしまうかのような魅力を持っている。どこかへ動いて消えてしまうでもなく、ただその場に浮かぶ星なのに、見始めてしまったら最後、いつまでだって眺めていられる気がしてしまう。 そうしてしばしの間二人は視界を彩る景色に見惚れていた、のだが、ある時ナルトがぽつりと呟いた。 「手を伸ばせば掴めそうなのに、掴めねーんだ」 「星?」 「違う、ねーちゃんのこと」 草の海に広がる恋人の髪を無骨な手でふわりと掬う。草の尖端が彼女の頬をくすぐった。 「・・・なあ、俺って頼りない?」 じっと射抜くような視線を感じてナルトの方を振り向けば、いつもの少年のようなあどけなさが消えていて、そこにあるのは真剣に一人の人間を見つめる大人の顔だった。 どきり。心臓が高鳴らないわけなかった。 「ねーちゃんが俺のこと好きって分かってる。ちゃんと分かってるのに、不安になっちまうんだってばよ」 ―ねーちゃんが、ここにいて、そんで俺も、ねーちゃんのとこにいる。もうそれで良いんだってば。 昨日言われた言葉が彼女の脳裏でふとフラッシュバックする。この言葉を言われた時、彼は随分大人になったと思っていた。それも勿論嘘ではないだろうが、でも全てがそうではなかったのだ。何よりも孤独を嫌う子供だったからこそ、その不安が今も無意識に心に根付いてしまっている。そしてそれを自分はよく知っていたにも関わらず、忙しさにかまけて蔑ろにしてしまっていた。愛情を言葉にするのも、態度に出すのも二の次にしてしまった自分はなんて身勝手なんだろう、と、は鼻の奥が熱くなるのを感じた。 (色んなことが手に付かなくなるほど、寂しい思いをさせていたなんて) ご飯食べたい、出かけたい、キスしたい、抱きしめたい。 自分の心に忠実なナルトを甘えたがりだと思うことも多々あった。はいはい、とあしらえば子供みたいに顔をむすっとさせて、頭を撫でてやれば太陽みたいに顔の筋肉を全部使って笑ってみせて。でもそんな彼の笑顔に甘えていたのは自分の方だったのかもしれない。 「ナルト、あのね」 彼の頬に、手を伸ばす。 刻まれた九尾の髭をなぞり、頬全体を覆うように手を動かせば細められるナルトの瞳。 「あなたの笑顔も、この髭も、ツンツンした髪の毛も、青い瞳も、」 は口にした箇所を順々に指先で触れていった。 「私を抱きしめてくれるこの腕も、ぎゅって握ってくれるこの手も、」 そして最後に胸にそっと手を置く。服の上からでも分かる、鍛え上げられた肉体だ。 「私を想ってくれるこの心も。・・・ナルトの全部が私には愛おしくて、愛おしくてたまらないの」 「ねーちゃん・・・」 「なのにごめんね、私、言葉も態度も足りなかったね、自分のことばっかりになっちゃって、手を差し伸べてくれたナルトのこと、ちゃんと見てなかった」 彼女の髪を弄っていたナルトの手が、自身に添えられている柔肌にするすると移る。そして彼女の腕を這うように指を滑らせて、優しく手首を掴んで手の甲に唇を押し当てた。 その忠誠を誓うかのような振る舞いにの鼓動はまたも速くなった。 「・・・ナルト、愛してっんぅ、っ」 ナルトはたまらず身を起こし彼女に覆い被さると、唇で言葉の続きと呼吸の残滓を呑み込んだ。 彼は、自分はずるい人間だ、と思った。 相手が自分を見てるなんて分かりきっているのに、それじゃ足りなくなってしまうのだ。好きで好きでたまらない気持ちと同じぐらいの、いや、それ以上の愛を求めて、捨てられてしまうのではないか、一人になってしまうんじゃないかと気持ちが制御できなくなって暴走してしまう。確固たる愛が欲しくなってしまう。欲しいのは、ただひたすらに深い愛。ただひたすらに深い信頼。 「好き。ねーちゃん、愛してる」 「うん、私も、愛してる」 「っへへ」 「・・・ナルトが思ってる以上にね、私、ナルトがいないとだめなの」 「えっ」 「ナルトと一緒に食べるご飯が何より美味しいし、お店でナルトが好きそうなもの見つけると欲しくなるし、すぐにそのことナルトと共有したいって思うし、それに、それにね、ナルトがいるから安心して眠れるの」 今にも泣きそうな顔をするの瞳に夜空の星が幾つも映るものだから、ナルトは余計にその言葉の意味を強く感じた。 きっともう大丈夫だと、一つ一つの言葉が不思議な力を持っているみたいに、靄めく何かを体内から霧散させ、代わりに充足を運んでくる。 「・・・ねーちゃん、なんだろ、すげえ心がぽかぽかする」 「良かっ、あ!」 「え?」 上空を、右から左に通り抜けた一筋の光。 「流れ星!」 「え!どこどこ!え!」 慌ててナルトは後ろを向くが、そこはすでに先ほどと変わらぬ星の群。滅多に見れない貴重なものを見逃したと頭を抱える彼に、彼女は微笑みながら「何をお願いするの?」と問う。 ナルトは後ろに広がる星空をじっと見据えた。その瞳は彼女から窺うことはできなかったが、ひどく真剣だった。そしてゆっくりと振り返ると、今度は彼の瞳は真下の恋人を捉えている。 その眼差しの一途さには思わず息を呑んだ。全ての音が遮られてしまったように、今は色を濃くするその青だけが彼女の全てを支配していた。 「なあ、結婚、しよ」 どんな命がけの任務より、どんな窮地よりも心臓が高鳴る。 「俺の苗字、貰ってくれってばよ」 「ナル、ト」 「それで、毎日俺に、味噌汁作ってください」 「・・・み、みそし?」 「・・・・・・ッ」 「っ・・・ふっ、あははっ、お味噌汁って」 「ぐううっ、お、俺ってば今めっちゃ気合いれたのにぃ」 一世一代のプロポーズなんだぞ、と照れを含んでナルトは歯を食いしばる。いつも耳を赤くするのはの方だが、この時ばかりはそうはいかなかった。 一体いつの時代の人間だと突っ込まれ兼ねない発言に、は万年口布男の「意外性ナンバーワン」という言葉を思い出した。まさにその通りだとまた頬が緩む。 「・・・だめ?」 「・・・ううん、だめじゃない。ナルトの苗字、私にください」 (2015.9.2 里に帰ったら二人はみっちり叱られました) CLOSE |