(このナマゴロシな状況はなんなんだってばよ) こちらの方をちらちらと気にしながら、少しの恥じらいと共に服を脱いでいくに、ナルトが中てられない筈がない。この三週間自身で慰めるしかなかった(もちろんオカズは彼女)ナルトにとって、目の前にいる彼女は極上のご馳走だ。となればナルトはさながら狼といったところで、最高点に達した空腹がどんどん思考を「食べたい」という欲のみに絞っていく。ここで手を出してしまうのはそう難しいことではないし、自分の持つ欲に身を任せるならばもちろん何も考える必要は無い。しかしこの休暇は彼女のためを思ってしたことなのだ。彼女は街を歩きたいと言っていて、それを思えばここで行為に及ぶのはナンセンスというものだ。とはいえここまで自分も頑張ったのだから、少しくらい我儘を言ったって、少しくらい褒美を貰ったっていいではないかとも邪な考えが頭をよぎる。 (そりゃあ休みは沢山あるけどさ〜) それはそれ。これはこれ。 だって一緒に風呂に入るかどうかを提案してきたのは彼女の方なのだから。あんな言葉、誘い文句以外の何物でもないと相場は決まっているじゃないか。もしそれを分からずにやっているとするならタチが悪い。 そうこうしている間にもは頭を洗い終えてしまったのか、水を切るためにぎゅっと髪を絞っている。 (水に濡れてるとこも色っぽいんだよな) 考えれば考えるほど、眼前の彼女を目に焼き付ければ焼き付けるほど、自分がどうにかなってしまいそうだった。 微動だにしないナルトを不思議に思ったのか、が首を傾げる。 (あ〜〜〜も〜〜〜!) その振る舞いがナルトの琴線をぐらぐら揺らす要素の一つであることを、は恐らく知らない。首を傾げて、ただ自分だけを真っ直ぐに見つめてくれる。たとえ深い意味がなかったとしても。なんでもない行為のはずなのに、そこには幸せが沢山詰まっているのだった。 (・・・そうだ、幸せなんだ、今) すれ違いどころかかすりもしなかったこれまでの日々を思えば。 こうして一緒にいられるだけで満足というものだ。事を急ぐ必要もないだろう。 「ねーちゃん背中流してってば」 「ん、はやくおいで」 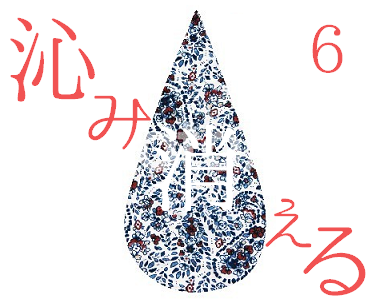 極僅かに硫黄の匂いを孕んだ湯気がもくもくと上がる湯船。乳白色のそこに体を沈ませればみるみるうちに白濁に飲み込まれていく。熱めの湯だが、それがまた気持ち良い。身体にじんわりと染み渡るように熱が広がれば、日々の疲れが一気に吹き飛んでいくようだ。 「あーっきもちい・・・」 「いや〜五臓六腑に染み渡るとはまさにこのことですなあ」 「なにそれ、じじくさ〜」 古代檜で作られた楕円形の浴槽の中で、二人は向かい合うようにして湯に浸かっていた。大きい作りのおかげか背の高いナルトが足を伸ばしてもまだまだ余裕がある。 「やっぱ温泉は最高だよな〜」 「ほんと。幸せ・・・」 ふう、と息を吐いては目を瞑った。湯の流れや鳥の囀り、風の音が普段聞くよりもダイレクトに感じられる。忙しさにかまけ疎かにしてせき止められていた色々なものが、ゆっくりと動き出す気がした。血が循環するとでもいうのだろうか。体内の毒素という毒素が流れていく、そんな感じだった。 「ねーちゃん」 ナルトに呼ばれて目を開けば、間近に迫る青い瞳。 「なに?」 「こっち」 「あっ」 白濁の湯のせいで腕が引っ張られたことに気が付けず、一体何が起きたのかと彼女は困惑した。されるがままに身を任せていると、今度は腰に手を当てられてくるりと向きを変えられる。結局ナルトの腕の中にすっぽりと納まるような体勢に落ち着くと、荒く揺れていた水面は次第に元の状態を取り戻していった。 「ねーちゃんスベスベ」 ナルトがの首筋に顔をうずめ、彼女の腕やら足やらを手でまさぐり始める。手を動かせば動かすほど、湯に揺られる柔らかそうな双丘が視界をちらついてしょうがない。くすぐったさに身を捩る彼女をとても愛らしいと思い、色付いて湯下が見えないのを良いことに、彼はその行為を加速させていく。 「やん、ちょっと、ナルト」 いい加減にしろとが振り返れば、思いの外恋人との距離が近い。熱気で紅潮した二人の瞳と瞳がかち合って、ふと時が止まってしまうのは自然の成り行きだった。 その場の空気が二人の距離をどちらからともなく近づけさせると、両者の視線がそれぞれの口元へと徐々に下がっていく。ナルトがさらに顔を近付けた。腰を抱いていた手にも自然と力が入り、吐息が湯気に溶けていったなら、もう二人は互いの唇をゆっくりと、そしてやんわりと押し当てあっていた。 肩越しの、彼女からしてみれば振り向きざまの、キス。 蕩けるような時の流れに身を任せ、心ゆくまでに貪り合い、惜しむように離れれば、彼女はゆっくりと深呼吸をして身体を恋人に凭せ掛けたのだった。 「・・・俺、聞きたいことあるんだ」 「聞きたいこと?」 するとナルトは徐にの腕を掬うように引き上げた。途端、川のせせらぎのように湯が音を奏でる。なんだろうと視線を追うと、彼は更に腕をねじって手のひらを上に向けたではないか。 「これ、ずっと気になってたんだ」 これ、と言ったところをナルトは指先でそっと撫でた。 そこには黄枯茶色で描かれた、あの「鳴門」のマーク。これが自分のことを指すのだろうというのは、なんとなくだがナルトには確信があった。けれど一体どういう経緯でこのマークを入れたのか。それがずっと気になっていたのだ。 「あ〜、これね」 「ねえ、これって俺のこと?」 「・・・えーと」 「もうそれイエスって言ってるようなもんじゃん」 俯きがちに、視線を泳がす腕の中の彼女が可愛くて、ナルトは思わず唾をごくりと嚥下した。 「どこだったかなあ、任務の途中に物資の補給で町に寄ろうとしたらね、遊牧民族の人たちと出会ったの。そしたらその中にいた女の子が、ヘナタトゥしてあげるよって言ってくれて、それで」 「へえ〜」 「つらくても、これ見たらナルトのこと思い出せたから」 その気持ちがとても嬉しかった。ナルトはの腕をさらに引き上げ、ヘナが施された部分に口付けた。まぎれもない、たおやかな愛の印だ。この溢れ出る愛をどう表現したらいいだろう。寂しかったとか、一緒にいられないのがつらかったとか、そんな振る舞いが幼稚なものに思えてくるほどに。 愛したい。この腕にぎゅっと抱きしめて、愛し尽くしたい。 「あのさ、ヘナって消えちゃうの?」 「うん、二三週間ぐらいしたらもう消えちゃうかな」 「そっか」 「なんで?」 ナルトは口を噤んだ。黄枯茶色を注視しながら。 「え?」 「?」 彼はふと、こんなことを思ったのだ。 もし、その消え方が表面が剥がれるように色が落ちるのではなく、皮膚に沁み込んでいくように消えていくのなら。それはこのマークを描いてほしいと願った、すなわち自分のことを思った彼女の気持ちも一緒に織り込まれていくようで。キスを施した己の気持ちと相俟って、皮膚から体内へ、そして細胞の隅々まで、自分の欠片が行き渡ってくれたら、と。そんなこと口にでもしたらきっとまたくしゃりと笑って「ばか」と言われるんだろう。同時に少しだけ女々しい気もして、ナルトがこの思いを口にすることはなかった。 「へへ、愛されてますなあ」 「はいはい愛してますよ」 「あーもーだめ、やっぱ我慢なんねえ」 の項に噛み付くようにナルトはキスを落とし、わざとリップ音を立てながら、徐々に肩へと彼女の肌を食んでいく。逞しい腕で身体をさらに密着させると彼女は何かに気が付いたのか、思わず背筋をピンと伸ばした。 「あのう、ナルトくん?」 「え〜そりゃ〜勃つってばよ」 ねーちゃんがいるんだから、と付け加えるとナルトはいよいよ性的な意図を持って手を動かし始める。 「ナル、ト」 力の抜けた身体が湯に少し沈む。体勢が変わったことで彼女の胸が浮かんできたのを良いことに、下からやんわりと触れてやれば風呂に浸かってるせいなのか、普段よりそれは一段と柔らかかった。手のひらで包むように、そして円を描くように揺らしていくと、その動きに合わせて水面も緩やかに波立つ。 「お湯の中だからかな、なんか、すっごいやらかいってば」 「・・・ばッ」 興奮しているのか耳に響くナルトの息遣いが荒く、湿り気を帯びた吐息に中てられながら、も脳が働かなくなるのを感じた。そう、脳は鈍くなっていくのに快感を拾う神経は鋭敏になっていく。彼の指先が時折乳首を掠めるのが歯痒いと思えど、口にするなどできるはずもなく。そんな恋人の気持ちを普段なら心ゆくまでに利用するナルトだったが、今回ばかりは余裕がないのか彼女の悩みは直ぐに解消されたのだった。 「あっ・・やぁ」 「好きなくせに」 「ふ、ぁ、っあ」 漏れ出す甘い声。外の明るさが二人の行為に対する背徳感を助長させる。ここが露台であるということもそれを助長させた要因だった。好き勝手動く男の指を制止させようにも、後ろから抱きすくめられているから叶わない。それどころかやってくる快感に更に喘ぎ喉元を晒してしまう始末だ。ナルトは彼女の白い喉元に舌を這わせながら、向きを変えさせようと再び腰を掴んだ。 「ひゃう」 「ねーちゃん、足またいで」 膝立ちにさせられたがナルトの身体を跨ぐと、今度はストンと腰を落される。そうすることでムクムクと主張をし出した怒張が下腹部に密着した。その感触に思わず腰を引くも彼はそれを許さない。ここまで来てしまったのだから、「やめよう」なんて引き返すことはできない。それは彼女にも重々解かっていることだった。それに彼女とて久々のセックスなのだ。拒む理由もなかった、のだが。 「ね、ナルっぁ、ん」 「んー?」 彼女が言いたいことを口にしようとした途端、ナルトは目の前で揺れる彼女の尖端にむしゃぶりついた。指とは違って唾液を纏った舌にねぶられて、電気が走ったかのような快感のせいで言葉の続きが阻まれてしまう。 彼女が何かを訴えかけようとしているのはナルトにも解かったが、それがなんとなくこの行為を中断させる一言ではないのかという恐れから、半ば本気に聞いてやることができない。なにしろようやく聞くことが出来た艶声だ。もう火は付きかけているのではなく、とっくに付いてしまっているのだ。一人という寂しさが溢れる時はいつも彼女の夢を見ていた気がする。でも所詮はただの夢なのだ。夢の中で彼女の温もりに触れれば触れるほど、心の中に悲しみの雫が落ちては消えていった。けれど今はこうして腕の中に確かな存在としているのだ。いくらこの休暇の日にちに余裕があったとしても、ここまで来てしまったらやめることなどできる筈もないだろう。 「あっぁっ、も、だかっら」 細めた舌先でつんつんと乳首を押されたり、舌の根の方で潰すように舐められたり。かと思えばほんの少しだけ歯を立て甘噛みされたり。 余計に気分が乗ってきたのか、ナルトは中心で主張をする自身をアピールするかの如く腰を揺らしてくる。 「ッ今更やめようなんて無理だかんな」 「そ、じゃ、なくて」 「え?」 が一度大きく息を吸って呼吸を整える一方で、ナルトは「そうじゃない」という彼女の台詞に目をきょとんとさせた。 「お湯の中、やだ、」 「あ・・・!そっか、ごめん」 必死の懇願は、彼が思い描いていたものとは違っていた。そのことに安心するや否や、すぐさま彼は、以前家の風呂場でセックスをした際に彼女が痛がっていたことを思い出す。 どんなに愛液が分泌されようと、秘部に入り込んでくる湯のせいでそれが洗い流されてしまうのだ。潤滑油である愛液がなければ、どんなに愛しい相手であれ苦痛でしかない。ナルトからしても確かに浸かったままでは、普段と違って挿入も難しかった。最初から挿入した状態で湯船に入ればまた違うのだろうが、とはいえ湯の雑菌も気になり中々行為に没頭することもできないのだから、彼女にとって浴槽内で身体を繋げるのはできれば避けたいことだとその時知った。 「ねーちゃんちょっと捕まってて」 「う、ん」 体を拭いてベッドまで行くだけの精神的な余裕は無かった。ナルトはに首に捕まるよう指示し、彼女の臀部を腕でしっかりと支え勢いよく立ちあがる。そして備え付けられていたバスタオルを片手で何枚か乱雑に露台に広げると、その行動とはまるで異なり壊れ物を扱うかのように優しく彼女を寝かせたのだった。 時折差し込む日の光が二人の濡れた体を照らし、艶やかさを強調する。ごくりと生唾を飲み込んだナルトがのそりと彼女に覆いかぶされば、自身の毛先からぽたぽたと水滴が落ちるが、それはもはや些細なことに他ならなかった。 「・・・えっろ」 「ばか」 真顔でそんなこと言わないで、との視線が泳ぐ。 情欲に満ちた瞳でナルトは彼女の耳元にそっと唇を寄せ、ワントーン落とした声で「挿れたい」と囁いた。思わず肩を震わせた恋人に彼はさらににやりと笑みを投げ、米神にキスを落とす。自分と同じように、期待を孕んだ瞳が顔を覗かせたのを確認すると、ナルトは中指をそっと彼女の秘部に這わせた。二、三度具合を確かめるように動かし肉を割って入れば、卑猥な水音とともにするりと指が食われてしまう。 「ひぅ、ぁ、っあ」 「慣らさなくてもヨユーヨユー」 指を抜き刺ししながら、入り口の周りにも愛液を塗りたくる。そのむず痒い感覚には腰をくねらせた。同時に挿入している指が内壁に締め付けられ、いよいよナルトの高ぶりも頂点に達する。 「も、挿れるから・・・ッ」 「っん、」 ぷっくりと先走りの滴る先端を秘部に沿わせ、擦るように上下させた。肉と肉のぶつかりは、硬い皮膚を持つ指で触れるよりも快感そのものに触れているようで至極気持ちが良い。敏感な亀頭への刺激を堪能したあとに、ナルトは急く心を必死に押さえつけながら、それはそれはゆっくりと陰茎を膣の奥へとうずめていった。 「あっぁ、はぅっ、ん、あ、」 「力・・・ッ、抜けって」 「抜い、て、っる、あぁっ」 一番直径のある雁首がぐいぐいと秘部の入り口をこじ開けるものだから、はきゅっと目をつむってその感覚を享受する。正直少しの痛みがあるが、同時に、この広げられているという現在に対しての快感もそこに存在していた。痛いのだけれど気持ちがいい。それってマゾヒズムに近いものがあるのだろうか、と体内に侵入してくる雄を前にぼんやりと考えていた。 「っはー、久しぶりだからねーちゃんの中、狭い・・・」 全部入ったよ、と額にキスを落せば、涙に濡れた瞳が再び露になる。彼女は深部へと侵入した熱源をしっかりと全身で感じながら、身体が悦ぶとはこういうことなのだと、久々に思い知った気がしていた。忙しさにかまけて恋人への振る舞いを疎かにしていたというのに、今彼はそれを許し全身全霊で愛そうとしてくれている。申し訳無いと思う以上に、こちらもその愛に応えたかった。だからナルトの首に腕を回して誘うように腰をくねらせてやると、眼前の恋人は一瞬目をはっとさせた。だがすぐにニヤリとした笑みを浮かべている。 「ねえ、誘ってんの、それ」 「ん、はや、く、ナルト」 「!!!」 腰を浮かせたに、ナルトは少し言葉で攻めてやるつもりだったのだが、殊の外本能に従順に彼女が言葉を返すものだから、その妖艶さに彼は逆に追い込まれてしまった。まるで火山が爆発したみたいにナルトは目をぎらつかせ、腰を動かし始める。 「ああっ、うそ、あっあっぁっや、あ、っあ」 序盤から勢いよくやってくる律動に彼女から際限なく上擦った甘い声が漏れ出す。 「へへ、可愛いっ、てば、」 「う、ぁ、っも、そん、あっぁっなる、と」 「目瞑んなって、顔、見せてよ、」 艶声を耳に刻み身体に沁み込ませながらナルトは彼女の足を抱え込み、奥へ奥へと己の陰茎を打ちつけた。その動きと相俟って柔らかな双丘が揺れ、淡く色づいた乳首がちらちらと視界に入るのだからたまらない。結合部から奏で出される水音、他の人間には決して出させることの出来ない泣き声、筋肉質な男にはない肌の柔らかさ、熱に浮かされた焦点のぼんやりとした瞳、性行為独特の香りに口付けの味わい。人間の感覚という感覚がフルに満たされるのを感じながら、ナルトは何度もその内奥に全てを放ったのだった。 (2015.5.11) CLOSE |