どこかの誰かが描いた大名絵巻のように、景色が次々と変わっていく。西日の射す空に、森に、崖の下に見える街々に。川を飛び越え、草原を走り抜き、どこまでも前へ。 はナルトに捕まりながら、なんの危険が待っているでもない時間の流れに、自分の意識がぼんやりしていくのを感じた。兵糧丸の効果が切れてきたのだろう。ほら、こんな普通の兵糧丸じゃ三日三晩走れやしないじゃないか、と彼女は心の中で悪態をつく。 (力、入らない) 自分の首に絡まる腕が徐々にずり落ちていくのに気が付いたナルトは、走る速度を落とし、腕の中の彼女の様子をちらりと窺った。明け方に帰ってきた彼女と全く同じ表情だ。憔悴しきって、瞳の色を失いかけている。見ているこちら側の脳裏に焼きつくような、その厳しさ。 「ねーちゃん、大丈夫?」 「・・・ん、綱手様から貰った兵糧丸が、ポケットにね、」 「もうそんなの食べなくて良いんだってば、まだもう少しかかるからさ、寝ててくれよ」 「で、も」 「いいからいいから」 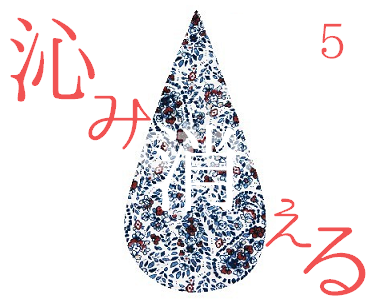 すっかり陽も沈んだ頃、を抱きかかえたナルトはようやく目的地へと辿り着いた。火の国から走ること約半日、風の国へと向かうルートの約三分の一を行ったところにある町、その名も「硝子町」。その名の通り硝子産業が盛んで、そのうえ、地理的にも火の国と風の国と雨隠れの里の中央辺りに位置して、宿場町としても有名なところだった。そのため観光産業もまた盛んで、この二つの産業によって町は十分すぎるほどの資源を得ており、連合には属していないのも特徴の一つと言ってもいいだろう。 そんな町に一歩踏み入れば、町全体で統一しているのか建物の色が遠目に黒紅一色に映る。だが近づいてみると黒檀を使っているのだろう、家々の木材は黒と僅かな赤みを持った帯が交互に重ねられていて、年数が経った建物の黒檀は、色の劣化も相俟って全体的に蝋色に落ち着いていた。建物は楼閣のような重層作りで、各階の軒平瓦からは等間隔に赤い提灯と、町のシンボルでもある硝子を切子状に細工した丸いランタンが吊るされている。それらが建物の黒と対照的に明るさを成していて、そのはっきりとした色調の差がより人目を引いていた。さらに今の時分では、町中至るところに吊るされた赤と透明が浮かび上がるように灯り、なんとも異国情緒溢れる景観を作り出していたのだった。 その景色の中に紛れたナルトが、重層の瓦を一般人の目では到底捉えられないぐらいの速さで駆け抜ける。当初旅行と宣言したとおり、これから宿へと向かうのだ。その宿はまだナルトが子供だった頃に、第七班と任務で訪れたことがあった宿で、シカマルから薬草を貰いサクラの元へと向かう際、影分身を飛ばし既に予約の手はずを踏ませていた。 だがナルトがここを選んだのはなにも昔来たことがあっただけではない。それはこの町の観光産業が栄えた理由と同じで、守秘義務の徹底から彼はここを選択したのだ。地形柄様々な人間が行き交うため(もっと言えばその人間とは、忍だけではなく商人や時には大名、名の知れた俳優や知名人が訪れるのだが、その大半が自らがいると知られることを嫌うため)、町はプライベートの強化を、観光産業を盛り上げる上での必須事項としたのだ。いわゆる「お忍び客」にとって、百歩譲って町を歩く姿を見られることは許しても、泊まっている宿や寄った店につきまとわれるのだけは御免被りたい。だからこそこの町は、様々な事情を持つものにとって好都合なところだった。おそらくそれを連合を含めたどの国も利点だと捉えているのだろう。自国にとっても有益であるからこそ、干渉が及ぶことはないのだった。 町の中心から少し離れたところに一際大きく聳え立つ、重層の最上階にナルトは降り立った。明かりの点いている部屋の中を窺い見ると、そこにはつまらなそうな顔をしているナルトの影分身が、一人寂しく胡坐をかいている。しかし窓の外にを抱えたオリジナルがいることに気が付くと、分身はぱっと太陽が雲間から覗き出したかのように明るい笑顔になり、急いで窓元に駆け寄り鍵を解錠したのだった。 「ねえちゃああん!」 「こーらー!寝てるんだから静かにしろってば!」 オリジナルに抱えられている愛しの彼女の寝顔に、ついつい分身も喜びを隠すことができない。そんな分身に「サンキューな」と言ってナルトは術を解く。その寸前に「あっもうちょっとだけえええ」と聞こえたのが面白かった。どこまでいっても自分は自分。彼女のことが好きでたまらないのだ。煙とともに分身が消えると、彼のこれまでの経験が自身に流れてくるのを感じ取った。道中何も問題はなかったようだし、宿泊の手続きも上手くいったようだ。ついでに美味そうだと目星をつけた屋台の情報まで入っている。 我ながら抜かりないと思いながら、ナルトは部屋の中を軽く見回した。前回泊まった時は素泊まり用の簡素な部屋だったが、今回はなんと言っても超ハイグレード。最上階にあることからも見晴らしは抜群だったし、何より部屋が豪華だった。 「思った以上に豪華だな〜」 居間の横にはダイニングルームのような食事部屋、そこから続き部屋で寝室があり、一方にはシャワールーム、一方には障子窓を挟んで、外界の絶景を望める露天風呂が設えてある。漆塗りの窓枠や露台がなんとも豪奢だ。 「お、さっすがー、布団敷いてある」 寝室には高級そうな敷布団が二つ。どちらも皺一つなく伸ばされたシーツが部屋の明かりを部屋全体に反射させている。部屋を選ぶ際に天蓋付きのベッドもあると言われたらしいが、どうやら分身は普段ベッドを使っているからかそれを断ってこの敷布団にしたようだ。いかにも旅行感(旅行だが)満載に憧れていたらしい。 そんな布団の上ナルトはをそっと降ろし、今朝してやったようにベストを脱がして、頭を枕に乗せてやった。深い眠りに落ちているのか、彼女からは全く起きる気配が見受けられない。 「あーあ、無防備に寝てやがんの」 ただただ、ぐっすりと。夢など見ないほどに。 安心したようにナルトは目を細めた。 「・・・お疲れさまだってばよ」 ほんの少しでも良いから休ませてやりたいという願いが、今まさに叶ったのだ。成し遂げたのだと思うと、ほどではないにしろ、半日人一人を抱えて走りきったナルトの体にも軽く疲労がのしかかる。時計を見ればまだ夜の九時過ぎだったが、この場所が中心地から少し離れていることもあり、外はすっかり静かだった。 「・・・俺もねーちゃんと寝よ、ヨイショっと」 布団と布団の合間に出来た若干の隙間をなくすように、ナルトは自分の敷布団をが寝ている方へと押しやると、上着を脱ぎ捨てアンダー一枚で布団にもぐりこんだ。ふかふかとしたマットに、ふんわりと軽く、しかししっかりとした温かさを持つ羽毛布団。普段家出使っている寝具とはまるでレベルが違う。 太陽の光を沢山浴びたに違いない心地良い香りを吸い込み肺に落せば、一日ナルトも気を張っていたのだろう、睡魔が徐々にやってくる。 「かわいいな〜」 久々にまじまじと見つめる恋人の寝顔はとても安らかだった。無防備すぎてあどけなさすら感じさせる。そんなにナルトはもぞりと身を寄せ、頬にキスを落した。そして彼女を抱き枕にするかのように、足を絡ませ腕にもしがみつく。布越しに伝わる体温に酷く安心を覚えた。やはり隣に彼女がいてこそ自分の安堵がその意味を成すのだ。 この温かさだけは、何にも取って替えられない。どんなに美味しい食事も、どんなに美しい景色も、どんなに素晴らしい出来事も、もう一人では満足できない。分かち合える愛しい人がいなければ、本当の意味での充足には成り得ないのだから。 「おやすみ、ねーちゃん」 * 翌朝、もとい翌日の正午すぎ。 眠りと覚醒の間で揺らめいていたの思考が、唇に当たった何かによって一気に覚醒へと引き上げられた。重そうに目蓋を上げれば、目の前にはナルトの顔。まだまだぼんやりとしている頭では、キスをされていることにも中々気がつけなかった。 「あ、ほんとに起きた」 「・・・」 寝ぼけ眼でぼんやりと恋人を眺める彼女には、今しがた彼が言った言葉が理解できない。 「おはよねーちゃん、すげーぐっすり寝てたよ」 「・・・おはよ、ほんとに起きた・・・って?」 「ほら、よく言うじゃん、王子様のキスでお姫様は目覚めましたって」 よりも前に目が覚めたナルトは朝から部屋を散策したり散歩をしたり活動していたのだが、それでも昼には手持ち無沙汰になってしまった。そこで布団に戻って彼女の寝顔を眺めていたら、ふとあることが念頭に浮かんだのだ。 というのも、彼女があまりにもぐっすり眠っていたからなのだが、それはいわゆる昔から伝わる御伽噺でよく聞くシチュエーションのことである。それを実践しようと口付けを試みれば、なんということだろう彼女が目を覚ますものだから―それが十分に睡眠を取り覚醒の間際だったのだろうことを思っても―、ナルトは驚いたのだった。 「・・・王子様って」 ばからしい、と思いながらも、それでも照れくさそうな顔をは浮かべた。 「それよりもさ、ねーちゃん外見てってば」 「あっ、ちょっと」 ナルトは上体だけ起こした彼女の腕を引っ張りその身を立ち上がらせると、そのまま手を引いて障子の向こうの張り出しの露台へと案内した。 障子によって遮られていた陽の光を直に浴びは一瞬眉根を寄せるが、その光に慣れてしまえば視界には大きな露天風呂と、異国情緒溢れる町の景観が入り込んできたのだった。 「すごい・・・きれい・・・」 墨のように黒い建物を彩る赤の提灯と硝子のランタン。そのどれもが目に新しく、の目に次々と刺激を齎していく。 「硝子町って言ってさ、昔七班で来たことがあったんだ」 「そうだったんだ・・・」 ずっと見ていられるぐらに美しい景色だと彼女は思った。 途中寝てしまったためにここが木の葉隠れの里からどれぐらい離れているか、彼女には見当がつかなかった。だがきっと遠い道のりだったのだろう。この町までナルトは自分を抱えて走ってくれたし、宿の手配だってしてくれた。表沙汰にはできない手段であったのに違いはないが、しかしその全てが自分を思ってのことだったのだ。 「ナルト」 「ん?」 は頭をナルトに凭せかけた。 どうしたのだろうとナルトが顔を覗き込めば、彼女は視線だけ上にあげて空の青に負けないぐらいに綺麗な青を見つめた。視界の端では太陽がナルトの髪をきらきらと輝かせている。 「ありがとう、連れてきてくれて」 目を細めて切なそうに微笑む彼女の姿に、ナルトは自身の心臓が跳ねたのを感じた。その甘さを孕みつつ侘しさも窺える表情に、何が隠されているのかナルトには全てを理解することはできなかったが、彼女の言葉には沢山の愛が込められている気がして。 だから彼はさらに頭を近づけて、彼女の唇に食むように吸いついた。寝起きだからだろう、彼女の唇は少し乾いていて、反応もまだ鈍い。 (きびきび働くくせに、ねーちゃんって休みの日はちょっと抜けてんだよな。かわいいけど) 「ねーちゃん疲れとれた?」 「ん〜それなりに」 「日にちはあるから今日はごろごろしててもいいってばよ?」 「あはは、それも良いけど町も歩きたいなあ」 「だってあんなに綺麗な町なんだもの」とはナルトから町の方へ視線を移し変えた。少し遠くの方に建物が密集しているあたり、この宿は中心から離れたところにあるのだろうと見当がつく。ナルトが言うように、確かに部屋で休日の特権と言わんばかりにごろごろするのも魅力的だ。だがどうせ日が沈めば部屋でゆっくりするしかないことを思えば、明るいうちに見知らぬ町を散策してみたかった。 「あ、ねえナルト、私着替えとか何も無いんだけど」 「ふっふっふ、影分身にぜーんぶ用意させてるんですなこれが!」 得意げに笑うとナルトはくるりと向きかえって寝室の隅を指差した。その指先を追うように、同じくも振り返れば、そこにはなにかを包んで膨らんだ、草木染めの風呂敷が置かれていた。 「あん中にねーちゃんの服とか下着とか入ってるってば」 「しっ下・・・!?ちょっと、棚漁ったの?」 「え、別にそんな今更じゃん」 「・・・そりゃ、そう、だけど」 だからって恥じらいが消えたわけじゃない、と彼女は心の中で毒づく。 「ちなみに下着は全部俺好みのをチョイスさせて頂きました」 「このマセガキ」 「もうガキじゃないもんね〜だ。もう着替えて行く?」 「あ、その前にお風呂入りたいかな」 何せ目の前に大きな露天風呂があるのだ。 この数週間シャワーで済ますしかなかったにとって、温泉はこれ以上ない宝に見えただろうし、正直、この露台に連れられてから立ち上る湯気やら耳に入ってくる湯の流れる音に、彼女が気をとられていたのも事実。 「オッケー、じゃあ俺ってばタオル持ってくるか・・・ん?ねーちゃん?」 ナルトは動こうとしたのだが、それが阻まれたことに気が付き、なんだろうと隣にいる自分の行動を阻止した張本人を見やる。どうしたことだろう彼女は自分の袖をきゅっと掴んで、顔を俯かせ気味にしているではないか。 「・・・い、一緒に入る?」 一瞬何を言われたのかナルトは解からなかった。なにしろ普段は殆ど聞くことが無い台詞だったのだから。 「へ?」 時間差で彼女の言葉が脳を巡ると、今度はその言葉がエコーのように何度も何度も響き渡る。そしてようやく意味を理解すると、ナルトはハッと目を見開き、期待に満ちた表情で口を開いた。 「え!!」 「・・・やなら良いけど」 「入る!入る入る入る!うおー!入る!!!」 (え、もう脱いでるんだけどこの子!) ものの数秒でパンツ一枚になったナルトに、はくすくすと笑い声を上げたのだった。 (2015.4.13) CLOSE |