ボンっと大きな音と共に上がった白煙が静まり、固唾を飲んだ、その瞬間。男の正体が白日の下に晒されるのを、見逃すまいとの感覚がぴりぴりと研ぎ澄まされていく。 「・・・ッ!?」 どうしたことだろう、あれだけ身構えていたにもかかわらず、彼女は全く身動きが取れないどころか、あろうことか気が付いた時には地面に押し倒されていたのだった。 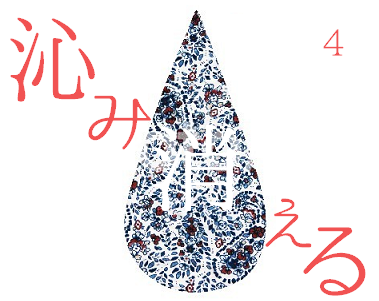 「ねーちゃああああああん!」 荒々しい叫び声とともにを押し倒したのは、瞳に嬉し涙を浮かべたナルトだった。何が起きたのかを全く理解できない彼女は、声を発することもできずにぱちぱちと瞬きをしている。なんで、どうして、なぜここに、ナルトが。少しでいい、ほんの三十秒でもいいから心を落ち着けて考えたいのに、彼女にのしかかる塊がそれを許さない。 「ああああーーーねーちゃんだあああ」 「・・・っ」 「会いたかったってばよおおおおおォォ」 頬ずりをされたかと思えば、次にやってくるのは額や目蓋や鼻や口、それこそ顔の至るところにキスの嵐。それから首元に顔を埋められ思いっきり匂いを嗅がれる始末。 (・・・い、犬だ・・・) まるで振り切れんばかりの尻尾が見えるかのようだ。 術を解いてからも匂いはしなかったが、こんなにも自分に熱烈な愛を送ってくる人間をはナルト以外には知らない。敵ならばとどめを刺すのにこんなに有利な態勢はないのだから、おそらく、いや百パーセントナルトだろう。 彼女の視界の奥では蝋梅の花がちらちらと舞っていて、太陽の光を受けてとても綺麗だというのに、そんな風景をぶち壊すかの如くナルトは忙しない。 「ねえ、ちょ、っと」 いい加減にしろと上体を起こそうとすれば、その仕草を読み取ったのか逞しい腕で自身のそれが引っ張られる。そうしてまた勢いよく姿勢が変わると、先程よりも間近に迫る恋人の顔。 「ほ、ほんとにナルトなの?」 「ヘヘ、俺に決まってんじゃん」 ちゅ、と唇に触れるだけのキスをナルトが送る。 「なんで、どうして・・・」 「持つべきものは友ってところかな!」 ナルトはニシシ、とお得意の笑みを浮かべながら、ポケットから調合した薬の入った袋を取り出した。そこには奈良家の家紋が刻まれていて、それを見たはようやく合点がいったのか「なるほど」と呟く。おおかたサクラにでも調合を頼んだのだろう。ナルトのことだ、言い訳ぐらい見繕うのは簡単だったに違いない。昔から悪戯っ子としての頭の良さだけは誰よりも秀でていたし、皆まんまと幼いナルトの罠にかかっていたのだから。 「でもどうして私が助けた人のこと知ってるのよ」 「前にねーちゃんが言ってたってば、じゃなきゃ俺が知ってるわけねーじゃん」 「う、うそだあ・・・」 「多分、酒飲んでたってばよ?まあばーちゃんが死にそうってのは作り話だけど」 「げー・・・」 どうしても解けなかった謎の答えがこれなのか、とはがっくりと肩を落とす。これといって里に危害が加わるような事態にならないことに安堵する以上に、たかだか酒を飲んだぐらいで、本来は心の内に保持しておかねばならない情報まで喋ってしまったことが、彼女にとってはショック以外の何物でもない。普段は決してそんなことないような気がするのだが、それもこれも相手が相手だからだったのだろうか。いやいやとはいえど。いくら相手が恋人だからとて、喋ったらいけないこともあるじゃないか、と見る見るうちに彼女の眉間に皺が刻まれていく。それを目の当たりにしたナルトが「まあまあ」と彼女を宥めにかかる。 「でもさ、記憶がなくなるのって、ねーちゃんが俺のことちゃーんと信頼してっからだろ?」 平然とした顔で言ってのけた青年とは反対に、その言葉に目を見開き押し黙ってしまったの耳が徐々に紅に染まっていく。 (ナルトって、たまにこういうところ、ある) 自分の方が何倍も色んな経験をしているのに、そういうものを全部どこかへ追い払ってしまう時がナルトにはある。そして彼自身の持つ自信を最大限前に押しやってくるのだ。 例えばナルトは自分を愛してくれていると思っている。それは直接的な言葉だけじゃなく、日々の生活の中に溶け込んでいる色々なところから愛を感じるからだ。でもそれを、態々口に出すのはどこか気が引けてしまう。本人を前に真顔で「ナルトは私のこと愛してるもの」とか、ましてや第三者に向かっては口が裂けても言えるものではない。思うか言うかの違いしかないが、それでも口にするのは恥ずかしい。自惚れだとも思うし、図々しいとも思う。端から見たらあいつは凄い自信家だ、とも思われる気もする。でもナルトは違う。言ってしまうのだ。けろっとした顔で。厳密に言えば、自信から、というよりは一に一を足したら二になるという自明の理ぐらいの気持ちから、だけれど。だからこそタチが悪い。彼は所謂「天然のタラシ」なのだ。恋愛感情を抜きにしても、無意識のうちに人をその胸中に抱き込む人誑し。 「・・・・・・」 恥ずかしさで返事ができないを窺うように青の眼がぐんと近くなる。 「え?なんで耳赤いの」 「・・・なんでも、ないです」 「ねえ、すげー可愛いんだけど、それ」 「・・・あっあのねえ!・・・・・・ッ!」 ギラついた目に射抜かれて、彼女はまた固まってしまう。 (やだ。いつから、こんな目をするようになったんだろう) 胸がざわざわと落ち着かない。今立ち上がらねばきっとまたキスされるだろう。頭では解かっていても、体が上手く動かない。魔法にかけられたかのように、は恋人の青い瞳から逃げられなかった。 「ぁ・・・っ」 近づいてくる本能むき出しの、真剣な顔。鼻がぶつかり、相手の鼻息を感じ、両者の視線が口元に下りた次の瞬間には、柔らかい感触までもが。 びくりと肩を跳ねさせたをナルトは優しく抱きしめ、己の舌で目の前の入り口を割って入っていく。 「ん、」 ねっとりと侵入してきた熱に戦き彼女が身をくねらせば、逃げられないようにゆっくりと体重をかけられて再び地面に押し倒されてしまう。さあもう逃げ道はないぞとばかりに、赤くざらついた舌で歯列をなぞられながら、口内が懐柔されていく。苦しそうに漏れる彼女の吐息の音が、彼の耳を侵してさらに興奮を高めていった。角度を変え、荒々しくの舌に己のそれを絡めるナルトはさながら野獣のようで、三週間分の愛を送り込むように無我夢中で彼女を貪っている。なりふり構わぬキスに、彼女は自分の思考が段々遠のいていくのを感じた。ここが外で、人が通るかもしれない街道だとか、頭や服が土で汚れるだとか、そんなことがどうでもよくなるほどに。 唇を食み、ナルトの誘いに応えるように己も舌を絡ませる。円を描くように二つの舌が絡み合えば、そこから沸き立つ卑猥な水音が二人の感度の波をさらに大きくした。意図的にナルトが動きを弱めれば、もっともっとと強請るようにリィの舌が後を追う。求められたことに気を良くした青年は一際強く唇に吸いついた。両者とも、目の前の存在を確かめたい。ただただそれだけだった。 「・・・っは、ぁ」 「ッねーちゃん」 「ナル、ト」 「ずっと、こうしたかった」 「う、ん」 瞳と瞳が重なった。 の熱に浮かされた瞳からは、ナルトが少し歪んで見えた。 「泣くなよ、ねーちゃん」 「っう、ん」 涙が滲んでいたから、はっきり見えなかったことにも気付けない、なんて。 腕を引っ張り上げられるままに上体を起こすと、恋人の節くれだった指に次々に零れ落ちる涙を拭われる。その行為が彼女にとってはたまらなく切なく感じられ、また涙を呼んでしまうのだ。 「ごっ、めん、ナルっ、ト、ごめっ」 「なんでねーちゃんが謝るんだってば」 「だっ、て、いっ家で、色々、して、くれた、のに、私、なにもっ、」 涙を拭うナルトの目が、少しだけ大きくなった。彼は知らなかった。恋人が自分のしていたことに気が付いていたということを。そのことが解かるだけで胸の箍が外れたような気持ちになる。思いが伝わっていたならそれでもう良いのだ、と彼は腕の中で大きな滴をこぼすの頭を撫でてやった。まるで子供をあやすかのように。 「いいんだって、ねーちゃん任務辛かったんだからさ」 「でも、でっ、も」 端から見たらどちらが年上か解からない光景の中で、自分の行いを許すことができないが眉を寄せたままナルトを見上げる。赤い瞳に、濡れた睫毛に、涙の跡に。普段中々見ることができない年上の感情的な人間臭い姿を、ナルトは可愛いと思った。可愛い、なんて陳腐な言葉で、誰にだって言える。けれどそれでも「可愛い」のだ。 「それに俺も、ちゃんと「いってらっしゃい」って言えなかった」 ナルトの手の動きが、ふと止まる。 「ねーちゃんが、ここにいて、そんで俺も、ねーちゃんのとこにいる。もうそれで良いんだってばよ」 「ナ、ルト」 「それにほら、さっき言ったろ?いつも笑っていてほしいって」 ナルトは得意の笑顔を浮かべて見せた。その台詞は、まだ彼が変化していた時に彼女に言った言葉だった。妻を思う夫の吐露したあの心情が嘘をついているように見えなかったのは、そっくりそのままへと向けられていた気持ちだったからだ。 「・・・あり、がと、ナルト」 彼女は未だ涙で腫れぼったい目で微笑んでみせると、両の腕を太く逞しい恋人の首へと回しぎゅっと抱きついた。その行動に上から気の抜けた笑い声が降り注ぐ。少しだけ彼の服用した薬が切れてきただろうか。匂いがしなくもない。温かくて、安心できる、優しい匂い。たまに家に帰った時に熟睡できたのは、きっと隣に彼がいて、彼の匂いがしたからだ。 「へへ、っよぉーし、ねーちゃんそのまま捕まってろよ」 「えっ、ひゃ・・・ッ」 言うや否やナルトはの膝裏に手を差し入れ、横抱きにする形ですっくと立ち上がった。突然のことに落されないように、彼女はしがみ付く腕にさらに力を込める。一体何が起きるのだろう、そんな不安な目で金髪を見やれば、またもナルトはあの得意の笑顔。子供の頃の、悪戯っ子の笑顔そのものだ。 「ちょーっとひとっ走りするぜ」 「へ、ど、どこへ?」 「いい?ねーちゃんは、俺に雇われたの。それで、ねーちゃんは今から俺と旅行に行くの」 「りょ、こ、う?」 まるで予想外な角度から話を切り込んでくるものだから、ナルトが何を言っているのかにはさっぱり解からなかった。 「ねーちゃんてば働きすぎだからさ、だから俺が雇い主になってねーちゃんを外へ連れ出せば良いって思ったんだってばよ」 「・・・ん、んんん?」 「里ン中じゃいつ呼ばれちまうかわかんねーだろ?だから里の外。でも問題はどーやってねーちゃんを連れ出すかでさ〜、抜け忍扱いされても困るし」 聞けばナルトの思惑はどうやらこういうことらしい。 いくら綱手に回復術を施されてるとはいえ、自分と会話もままならないぐらい疲れているのだから、相当な疲労が体に溜まっているのだろうと。だからほんの数日間だけでも良いから、恋人に癒しを与えたかったと言う。忍として生きると決めた以上、それが甘っちょろい考えだといういうことは十重に承知している、が、体が壊れてしまえばどんなに優秀な忍だってただの人間なのだ。 それでナルトは彼女にしっかりと休んでもらう環境を作り出そうと考えた。次に帰ってきたタイミングを見計らって彼女を連れ出したのでは、意味が無い。火影の命もなく、誰に何を言うでもなく里をこっそり抜け出せば、抜け忍扱いされる危険があるからだ。そうでなくともナルトは何度も綱手にに休みをくれ、と嘆願しに行っているのだから、彼女が消えれば犯人は自分だとバレてしまう。そうなれば捜索隊でも出されて強制送還されるのは目に見えている。ならばどうするか。そこでナルトは思いついたのだ。自分が依頼主になれば良いということを。最初は自分の貯金をはたいてSランク任務の申請を出し、彼女を呼び出すつもりだったのだが、それを任務受付並びに綱手やシズネが許すはずも無い。再び頭を抱えたところ、過去に彼女と家で酒を飲んでいた時のことを思い出したのだ。彼女がこぼしていた任務中にあった夫婦救済話。これだ、これならいけるに違いない、と彼はその助けられた夫婦の男役になることを決意したのだった。 身体検査さえクリアすれば自分だとばれることもないだろう、そう踏んだナルトはシカマルのところへ走り、匂いやチャクラの流れがばれないような薬が欲しいと願い出た。もちろん友人に訝しまれはしたものの、緊急の任務なのだと言い張り、しぶしぶ承知してくれたおかげで薬草を手に入れることができた。あとは調合だけ。そう思いサクラのところに行きそれらしい嘘を吐いたのだが、流石は長年の付き合いと言ったところか、すぐに見抜かれてしまった。同じ班で切磋琢磨し合ってきたからこそ、相手の些細なことにも気が付いてしまう。それで、嘘はつけないと腹を括ったナルトは、これから自分がしようとしていることを素直に打ち明けた。綱手やシズネの直属の部下であるサクラが許すはずもない、と半ば計画を諦めかけていると、どうしたことだろうサクラは悩み始めて、「さんの噂はよく聞くし、実際見るに耐えない姿だったのよね」と言ったのだ。そして彼女は続けた。「しょうがない、今回だけだからね」と。そんなこんなでトントン拍子に進んだ計画を、今現在実行中というわけだ。とはいえまさかこんなに早くに正体を見破られるとは思ってもみなかったが。 「・・・私、シズネさんに、あの男に見覚えありますか?って聞かれたのよ」 「げ、マジで?」 「怪しいなって思ったし、あんな里の入り口で戦うの嫌だったから、見覚えあるって答えたの。あれで私が見たことないって答えたらどうしてたわけ?」 確かにそうだ。彼女は元々戦闘ありきでこの任務に臨んでいたのだ。もしあの場でシズネの質問にノーと答えていれば、ナルトの正体などすぐに明るみになっていただろう。 「こんな穴だらけの計画、よく上手くいったわね」 「アハハハ、ハハ・・・」 「皆にも迷惑かけちゃって・・・」 「でっでもさ、上手くいったってことは、きっと旅行しろってことなんだって!」 「なにその勝手な、んう」 それ以上は言わせまいとナルトは強引に彼女に口付けた。溶接するように、ぴったりと。ただでさえ身動きの取れない姿勢だというのにが身を捩じらすものだから、彼女を支える男の手に一層力が込められる。ばたつかせた足の抵抗が止むまで息継ぎすら許さないキスは、ただ触れているだけなのにひどく暴力的だ。 観念したのか体の力をゆっくりとが抜いたのを確認して、ナルトは唇を解放したのだった。 「でも今は俺が雇い主だから。わかった?」 「・・・う、ん」 鼻先のぶつかる距離で、普段より低い声でそんなことを言われてしまえば、にはもう「里に帰らないと」なんて野暮なことを言う気力は残されていなかった。 (う、どきっと、しちゃった) 「よっしゃ、それじゃ行くってばよ!」 (2015.3.27) CLOSE |