風が網戸越しに部屋を抜けていった。肌の上を通る柔らかな刺激を感じ取ったのか、眠っているの目蓋がピクリと動く。普段ならとりとめて気にすることではないが、働き詰めで気を抜くことができない毎日では、些細なことにも身体が鋭敏になってしまうようだ。 「・・・ん、う」 重たい目蓋をゆっくり開くが、どう頑張っても全部は開きそうにない。寝ぼけ眼でもぞりと上体を起こしてみるが、疲れが抜けきっていないのか鉛のように身体が重たかった。 二度寝を決め込むことができたらどんなに幸せだろう。異国の御伽噺に出てくる眠り続ける姫のように、全てを忘れて眠れたら。しかしそれができないからこそ此処は現実なのであり、そんなことを思えば思うほど御伽噺が色褪せていく。 二三度目を擦った彼女が壁時計へ顔を上げると、時刻は午前十時をまわったところだった。 (三時間もベッドで眠れて嬉しいとか、感覚おかしすぎ・・・) だがそれもその筈だ。なにせこの三週間の睡眠時間は平均して二、三時間の仮眠がいいところで、それも野宿が殆どだったのだから。ふかふかの布団に包まって寝たのなど数えるほどしかない。 一つの任務で班員を引き連れて三週間というのなら、よくある期間であり生活のリズムも取りやすい。しかし今回彼女は日にいくつも任務を請け負っていた。自らの顔見知りを引き連れて部隊を編成することもあれば、全くの初見の人間の場合もあり、かと思えば一人であっちへ行けだのそっちへ行けだのと言われ、碌な食事にありつくことは皆無だったし、責任を取らねばならない立場の彼女には安眠もまたなかったのだ。 「・・・ベスト、ナルトかな」 正直、帰宅後の記憶が曖昧だ。ナルトがいたということも朧気にしか覚えていない、いや、それすらも本当だったのか解からない。けれどたまに家に帰ってきても、ボロボロの身なりのまま寝室に直行し倒れこんでしまうのだから、自分でベストを脱いでないとすればやはりナルト以外には思いつかなかった。 (最後にちゃんと喋ったのいつだろう) このハードな肉体労働は、最初は単に移動も含め五日間の鉄の国の国境警備のはずだった。それが三日目に起こった国境近くでの戦闘あたりから一気に忙しくなったのだ。敵組織の情報を割り出すこと、アジトを見つけ壊滅させること。そうしてようやく里に帰れるかと思えば、急遽単独の追加任務。部隊だけ先に里へ送り返し、雲の国にて密書を受け取ったは良いが、今度はその雲の国界隈で起きた誘拐事件の解明に強制参加。やっとこさ木の葉に帰ってくると、これまでの予定変更のおかげで溜まりに溜まった任務を言い渡される始末。 それもこれも同盟が連合に変わってから、それぞれの里が持つ依頼請負システムが変更されたせいだ。同盟国での情報共有が必須になったため、共同戦線を張ることも多いのだが、良いこと尽くめではない。今回のようにたまたま近くにいたというだけで追加任務が与えられると、中々里に帰ることができないのだから。 そしていくら情報の共有と言えど、里の根底に関わるようなものについては里それぞれの管理下が原則だ。そういった分野に関しては今も暗部がその一端を担っており、公にできない任務が数え切れないほど存在している。そのような毎日だから、家に帰れたとしても布団に飛び込むほどの僅かな時間しかなかった。決してナルトのことを忘れていたわけではないのだが、この三週間に、仕事量にして約三ヶ月分ほどこなしていたために、久々に体も心も精一杯だったのだ。 (・・・ごめんね、ナルト) ナルトがを思ってあれこれしていたのには、彼女自身も気が付いてはいた。恋人は食事を作ってくれていたし、洗濯だって、掃除だってしてくれていた。メモの一つでも残してやれたならまだ良かっただろうに、と彼女の胸には後悔の念が募る。 (なにが隊長なんだろう、ナルトに気も使えていないのに) 仕事を言い訳に、そんな簡単なことすらできなかった、なんて許されることではない。お互い忍だ。いつなんどき任務が入るかわからない毎日を理解しているとはいえ、二人で一つの屋根の下に暮らしているのだから、相手を思いやれなくてどうする。すっかり大人になった年下の恋人だが、元来我慢強いタイプではない。思ってることは直ぐに口に出すし、納得いかないことがあれば直ぐに行動しようとする。そんな彼が何を言うでもなくただじっと耐えていたのだ。きっと寂しい思いをさせただろう。それを思えば思うほど、切なさで心が締め付けられてしまう。 「任務・・・」 後悔したって始まらない。とにかく仕事を片付けなければ、休みもなにもないのだから。 はベッドから降りると、新しい忍服を取り出し洗面所へと向かった。ゆっくり風呂に入る暇もない彼女は、文字通りからすの行水で済ますと、タオルで頭をガシガシと拭きながら、水を飲むべく台所へと歩いていく。 しかしそこで最初に目に入ったのは。 「え・・・」 勝手台に、ぽつんと乗っかるカップラーメン。最早侘しささえ感じられる、蓋が半開きのそれ。 「・・・手付かず?」 怪しげに捲ってみれば、蓋に付着しているすっかり冷えた水滴が、容器の中に零れ落ちる。湯気の「ゆ」の字もないそこは、一体いつ作ったのだろうというぐらい、あらゆる水分を吸って膨張した麺に支配されていた。 「急な任務かな・・・」 しかしあのナルトが麺を放っておくなんて、正直考えられない。とはいえリビングには脱いだ形のまま放置されているナルトの寝巻きがある。やはり何か急用ができたのかもしれない。その寝巻きを横目に彼女は冷蔵庫からミネラルウォーターを取り出すと、何を思ったのか徐に箸を取り出して、目の前の伸び切った麺をつまみ上げようとした、のだが。 あまりに伸びているので、つまんだ瞬間に切れてしまう。それでも意地で持ち上げ口に運べば。 「ふにゃふにゃ・・・」 もう一口食べる勇気が出なかったのか、彼女は諦めて箸を置いて、ポケットの兵糧丸に手を伸ばした。一つ口にすれば三日三晩は寝ずに戦える、なんて謳い文句のある兵糧丸だが、最近多用のし過ぎで体が慣れてしまった気がしなくもない。そのため二つ三つと平気で服用していたが、食事とはまるで違う黒い塊はとても味気なく虚しかった。 ため息をついたはふと、自身の手首に刻まれた鳴門のマークに視線を落とす。 黄枯茶色の、暗喩。 (一緒にご飯、食べたい) 休みになったら、ナルトと何を食べようか。 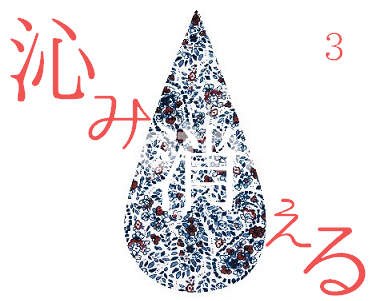 家を出る寸前、伝令鳥により急遽任務変更の命を受けたは、「あうん」の門にやってきた。ここで依頼主を待つよう文に書いてあったのだ。元々今日は暗部での任務が入っていたのだが、それを後回しにしてでも優先したい任務とは、はて一体なんだろう。 (・・・空が眩しい) 指定された五分前に着いた彼女は、手持ち無沙汰のまま空を見上げた。眠気を伴う両の目に、なんてことはない青空すらいつもの数倍は明るく感じられる。まだ空気がひんやりしているとはいえ、これから午後に向かって力を発揮しだす太陽の熱も、肌を通って伝ってきている。 (立ったまま寝れそう・・・) 時の流れと共に微睡みも。 段々と思考能力が低下していく自分に気付き、いかんいかんと顔をペチペチ叩いていると、一人の男とシズネが一緒に歩いてくるのが目に入った。彼女は一足手前で男を立ち止まらせ、一人だけでの元へとやって来る。 「任務詰めなのに本当にごめんなさい、これ、綱手様から。特別仕様の兵糧丸です」 「ありがとうございます。シズネさんも眠そう」 「あはは・・・お互いもう少し頑張りましょう、そうそう、今日の任務なんですけど、実はちょっと聞きたいことがあって」 「聞きたい、こと?」 「ええ、あの男性をご存知ですか?半年ほど前に面識があるそうなんですが」 あの男性、それは勿論シズネが連れてきた男のことだ。 がちらりと後方に目配せする。中年ぐらいの、あまり特徴らしい特徴の無い男だ。彼女は記憶を必死に探ってみた。しかしこれといってどこかで接点があった覚えはない。記憶に残らないぐらいの些細なことだったのかもしれないが、それでも職掌柄、関わりのあった人間に関して、そのすべてを忘れてしまうことなどあり得ない。けれどあちらは自分をよく知っていると言う。どういうことだろう。 「・・・む」 「昔、山賊に襲われたところを助けてもらったと言っているんです」 ―山賊。 そのワードに、の脳裏に一筋の線が走る。そして思い出す。昔、そんなことがあったのを。あれはいつかの任務の帰路の途中、どこからともなく叫び声が聞こえた時のことで、何が起きたのかと声のする方を辿れば、山賊に襲われている夫婦と出くわしたのだ。 (・・・でも) 彼女はもう一度男の顔を一瞥した。 (・・・この男じゃ、ない) そう、彼女の記憶の中では、当時助けた夫婦とこの男とがどうにも一致しないでいた。では何故この男は自分しか知りえない情報を知っているのか。報告書にだって詳しいことは書いていない。なのに詳細を知っているということは、あの時自身の気が付かぬ間にあの場にいたということだろうか。 (・・・・・・) 考えたところですぐに答え出せそうになかった。そのため彼女はシズネに次のように答えたのだった。 「ああ、そういえば、確かに。覚えがあります。随分前のことだったから忘れかけてたのかも」 あたかも今思い出したような返事をしたが笑顔を繕うと、シズネは彼女の言葉を信じたのか、ほっと胸を撫で下ろした。身体検査を徹底し、綱手と面会させたとはいえ、シズネもこの突然やって来た男に半信半疑でいたのだ。ごまかすことなんていくらでもできるが、助けた本人が覚えがあると言っているのだから、とりあえず間違いではないのだろう、と。 そうとなれば早速、とシズネは任務内容をに伝え、軽く頭を下げ煙とともに消えてしまった。普段ならば火影の付き人が依頼人と忍を集合場所に引き合わせることなどしないのだが、おそらく今回は不安材料があったから直々にここに来たのだろう。シズネがいなくなったのを見て、立たされっぱなしだった男がの元に歩いて来るその様を彼女は注視した。年齢の割に幾分足腰が身軽い気がしなくもない。 「さん、久しぶりだな」 「・・・お久しぶりです」 「早速だが行こう」 男はにこりと目を細め、そのまま里の外へと歩き出す。自らの横を通り抜く瞬間や、先立って歩く男の後姿をまたも彼女はじっと見つめた。 服の下に武器を隠し持っている様子はない。確かにぱっと見た限りおかしな点はどこにも無い。けれど何故だか違和感がある。だがそれが何であるのかがいまいちピンとこない。疑ってかかっているからこそ勝手に違和感を覚えてしまうのだろうか。 (でももし、何かを企てているとしたら?) そう仮定したからこそはシズネの質問にノーとは言わなかった。万が一戦闘でも始まった場合、相手はあの綱手やシズネを騙しきったのだから、何かからくりを持っているか、相当な手練れに違いない。そうなれば一般人もいる里の出入り口付近での戦闘は避けたい。人質を取られでもしたらたまらないからだ。まずはその仮定を確信に変えるために、相手の本性を探る必要があった。 彼女は平然を装いつつ、快活に進む男に続いたのだった。 * 「私の妻は、笑顔がとても綺麗なんだ」 舗装された道を歩きながら男は言った。しかし横に並ぶが返事をすることは無かった。 「いつも笑っていてほしい、それだけが願いなんだよ」 男の顔には哀愁が浮かんでいる。その切なさに満ちた表情から嘘は微塵も感じられない。妻を想う夫の顔そのものだ。 だから彼女は困った。演技でこんな表情ができるものだろうか、もしかしたら自分の記憶違いだったのではないだろうか、と。 「さんには、そういう人はいるのかな?」 「・・・任務中ですので」 馴れ合う気のない彼女を窺い見るように男が首を傾げる。無表情だ。凛と前を向いて歩いてはいるものの、とにかく彼女は無表情だ。そんな彼女に居心地の悪さでも感じたのか、男はさらに口を開いた。 「妻は弱っていて口もそんなに聞けない。だから着く前に色々とさんのことを知りたいんだ、それも任務の内には入らんかな?」 妻を想う、その一心が、この男を動かしている。忍であってもとて一人の人間だ。心が動かない筈はない。ないのだけれど。 (この違和感は、なんだろう) 木の葉の門で会った時にも感じた、この違和感は―…。 それがわからないことには男の正体に近づけないのだから、感情に訴えられたからといって彼女にはそうやすやすと身の上話などできはしないのだ。そうして彼女が「ご容赦を」と返事をしようと口を開いた時だった。穏やかに流れた風に乗って、一片の花びらが舞い落ちてきたのは。 (・・・蝋梅だわ) それはこの時期に黄色の花を咲かせる蝋梅だった。目の前の花びらをは視線で追う。土の上に落ちたそれがまた風に乗ってどこかへ流れていった。さらに先を追えば、気付けば周りは沢山の花びらで吹雪いていた。 「おお、綺麗だな」 まるで桜のようにひらひらと舞う美しい光景に男の声が弾む。春の到来を告げるとも言われる蝋梅の、甘くて芳しい香りが二人の鼻をくすぐりだす。その香りを男が胸いっぱいに吸い込み満喫している姿を見て、彼女は自身が抱えているものの答えが、喉元まで出掛かっていることに気が付いた。 (・・・ああ、そっか、これだ) 足元に落ちた新たな一枚に、さらにこの花が放つ香りに、自身がこれまで男に感じていた違和感の正体に、ようやく辿り着く。 そして彼女は足を止めた。横を歩いていた人物が急に視界から消えたものだから、男もつられて足を止める。すっかり心の靄が晴れたは、真剣な眼差しで男と向き合った。 「どうかしたかね?」 「あの、木の葉に来る時、どこを通りました?」 「・・・どこ?どこって、山を越えて、この道を通って、火の国の森を歩いて、だったかな」 突然何故そんな質問をするのだろう、と男は首を軽く傾げつつも、彼はその質問になんの躊躇もなく答えてみせる。 「なッ!!」 その回答に一つの確信を得たの行動は、目にも止まらぬ速さだった。 「さん、何をするんだ!」 男の後ろに聳える蝋梅の木から大きな影が上から下に動いたかと思えば、次の瞬間には男は首元にクナイを突きつけられていた。それは彼女の影分身―「あうん」の門で依頼主を待っている際に仕込んでおいた影分身―だった。 綱手から伝令を受けた内容にはシズネが随伴することも書かれており、その時点で彼女は何か不穏な点を感じていたのだ。念には念を。忍の基本である。 「何者なの」 皮膚を切らない程度にクナイの先端を食い込ませ、軽く殺気を飛ばす。男の体が震えたのが解かった。 「・・・匂いが無いのよ、あなた」 「に、匂い?」 「山を越えて、この道を通ってきたなら、普通は服に土の匂いとか、外の空気の匂いが付くわ。でもあなたからは何も匂わなかった。・・・汗の匂いすらも」 そう、それこそが彼女の胸に蔓延る靄の正体だった。 男の言うとおり、彼女が以前助けた夫婦の国から木の葉隠れの里までは、確かに山を越え、この街道を通り、さらに火の国の森を通らねばならない。そんな道中を一日ほどの時間をかけてやってきたというならば、当然衣服にそれらの匂いが染み付いているはずなのだ。たとえ一般人には気付けずとも、忍の嗅覚でならその気で嗅げば何の問題もない作業。なのにこの男からは何も匂わなかった。体臭すらしないとは、全くおかしな話ではないか。 身体検査に引っかからなかったのは、おそらく所持品のチェックやチャクラの流れを見ることの方に重きを置いてたからだろうし、検査室の人間の数だけ体臭が混ざっているのだから、その中に入ってしまえば見つけにくいことこの上なかったのだろう。 「私は確かに半年前に山賊に襲われた夫婦を助けたけど、でもそれはあなたじゃない」 だがこれは問題の一部分が解決しただけなのであって、全てではない。目の前のこの男が偽りの人間であったと判明はしたものの、肝心の、この男が何者あるのかが分からない。何故報告書にも書いていないことを、この男は知っているのか。 はさらにクナイを強く押し付けた。 「ちょ、ちょ、待っ、待ってくれ!」 命の危険を感じたのか、降参とも言わんばかりに狼狽した男から大きな白い煙が上がる。それは術者が術を解くときの、あの白い煙と同じであった。 ―とうとう、正体が白日の下に曝される。 (2015.3.24) CLOSE |