代々奈良家の人間しか立ち入ることの許されない森の中で、特別通行証を首から提げたナルトはシカマルと共に獣道を歩いていた。 日の当たるところでは、草木の葉、花の一枚一枚が、燦々と降り注ぐ陽の光を浴びて、一層鮮やかな色を映し出している。さらに木々の合間から、あたかも天へと続く梯子のように木漏れ日が筋を作り、時折風が吹いてはその筋を揺らめかせ、幻影的な風景の演出に一役買っていた。その一方日陰は鬱々としており、樹木や石に苔が生えているところは一年を通して日光が当たることが少ないのだろう、鬱蒼としたそこは肌にひんやりと冷気すら感じさせるようだ。 苔に足を取られないよう注意して進みながら、森の中でも一際存在感のある巨木の前までやってくると、シカマルは膝を曲げ腰を落とし、周辺に生えている野草を摘み始めた。どうやら必要な部分は球根らしく、葉の部分を千切り土を軽く落してから、それを持ってきた小篭に次から次へと入れていく。その姿を後ろから眺めていたナルトは友を手伝おうと、今しがた摘まれた草の形をしっかりと目に焼き付け、それと同じものを抜こうとした、のだが。 「そいつぁキツネユリって言って球根にとんでもねえ毒があるんだ、抜くなよ」 「ひっ」 「毒」というワードに敏感になったナルトは、伸ばした手をそっと戻すと、また別の野草に手を伸ばした。 「シカマル、これは?これは?」 「そいつも毒があるぜ」 「む、どれも一緒に見えるってばよ・・・お、これとかは?」 「おい・・・手伝わなくて良いからじっとしてろ、死人がでる」 ナルトの目にはどれも同じに見える草木も、森を任されている奈良家の人間にとってはどれもが違うもの。 人様に渡す際に間違いがあっては、信頼関係にひびが入るどころか取り返しのつかないことになるのが目に見えているため、幼い頃から森に息づく全ての生命の知識を徹底的に叩き込まれるのだ。シカマルがため息を付きながらも必要な薬草をどんどん篭に入れていく様を見て、ナルトはただただ純粋に感動していたのだった。 「よし、必要なモンは揃ったから、あとはサクラんとこで調合してもらえ」 「サンキューシカマル、ほんっと助かったってばよ」 「ほら、急いでんだろ、とっとと行けよ」 「おう!今度メシ奢っからな!」 言うや否やナルトは「じゃあな」と言うと印を結び煙とともに消えてしまった。風圧で生じた土ぼこりを細目でやり過ごしたシカマルが、訪れた静寂を真剣な眼差しで射竦める。 「・・・」 任務で必要な薬があるのだと言う友を疑うわけではないが、正直腑に落ちない点がいくつかあった。 一つ、何故医療部隊の人間ではなく、前線へ赴くナルト自身が依頼しに来たのか。 任務において必要な物資は、基本的には火影のお付きであり、医療部隊の頭でもあるシズネによって、医療忍者それぞれに命令が下される。だから前線へと赴く忍が直接奈良家を尋ねるのは滅多にあることではない。(少しはある、という意味においては、それは人員不足の時が大体であるが、今里はそういう状況には陥っていない。) 一つ、何故任務直前にやってくるのか。 基本的に任務へと携帯するものは、全て十分すぎるほどの予備がある。それこそ急に入った特殊な任務にも対応できるように、種類も豊富に蓄えがあるのだ。それに万が一備品がなかったとしても、ここに寄越すならナルトではなく医療班、それか研究部の誰かだ。緊急事態と言うのならば、尚更薬草の見分けもつかない人間を寄越すのには疑問が残る。 そして一つ、何故通行許可証を持っていないのか。 現在ナルトが持っているものはシカマルが急遽用意したものだ。通常ならば綱手またはシズネによってそれが渡される筈であるが、ナルトは許可証の存在すら知らなかった。 この三点からだけでも、ナルトが公的な理由から、薬の調合に必要な薬草を欲しがっているとは思えない。 つまるところ私的な目論見があって使おうとしているのは明らかだが、それでも何故シカマルがこれらに目を瞑ろうと思ったのか。それは自分の所に懇願しにきた友の目に、一寸の動揺も、嘘も、悪戯心も無かったからなのだった。ただ一心に自分を見る真っ直ぐな瞳には覚悟すら浮かんでいて、過去にサスケを取り戻そうと必死になっていた目を彷彿とさせていた。こういう時のナルトが間違いを犯したりはしないことを、シカマルは十分に理解していたし、だからこそあれこれ問うのは野暮というものなのだ。 (・・・おおかたさん絡みなんだろうけど。後先考えない奴だからな、めんどくせーことにならなきゃ良いけどよ) 尻拭いをするのだけは嫌だ、とシカマルは銜えた煙草に火を点けた。肺に落すのが好みではないのか、吐き出された煙がゆらゆらと青空へと昇っていった。 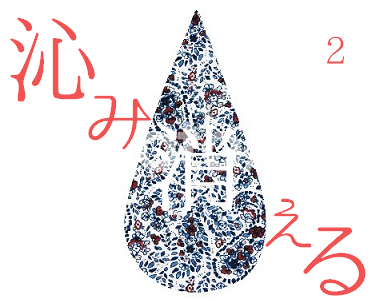 シズネは神妙な面持ちで火影の執務室へと向かっていた。普段とは違う顔つきに、彼女の腕の中にいるトントンがなにやらひ弱な声をあげている。 「綱手さま!」 勢いよく扉を開けると、沢山の書類と格闘する綱手がああでもないこうでもないとぶつくさ呟いていた。彼女はシズネと目を合わせることもなく、書面を見ながら「どうした」と声をかける。 「受付所にて急を要する依頼が」 「なんだって?」 「それも・・・さん以外では駄目だと言っていて」 人名を指名しているあたり、ただの依頼ではなさそうな雰囲気を感じ取る。綱手は手を止め、しばしの間考え込むと、眉間に皺を寄せたまま顔を上げた。 「・・・どんな内容だろうと今はこれ以上あいつに任務は任せられん、人を変えるか日を改めてもらうかどちらかにしろ」 「それがですね・・・」 シズネが依頼された内容を語り出す。 依頼主は火の国と風の国との丁度中間辺りにある、とある国の男だった。男は初老を過ぎたぐらいの容姿で、それなりに裕福であるのか身に纏う服は上等な布のように思えた。その男が言うには、半年ほど前偶然山賊に襲われたところをに救われたらしい。特に男の妻は持病を患っていて、悪漢に襲われたことでショック症状を引き起こしてしまったのだが、その日はたまたま薬を家に忘れてしまい、最早死を待つしかなかったという。しかし病状を聞いた彼女が薬草を集めて、所持している医薬品と合わせて応急処置的な薬を調合してくれたらしい。そのおかげで妻は一命を取り留めた上、さらに彼女は妻をおぶさり、家まで運ぶと、その後も一日ずっと付き添ってくれたのだそうだ。 しかしそんな妻の持病が最近悪化してしまい、余命は僅かだろうと医者に宣告されてしまった。命の期限を察した妻はこれまでを振り返りながら、やり残したことを少しずつ消化する日々を送っているのだが、その中でも特にしたいことがあると言い出した。それは彼女に十分な礼をすることだった。 妻は彼女に命を救ってもらいながら、礼ができなかったことを酷く悔いていた。その当時、妻の容態が安定してから直ぐに彼女が家を後にしてしまったので、そのことをずっと気にしていたらしい。去る先月にはなんと孫が生まれたそうで、あの時彼女に命を救ってもらわねば、孫の顔を見ることができなかったと思うと、一目でも良いからどうしても彼女に会いたいとのことなのだ。ちゃんとした礼もできずに死ぬなんて、罰当たりすぎて死んでも死にきれない、と。 なので男はこうして遠路遥々木の葉隠れの里まで来たのであり、依頼を申請する上で担当の忍は以外では駄目だと主張したのだった。 「どうしましょうか・・・」 「・・・その男の話の裏は取れてるのか?」 睨んでいるとも取れる眼差しで、綱手はシズネを見上げた。これは彼女の癖ともいうべきもので、物事を思慮する際はこういう厳しい顔つきになることがしばしばあった。 綱手としては話を信じてやりたいところだが、まずは何よりその話の信憑性と男自身の潔白が必要だ。信用に値するものでなければどんなに心に響く内容であれ認めることはできない。過去にはそういった作り話で相手を信用させ、若いくの一に自身が雇い主なのだからと詰め寄り、淫らな行為を強要することがあったのも事実だ。任務を依頼し、請け負う関係は常にクリーンでなくてはならない。ましてや他国の人間を相手にするとなればそれはますますそうだ。 「さんの提出した過去の報告書を見ましたが、半年前に確かにそういうことがあったようです。ただ「病人救護のため帰還遅延」とは書いてますが、男についての詳細は何も・・・。まあ突発的なことだったので、詳しいところは知り得なかったのかと」 「ふむ・・・何故その男はの名を知っている?」 「一日付き添っていたとも言っていますし、名前ぐらい聞いた可能性はなきにしもあらずってところですかね」 シズネの説明に、綱手はいまいち納得がいっていないようだ。それもそうだ。目立ちたがり屋の誰かと違って、彼女は任務中に自ら名を名乗るようなタイプではなかったのだから。それが依頼主に対する自己紹介というならまだしも、偶然出会った人間に対して名乗るなどとは。それに彼女は暗部にもまだ籍がある。不必要に己の素性を表に晒すのはご法度だ。とはいえシズネの言うような状況も起こりえないわけではない。命を救ってもらった相手の名ぐらい誰だって聞こうとするものだろう。 「身体検査の方は?」 「そちらも特に怪しい点はありません。私も同行したのでほぼほぼ間違いはないかと」 「そうか・・・。仕方ない、今日のあいつの任務はまた後日にまわすとして、その依頼、正式な文書に起こしてきな。あと依頼人をここに連れて来い」 「はい、わかりました!」 そう言うや否や綱手は、小さな紙に墨を沁み込ませた筆で二、三行文字をすらすらと書き付けると、窓辺に待機していた伝書鳩の中から無作為に選び出した一羽の足に括り付け空へと放った。 勢いよく飛び立っていった鳩から落ちた羽毛が、ちらほらと机の周辺に舞っていた。 「まったく・・・どうしてこう物事集中するんだろうね」 はあ、とため息を一つ。 任務に送り出す側の人間の苦悩は、送り出される者よりも強いのだった。 (2015.3.19) CLOSE |