鬱蒼と草木が生い茂る中、雨季独特の湿度とドクダミの匂いが辺りに蔓延していた。それはカカシにとって久々の暗殺任務であった。森の中を自里へ向かって進む駕籠の中の要人の周りには、予想以上に護衛の忍が多く、しかもそれらが全くと言って良い程隙を見せないあたり相当の手練であることが予想された。それでも一番後方に居たのは中忍クラスだったのだろう。脇の引き締めの甘さが幾分垣間見えた。隙を突いて始末し、さらに部隊の前方に一瞬の大きな隙を作るために、影分身で三方向から要人と護衛の忍を包囲する。案の定できた隙を無駄にすることなく鮮やかに次から次へと始末していくが、殊の外写輪眼を消費してしまったようで、影分身をした事も相俟ってカカシはチャクラの残量に懸念を抱かずには居られなかった。 万が一の事態を考え、戦闘に突入する前に応援要請の忍鳥を火影に向かわせたものの、そもそもこの任務が暗部の人手不足によって止むを得ずカカシに回って来たために、肝心のそれはあまり期待できそうにない。一人ずつ相手にするならばまず負けることはないだろう、そういう自信がカカシにはあった。だがしかし、それなりの使い手を一挙に十人以上も相手にするのは流石に厳烈だったようで、息が上がり始めてしまう。来るか来ないかも解からぬ応援を期待するよりも、この状況を一人でどう打破するか、考えるべきはそれであった。 その矢先、大鎌で切りかかるような風が森の中を駆け巡り、同時に草木の、とりわけドクダミの香りがよりその濃度を高くする。犬並みに鋭いカカシの鼻を鈍らすのにこれ以上無い攻撃はなかった。独特の馨香にカカシが顔を顰めた瞬間、周囲のあらゆるところから彼目掛けて、無数の起爆札付きのクナイが飛んでくる。身代わりの術を繰り出す余裕はなく、上にジャンプするしか逃げる道は無かったが、それが敵の狙いだと解からないカカシではなかった。とはいえ今はそれしか攻撃を回避する術は無いと、仕方なしに上に跳ぶと、また新たなクナイが四方八方から飛んで来たのだった。 (・・なんだ?) 一瞬だがクナイの先端が鈍く光ったような気がした。もしかしたら単に光が反射しただけかもしれない。しかしもし毒が塗られているとしたら。確証は無かったのだが、仮にそうであるとするならば何としてでも避けねばならない。だがこの状況で一本も当たらずに済む考えは瞬時には浮かばなかった。致命傷を避けるためには何本か刺さるのは必至であるが、最低限の救護パックは持っているので、もしあの鈍い光が毒であっても応急処置的な解毒は可能であると踏むと、カカシはごくりと唾を嚥下する。 襲い掛かってくるであろう痛覚に覚悟を決めた瞬間、一体何が起こったのであろうか、カカシの位置よりさらに上空から、何者かによって肩を下に押されてしまったのだった。強制的に下に落とされたことでカカシはその身にクナイを受けはしなかったが、予想外の状況に当然困惑せずにはいられなかった。 「え、?」 「おまたせ」 地面に着地すると同時に彼の眼前には背を向け立つ女性が一人。くるりと振り返りこちらへ向けられた笑顔は、夜勤だからと昨夜玄関で見送ったあの笑顔と何ら変わりがなかったものだから、カカシは呆気にとられて緊張の糸が変に緩んでしまう。の姿に思わず温かさが染みるように胸中に広がるも、カカシは彼女が自分を庇ったことで負ってしまった腕の傷を見遣った。傷自体は浅そうで、大した出血もない。しかしまだ安心すべきではなかった。何しろ先程クナイの先端に違和感を覚えていたのだから。 「腕、平気か?」 「うん、大丈夫。ここは任せて早く行って?」 が笑顔で腕をぶんぶんと振る。一見何も無さそうだが、カカシは一抹の不安を拭うことが出来なかった。けれどそうこうしている間にも目的である要人を乗せた駕籠は前に進んでいく。大丈夫だと言う彼女を信じ、カカシは任務遂行の為に走ったのだった。 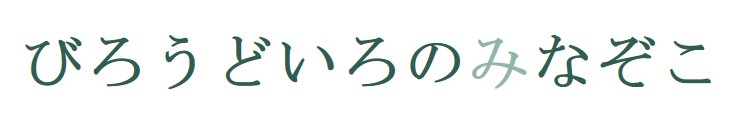 要人の暗殺を終え急いでの元へと戻ってくると、すでに息の根の止まった忍に混ざって彼女自身も倒れていたのだから、カカシは大層驚かされたのだった。目立った外傷はカカシを庇った時にできた傷以外には無かったが、駆け寄って抱き起こせば大量の汗で前髪がぐっしょりと濡れていた。 やはりクナイの先が光っていたのは毒だったか―…。 畜生、とカカシは奥歯を噛み締める。恐らく虚を突くために毒は遅効性だったのだろう。戦闘が始まる前に確認した敵の数と、今現在倒れている数が一致していることから、殲滅してから毒が回り始めたに違いない。毒の回る時間が少しでも早かったなら、と、起こりえたであろう事実にカカシは身の毛がよだつ。 朦朧とした意識の中でも銀髪の存在を捉えたのか、は苦しそうに息を短く繰り返し吐きながらも口を動かしていて、カカシはそれを聞き取ろうとすぐさま耳を寄せる。すると彼女は「痺れる」の一言ととも瞼を落としてしまったのだった。使用された毒はどうやら神経性の痺れを引き起こすものらしい。致死性の毒でないというのが不幸中の幸いとも言うべきか。カカシは解毒剤を打とうとしたのだが、既にの直ぐ傍に空になった注射カプセルが落ちており、命に別状がないことを確認すると、ほっと安堵の息を洩らす。それも束の間、とにかく戦闘地から離れるべくカカシはをそのまま抱きかかえ、人目につかない森の奥へとさらに進むのだった。 適当な木陰に結界を張りその中に彼女と共に腰を据えた。彼女の額に浮かぶ玉のような汗を布で拭き取ると、皮膚に乗せられる布の感触に気が付いたのかがうっすらと瞳を開く。彼女の少しだけ熱に浮かされた、それでも先程よりは幾分具合の良さそうに見える瞳に、カカシはそっと微笑んだ。 「・・・ごめ、んね、カカシ」 まだ残る痺れのせいか、彼女の声はたどたどしかった。 「それは俺のセリフだよ、悪かったな、つらい思いさせちゃって」 「応援に、来たのに、足引っ張っちゃった」 「なーに言ってんの、が来てくれなきゃ今頃どうなってたことか」 足を引っ張るなどとお門違いも良いところで、感謝してもしきれないぐらいだ、とカカシは思った。応援など微塵も期待していなかったというのに、そこに彼女が来てくれたのだから、と。それに夜勤帰りで疲れているだろうに、申し訳ないことをしてしまった。 「まだ痺れる?」 「ちょっと、びりびりする。でもさっきよりは、平気」 心配をかけたくなくては無理に笑ってみせたのだろうが、カカシからしてみればその笑顔が身体の辛さを物語っているようにしか思えなかった。きゅっと胸が締め付けられる思いとともに優しくの頭を撫でると、彼女は安心したように目を閉じ頭を預けてくる。 (戻るのはもう少し休んでからでいいかな) 暗殺の目標だった要人といっても、ターゲットは国を揺るがすような一国の主では無い。売春に手を染め財を成した下衆な輩だった。その為報告書の提出の為にすぐさま里に直帰せねばならない状況でも無いだろう。なのでこのまま彼女の状態を様子見しつつ、しばしの間休んでいこう、カカシはそう心に決めたのだった。相変わらずドクダミがその主張を忘れずに度々風に乗ってやってくる。雨上がりで無いだけまだましだろうか。静寂が包む森林の、日陰の至るところにその根を生やすドクダミを見て、カカシはそれについて熱く語る暗部の忍がいたことをふと思い出した。 (名前は、なんだったけ) 自分より三歳ほど年上の、普段は落ち着いた物腰だが、薬草の話となると途端に人が変わる男。 ドクダミの花だと思っていたあの白い部分は実は本当の花弁ではなく、あれは総抱弁と呼ばれる器官で、中心部の黄色い蕊のように見えるのが花の集合体なのだと聞いた時には正直どう返答したものかと困ったものだが、あまりにも熱く語るものだから草の話よりも彼自身の方が面白かった記憶がある。思わず零れた笑みに、彼は自分自身が笑われたのだということには露とも気が付かず、草木に興味を持ってくれたのかとそう言わんばかりに他の薬草についてあれやこれやと話をし始めたのだ。不思議とどこか憎めない男だった。 「・・・ドクダミ」 ぽつりと呟かれたの声にカカシははっとした。 「白いのって花じゃないんだって、カカシ知ってた?」 直ぐ傍に生えていたドクダミには手を伸ばし、抜こうとしたのだろうが、いまだ痺れの残る身体でそれは叶わなかった。するりと彼女の手を抜けたドクダミは元あった状態のまま、時折吹く風にその身を揺らしている。彼女は虚ろな瞳で掌をじっと見つめた。そしてそのまま鼻先に持っていくと、「くさい」と聞こえるか聞こえないか程の声を洩らした。 「・・・」 ああ、そういえば、そうだった。カカシは思った。けれどもそれを口に出したくは無かった。忘れた訳ではなかったが、自分の女の過去の男の話など、正直聞きたくも無ければ、思い出したくも無かったのだ。人柄の良い憎めない男だっただけに、余計に。例えば、今あの男はどうしてるのか、といったような質問をこちらからするのも嫌だった。友人ならば何に引っかかるでもない質問だが、この場合そうもいかない。この問い一つで様々なことが推測されてしまうのがカカシにとっては苦痛でしかなかった。そうして妙な沈黙を作り上げてしまったと一方的に感じてしまったものの、彼女の方はそんなこと気にも留めてないようだった。けれどもそれを勘違いしたまま、カカシはとうとう投げやりに口を開いたのだ。 「今、何してんのかね」 の瞳が揺れた。明らかに彼女が意識しているのをカカシは見逃さなかった。過去の何かを思い出していたからなのか、読み取ることはできなかったが、その瞳の僅かな動きの一つ一つにカカシの感覚は確かに奪われていた。 「言わなかったっけ」 「ん?」 「そっか、カカシ、長期でいなかったのかも」 「どういうこと?」 「・・・先輩は実は二重スパイで、しかも殺したのは私でしたーって」 笑っちゃうよね、とは呟いた。それも、自嘲と共に。 抜けかけの痺れ薬と陰鬱な湿度にうっすらと浮かんだ汗が、翳りを見せた遅い午後の太陽によって照らされ、地面を見つめる両の眼には儚さが孕んでいて。 不覚にもその姿を美しいとカカシは思った。 「あのさ、」 しばしの沈黙の後、カカシが口を開いたのと同時に、ぽつりぽつりと雨が降り始めた。 快晴とまではいかずも、光が差していて雨など降るような空模様ではなかった筈だが、天気雨だろうか。一気に降ってこないあたり驟雨でもないようだ。 今張った結界は雨には通用せず、そうとなればここにはいられないとカカシは開きかけた口を噤み、を背におぶり足早にその場を後にした。 幾分疲労の取れた体は軽く、どこまでも走れそうだった。 * 黙ってカカシの背におぶられながら、は遠くでハゲワシの鳴き声がするのを聞いた。きっと死体でも漁っているのだろう。嘴が肉を食む感触と、クナイが皮膚を貫く感覚は似ているのだろうなと彼女は思った。 ―背後に回りこみ、左手で口と鼻を強く押さえ付け、右手のクナイでまず腎臓を一刺し、そして耳から耳まで咽喉を切り裂く。 暗部に入りたてで、単純に人間の急所を狙えば良いのだと思っていた自分に、人体の構造について詳しく教えてくれた、あの人。心臓は頑丈な肋骨で守られているため、訓練もそこそこの忍にはそれよりも腎臓が向いている。腎臓には大量の血管が集中していて、骨の守りも無いため非常に狙いやすく、また、腹筋などに比べて背筋はあまり鍛えられていない人間が多いから、その点においても攻撃しやすい箇所なのだ。しかし神経叢が集中している箇所でもあるので、攻撃の際に壮絶な激痛を生じる。だから口も一緒に塞いでおかねばならない。さらに確実性を上げるために頚動脈を狙う。ここで注意しなくてはならないのは、頚動脈には外頚動脈と内頚動脈と二種類あり、内頚動脈の方が太く大量の出血が望めるが、皮膚から深いところにあり且つ筋肉で保護されているということ。すなわち狙わなくてはならないのは外頚動脈で、これを片方だけでも完全に切断してしまえば、腎臓への攻撃と併せていくら医療忍術と言えども治療はできない。 彼を殺したあの時程この時のことを思い出したことはないと、クナイの切っ先が肌の弾力に打ち勝つあの瞬間程、まるでこちらが殺されているような感覚に陥った感覚は無いと。 先輩は自分にとってかけがえのない存在だった。もちろんそれ以上の関係になったのも確かだが、ミナトやクシナとは違えど家族に近しい存在であったことは確かなのだ。だが不思議と裏切られた気持ちはなかった。それ以上にその心の奥底を知ってやれなかった自分に腹が立った。彼は一体どんな気持ちで木の葉で生きていたのだろう。三代目の信頼すらも勝ち取った彼は一体何を思っていたのだろう。そのことを思うと、悲しさよりも寂しさの方が大きかった。それでも現実は残酷だ。近しい人を殺した次の日から、普段なら気にすることもない、美しいまでに計算された図形を描く蜘蛛の巣にすら畏怖した。草原を歩けばその下に漲る生命の根源を感じた。一歩一歩、これが生なのだと。恐怖に震える心に襲い掛かる生の嵐に何度自分を傷つけようかと思ったことか。しかし全てはもう、遠い記憶に佇む、ひとひらの花。深く底の見えない器の中の揺蕩いだ。 「・・・あのさ、」 俺、お前の心、ちゃんと埋めれてる?なんて柄にも無く女々しい質問がカカシの頭を過ぎったりして。 「ふふ、もう吹っ切れてるから」 カカシが何を言おうとしたのかはには解からなかった。しかし先までは言わせまいと抱きつく腕に力を込める。気にかけてほしかったわけではない。困らせてみたかったわけでもない。甘い言葉がほしいのでもない。ただなんとなく、湿った空気とドクダミの匂いに中てられただけなのだ。これから本格的な梅雨がやってくる。梅雨が明ければすぐに夏だ。感傷的な心はきっと夏の暑さに溶けて形を失くしてしまうだろう。 「ねえカカシ」 「ん?」 振り返ることなくカカシは前を向き走り続けた。頭上から降る声は、真正面から聞くそれよりも耳に直接響く気がする。 「寒いから、もうちょっとぎゅってしていい?」 「この湿度でよく言うよ」 「あー凍えそう」 「全く。素直に言えないのかね」 汗ばんだ肌同士がべたりとくっついた。カカシの項からは汗と泥と雨の匂いがした。 (2014.5.25) (2016.3.11修正) CLOSE |