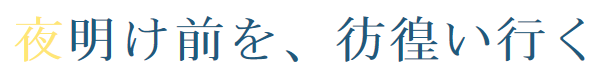
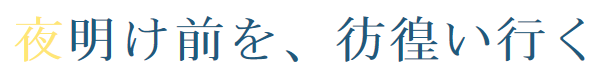
パタリ。栞を挟むことも無くページを閉じ、カカシはサイドテーブルに永遠の愛読書を静かに置いた。本の横には陶器で出来たパグの小さな置物が一つ。いつだったか同居人が任務帰りに嬉しそうな顔で「こんなの見つけたの」と持って帰ってきたものだ。そんな馴染みの無い空間が生活の一部になってからもう随分と時間が経っていて、最近ではカカシが自らの家へ帰る回数もめっきり減っていた。焦点をどこに合わせるでもなく天井をぼんやり仰ぎ見れば、壁にかけられた小さな額縁が視界に入る。今まで特に意識しなかったせいなのか、その存在に全く気が付かなかった。 (ん?あんなのあったけ?) その額縁は四方が十センチ程の小さな物で、中には押し花状の四葉のクローバーが飾られていた。朧気に記憶を辿ればいつだったかの日のことが想起される。あれは確か、カカシが第七班とマダムしじみのペットを探していた時のことだった。それは草むらの中で慎ましやかに背を伸ばしていて、まるで映画の主役のようだったのだ。大人になった今でも何か良いことが起きるのか、などとついつい嬉しくなってしまうその幸運の印は、カカシにさらなる記憶を浮かび上がらせた。それはまだ彼がアカデミー生だったころに、校外学習で班を組んで探していた時のことで、当時は探しても探しても見つからず諦めて帰ったという、子供心に侘しさを抱いた日のことだ。あんなにも苦労して見つからなかったものが、全く別のものを探している時に見つかるとは、と思いつつも探し物なんて物はたいてい、探そうと気合を入れない時のほうが、そう、目当ての物への意識が薄い時にほど見つかるものなのだから。そうして見つけたそれを、話の種にでもなるだろうかと摘み取り帰って恋人に渡して以来、すっかりそのことを忘れていたが、どうやら彼女は大事にしていてくれたらしい。 そんな額縁を軸にカカシは視線だけをぐるりと部屋中に動かしてみる。するとそういう類の二人の思い出が、部屋の中には随分と増えたような気がしたのだった。サイドテーブルの犬の置物もそうだし、戸棚にしまわれた月に一度の骨董市で二人で選んだ食器類や、本棚に並べられた互いの好みの本や、そこに飾られてる一見なんだか分からないような雑貨(といったら怒られそうだ)など。それだけ一緒に歩んできた証なのであるが、改めて考えるとやはり感慨深いものがあった。歯ブラシだとか、洋服だとか、そういう簡単な物じゃないところがまた良い。端から見ればがらくたのようなものでも、二人の中ではちゃんと思い出の品。結婚という二文字は未だ頭の中でイメージとなって膨らまないものの、この前ソファを見に行った時には、無意識の内に二人で使えるものを探していた。完全に彼女の部屋に置く、彼女の私物、だというのに、だ。だからカカシは思う。きっと結婚は、こういうことの延長線にひっそりと置かれているのかもしれない、と。 しかし肝心の部屋の持ち主、がいなくなってから早二週間。やはり部屋は人がいてこそ部屋なのだ。彼女のいない部屋はすっかり色褪せた様にカカシの目に映った。というのも、はある大名の客人の護衛で当初十日間という任務を宛がわれていたのだが、客人たっての希望で延長を請願されたらしい。そろそろ終わる頃合なのだろうが、現地の詳しい事情はカカシにはよく解からなかった。 自分が二週間の任務に就いてる時など、その時間はあっという間に過ぎて行くというのに、待つ身にその期間はとてつもなく長い。その間カカシ率いる第七班にも任務は次から次へと放り込まれたが、下忍に成り立ての子供たちと共に受ける任務は、今までカカシが受けてきたものとは比べ物にならないほど易しかった。朝起きて、慰霊碑に寄り、任務に出かけ、夕方には解散。だから上忍師の特権であろう、忍にしては滅多にない規則正しい生活を謳歌しようにも、読書以外に熱中することなど無いに等しいカカシにとっては、手持ち無沙汰な時間が増えるだけなのだった。なにせ家にいる時の話し相手は当然なのだから、その彼女がいない世界が淡白になりがちなのは、カカシにとって仕方の無いことであろう。 勿論これが初めてではないし、今までに何回もこういうことは経験してきた。半年会わなかったことだってある。仕方がないと割り切っても会いたいという気持ちが消える訳ではない。時々ふとやって来る、ぐっと堪えてもその限界量を超える物憂げな日は決まってセンチメンタルだった。 無性にを抱きしめたい。いっそのこと分身でも出してみようか、などと浅はかな考えが浮かんでは消えてゆく。壁のクローバーを見て、彼女が早く帰ってこないかとどこか女々しい気持ちにカカシはため息を付き、夕飯の支度でもしようと立ち上がった。すると驚いたことに脳裏に描いた愛おしい人の気配が感じ取れるではないか。想像のしすぎで嗅覚が馬鹿になったんじゃないかと疑い、深呼吸の後にもう一度感覚を澄ませてみるが、やはり間違いではない。玄関の扉の前に立つと次第に強さを増すその気配に胸が躍り、扉が開くのを今か今かと心待ちにし数秒。鍵が差し込まれる音とともに、ガチャリとドアが開く。 「・・・わっ」 「カカシ!」 カカシは出迎えるや否や思い切り抱きしめてやろうと目論んでいたのだが、そのカカシの思惑よりもの行動の方が早かったようだ。 彼女も立派な上忍であるから、ドアの向こうにカカシがいることに気付いていたに違いない。思わず動けなくなったカカシは、胸に飛び込んできた脳天しか見えない恋人を見やった。ざっと確認したところ、忍服には汚れも傷も付いていない。血の匂いもしない。ほっと一息つく彼の心を恋人はきっと知らないのだろう。彼女はぎゅっとカカシの背中に手を回し、これでもかという程力を込めると、息をするのも忘れるぐらいに顔を彼の胸板に押しつけた。 熱烈な帰還だ、と緩む頬もそのままにカカシが片方の手を腰にまわし、もう片方での頭をそっと撫でる。すると、子猫よろしく言葉にならない唸り声を上げるのだからおもしろい。まるで伸びをしているかのように気持ち良さそうな声だ。 「はあ、カカシだ・・・」 しばらくの後にが満足そうに顔を上げる。 「よしよしおかえり、お疲れさま」 カカシはの前髪を指で退け、露になった額に口布越しにキスをした。外の匂いを纏いながらも彼女自身の確かな匂いにカカシの心が満たされていく。退けきらなかった前髪が変な角度からちくりと肌を刺すのがくすぐったく、は少しだけ身体を捩った。そんな彼女をカカシは近距離から覗き込む。僅かな疲労の色が見受けられ、少々眠たげであったが、傷一つない、二週間前に見送ったままの綺麗な顔だ。 髪の間にするりと掌を差し込み、指先でその存在を確かめるようにのを頬を撫ぜる。親指が鼻筋を通り、そして唇に。ゆっくりと唇を這う指は明らかに性的だった。ほぼ力が入っていないその指先で唇を押せば、やわらかい弾力が返ってきてカカシの背中がぞくぞくと刺激される。 疲れているとてカカシの指使いに沸々と身体の中で熱が滾るのを感じた。この欲を満たせるのは、他の誰でもない、目の前のカカシだけ。瞳を見つめ返したまま、はカカシの口布にそっと手を伸ばし、下ろしていった。暴かれる素顔はいつ見ても端整で、その美しさ故に少しだけ憎らしい。待ってましたと言わんばかりに、カカシが目の前の柔らかな唇に吸い付く。余裕はそこにはもはや存在しなかった。 求める時間も、息継ぎの一瞬すらも惜しい。十代の健全な性欲にまみれた少年のようにカカシはを求めた。靴を履いていることなどお構いなしに恋人を壁に追いやると、彼女はどうやら自らの足に突っ掛かったらしく体勢を崩しそうになった。それをすかさずカカシが支え、同時に手での手首を壁に縫いつけると、さらに距離を縮めようと角度を変えては貪りつく。荒々しい息継ぎと、お互いから漏れる少し上ずった声が空間を支配した。 あまりの性急さにが身を引こうとすれば、壁に頭が当たってしまった。逃げ場を失いカカシの猛攻に着いていくのが難しくなった彼女は、息継ぎすらままならないようで徐々に力を失ってゆく。 (喰われ、そ) 熱に浮かされた頭ではそんなことをぼんやりと思った。だから壁に縫い付けられた片方の手をパタパタと動かして、もう限界だとカカシに合図を送る。往生際悪く彼女の下唇を何度か食んでから、名残惜しそうにカカシがその身を引けば、目の前には頬を赤くして瞳の潤んだ恋人が出来上がっているものだから、彼は純粋に「食いたい」と思ったのだった。 「はあ、は、も、ただいま、ぐらい、言わせて」 「え〜がっついてきたのどっちだっけ?」 「え〜なんのことかなあ」 はにかみながらはその場にぺたんと座り込む。一糸乱れぬカカシとは裏腹に、彼女は短い呼吸を繰り返し、落ち着いたところで大きく深呼吸をすると、気だるい腕をなんとか動かして靴を脱ぎはじめた。そして立ち上がろうとしたのを察したカカシが、力の入らない彼女に代わってぐいとその身体を引っ張り上げた。 「笑われちゃうかもしれないけど、一個いい?」 リビングに戻りながらカカシが呟く。はベストのファスナーを下ろし、横手にある脱衣篭にそれを放り込み「なあに?」と返事をしたのでカカシは、彼女がアンダーのハイネックの襟を崩し、大きな伸びをし終わったところを見計らって言葉を続けた。 「さ、いつか俺が拾った四葉のクローバー壁に飾ってくれただろ?」 「あ、気付いてくれたの?任務行く前に飾ったからカカシに言えなかったのよね」 「いや、それが申し訳ないことに今日気付いてさ」 ペタペタと裸足でカカシの後をが追う。本当は今すぐにでも風呂に入ってソファでのんびりしたいところだが、すぐにでも提出しなくてはならない報告書と戦うため、格好もそのままに椅子に座った。カカシは冷蔵庫からミネラルウォーターを取り出し、丁寧に蓋を開けると、テーブルの上に無造作に並べられた報告書の横にそっと置き、ソファに自身も腰を下ろす。すると、「ありがとう」とが早速水に口を付けた。その姿をカカシがソファから横目でじっと見やれば、水を嚥下する様につい目を奪われてしまう。ペットボトルから離れた唇が、濡れて艶やかに光っていてひどく色めかしかった。 「でさ、何か良いこと無いかなーっていい歳して思っちゃったわけ」 「うんうん、良いことあったの?」 カカシにしてはなんだかとても可愛いことを言う、とは心の中で思った。 「に会いたいって無性に思ってたらさ、お前、本当に帰って来るんだからびっくりした、・・・よ。」 「え・・・」 頭を指で掻きながら、どこか照れくささの窺える顔でカカシが言うものだから、つられても急に照れくさくなる。数分前に、あんなにがっつくようなキスをした男には全く見えなかった。 そんな予想もしなかった四葉のクローバーの話に、ははっと何かを思い出し、勢いよく立ち上がる。どうしたのだろうとカカシが視線で追えば、洗面所から「あったー」と彼女の声がし、またペタペタとした音とともに帰ってきたのだった。 両の手が何かを隠すように胸の前で丸められている。微笑みながらがカカシの横に腰を下ろすと、一人増えた重みでソファが深くなった。 「見て、これ」 カカシの前でが手を開けば、そこにはなんと先ほどの会話の主役だった四葉のクローバーが。以前カカシが拾ってきたものに比べて些か小ぶりではあるものの、それは正真正銘の幸運のシンボルだ。 「護衛してた人にお子さんがいてね、帰り際に貰ったの。お礼だよって。私も良いこと起きないかな、なんて思っちゃった」 「へえ、大名界隈にもまともな子がいたんだ」 「こらこらカカシセンセ?」 くすくすと困ったようにが笑う。カカシは彼女から四葉のクローバーを手に取り、茎を回して遊び始めた。 「なんていうか、あれよね、恥ずかしいから言わないけど」 「・・・そーね、なんか俺たちウブなことしてる気がする」 「あはは、あーおかしい」 「いい年してなにしてんだか」 二人して一緒のことを考えて、一緒のことを期待して。それはまさしく付き合い始めのカップルがお互いに囁く愛の言葉かのように、お互いの愛を確認する言葉かのように。 つん、とが鼻先をカカシの鼻先にぶつけた。キスを求める仕草に応えるようにカカシが唇を近づければ、彼女はさっと身を引いていく。まるで悪戯っ子のような笑みを浮かべたに、乗ってやるかとカカシも負けじと追いはじめる。しかしまたもが逃げるので今度は逃がさないとばかりに、カカシはすかさずその腕で彼女の身体を抱きこみ、観念しろ、と不敵な笑みを浮かべてゆっくりとその距離を縮めていく。口付けを受け入れようと、カカシを見つめていたの瞼が段々と下がっていく。あっという間に熱を含んだ大人の表情に戻るのだからカカシは堪らなかった。 そして、互いの唇が触れる、まさにその瞬間。カカシから無遠慮な腹の虫の悲鳴が。 「っぷ、っく、あはは」 ムードもへったくれもない間抜けな音に思わずが吹き出し、目の前の銀髪もそれに続く。 「お腹空いちゃった?」 「はあ、丁度夕飯の支度しようとしてたんだよね」 この状態でこの場を終わらせてしまうのが、なんとなく癪な気がしたカカシは、軽いキスをに贈る。 「は?腹減った?疲れの方が強い?」 「疲れたけどお腹も空いてる。報告書も出したいから、今日は外で食べない?」 「いいねそれ。あ、そういやこの前アスマが隠れ家みたいな店教えてくれたんだけど、行く?」 「隠れ家?楽しみ、早く報告書まとめなきゃ」 がテーブルに移り報告書と格闘しはじめると、カカシは手の中にあった四葉のクローバーを永遠の愛読書の丁度中ほどのページに挟み込んだ。 壁にかかった額の中に、小ぶりなそれが仲間入りをするのはきっとそう遠くない。 (2014.3.26) (2016.3.11修正) CLOSE |