部屋に入った途端冷たい風が鋭利な刃物のように身体をすり抜けていったので、私は肩を跳ねさせるように身震いを起こした。流石は鉄の国の厳しい寒さといったところだが、問題はなぜ部屋の窓が開いているのか、だ。それも、全開で。 窓辺に顔を向ければカカシが立っていた。外の白銀に負けないぐらいの美しい色をしたカカシの髪は、雪混じりの風にそよいでいて、その背中はどこか侘しささえ感じさせる。こちらの気配に気が付いたのか振り返る彼の動きが、まるで映画のワンシーンかのようにスローモーションに映る。意識して動いている時の彼の所作は美しい。ひとつひとつがしなやかで、女性めいたものを醸し出すのにどこか雄々しい。 なにかあったのだろうかと疑問に思うも、その風貌は至って平生と変わりがなかった。 「おかえり」 その優しい声音も普段と何一つ変わりはしない。のだけど。 寒いよ、と言おうとした瞬間、大きな影が私を包み込んだ。どんな香りよりも私を安らかにさせる大好きな彼のそれが、肺を支配する。すると今度は声を出すことすら許されずに唇を塞がれる。同時に腰と頭も強く引かれて。 冷たい。カカシの唇が、氷のように冷たい。一体いつから窓を開けていたのだろうか。一体いつから外を眺めていたのだろうか。そんなことを思ったら心が締め付けられて、鼻の奥がじんと熱くなった。きっとまた、複雑なことを考えていたに違いない。貪るように求めてくる薄い唇に、同じように応えてやれば、段々と熱気を取り戻す彼のそれ。けれど反対に私はといえば体温が奪われていくようで、部屋に舞い込む風をより冷ややかに感じたのだった。 声が漏れて、新鮮な空気を欲すれば欲するほどカカシは私を力強く抱きしめ、何度も口角を変えて舌を絡めてくる。普段ならこれだけでスイッチが入ったように身体がじんわりと熱を覚えるが、今は寒さでそれどころではなかった。彼の首に回した手は風に当てられてどんどんと体温を失っていく。鈍くなった感覚に疲れを覚え、この場から解放される術を考えたが、その答えを見つけるのは難しいことではなかった。そう、私はすっかり冷たくなった腕を動かし、―彼の服の内側の―背中に差し込んでやったのだ。 途端体を跳ねさせたカカシがその反動で顔を退かせる。すると彼は困ったように笑って私の額に、ごめんねとばかりにキスを一つ落とした。 「窓なんて開けてどうしたの」 「いやー、こんな真っ白な世界はたまにで良いかなってさ」 「う、ん?」 「一人は寂しいってこと」 そう言うとカカシは私の首元に顔を埋めて、耳の付け根にまたもキスを落とす。いつになく甘えてくる恋人がなんだか無性に可愛くて、私は彼の頭を何度か撫でるも、やはり冷たい風に耐え切れなくて「閉めようよ」と呟くと、カカシは「んー」と渋りながら私をすぐ傍のベッドへとじりじりと押しやり始めた。されるがままになっていると、膝の裏側に不意にベッドの角が当たって視界が一気に回転するではないか。 瞳に映るは、カカシの僅かに口角の上がった顔と、その上の天井だけ。思えば最初からそういう雰囲気を持っていたからか、私の頭はやけに冷静だった。この後の会合は何時から始まるからまだ余裕はあるな、とか、会合の場所から少し離れたところに部屋を貰ったから誰も来はしないだろう、とか。 逃げる気なんてないけれど。きっとそれはお互いわかっていることだけど。私の揺れる瞳を射抜く彼は狼だった。ごくりと息を呑む。それが合図になってしまうなんて、ベタすぎだ。 カカシが私に馬乗りになって足でしっかりとこの身体を挟み込む。視線はますます腹を空かせた狼そのものだ。けれど怖くはなかった。むしろ喰われるのを待つ私には待ち遠しさすらあったのだから。とはいえど。 「カカシ、窓閉めよ?寒い」 するとカカシは不敵な笑みを浮かべて耳元に顔を近づけてくると、普段よりも低く、湿り気を帯びた声音で囁いたのだった。 「大丈夫、すぐにあったかくしてやるから」 「・・・ッ」 瞬時寒さとは別の身震いが全身を駆け巡った。ずるい。そんな声で。決して私には奪えない、その主導権。簡単な一言で喜ぶ自分の体が恨めしい。ううん。違う。自分の身体なのに、私の言うことより彼の言うことを優先させるのが恨めしい、のだ。 そのまま耳に熱を帯びた舌先が侵入してくる。彼の息遣いやら赤い猛獣の動きによって、まるで内部から体が侵食されていくようだ。さらに銀色の、見た目とは裏腹に柔らかい彼の毛先が頬を何度も何度も掠めてこそばゆい。耳たぶを甘噛みされたかと思えば、次の瞬間には細くさせたそれが耳の溝を這う。下から上へ。そして上から下へ。さらにそこから頬を滑っていった彼の舌が私の唇に到着すると、まさにいただきますとばかりに吸い付かれる。 ただ只管に求めてくる恋人が愛おしかった。だから手を伸ばして彼の髪を掻き抱いてやると、彼は気を良くしたのだろうか、一層熱心に唇を寄せてくる。ちらりと目蓋を開いて盗み見てやれば、男性の割に長い睫毛が下を向いていた。羨ましくなるほど綺麗な素肌だが、朝方になるとところどころチクチクするのを知っているのは、里中どこを探してもきっと私だけだ。 そんな私の視線に気が付いたのか、カカシも瞳を見開いた。その距離感が、なんだかゼロよりもゼロに近い気がして。 彼はにこりと笑い、鳥のついばみのように最後に唇を食んでから私を解放したのだった。 「ど?少しはあったかくなった?」 「ふふ、まだ寒いかなあ」 「お、言うねぇ」 「ん、はやくあっためて」 「・・・、知らないよ、そういうこと言うと」 それから全ては夢の世界のようだった。彼の声も、彼の肌も、彼の動きも。なにもかもが美しくて、たおやかで、それでいて烈火のようで。 行為の後に彼は言った。窓を閉めなかったのは、私の体温をより感じていたいからだ、と。 |
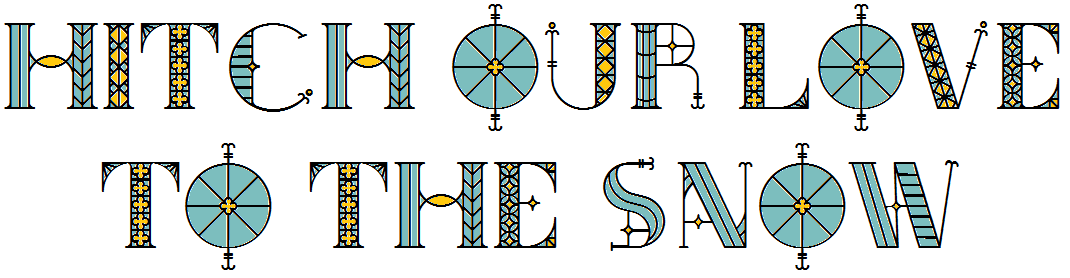
|
(2015.7.1 ぼくらの愛を雪に繋いで) (2016.3.31修正) CLOSE |