俺とを含む十数名に与えられた任務内容は、とある小国内の紛争における非戦闘員の救助活動だった。大名同士の派閥争いが発端の、代々続く一族達の薄っぺらい見栄と自尊心のための戦いだ。 過去にも何度かこのようなことが起こったが、折り合いの悪い両者に割って入れる者は誰もおらず、今回に至ってはなんと忍まで投入されてしまった。だがこの国は火の国の同盟国の傘下であり、公的な忍をそういった私情では要請できないため、そいつらは所謂「傭兵」の忍部隊だった。しかし所詮はその日暮らしの傭兵部隊。雇い主よりも金を積まれた方に心も傾くというものだ。裏切り裏切られの泥沼の戦いに双方はますます憤怒したのは言を俟たない。そしてそういう連中の中には決まって、人殺しが好きな奴がいると相場は決まっているのだから、事態は最低極まりなく、最早威信などどこにも在りはしなかった。 とはいえ一般人に被害が及んでは黙っていられないと、とうとう別の大名が火の国に事態沈静のための依頼を申し出に来たのがこの任務の発端なのだが、その時大名は言ったのだ。その滑稽が生み出すのは一族の歴史の紡ぎなどではない。何十年と繰り返し何故気付けないのか。しかし見過ごしてきたのだから我もまた同罪であろう。だから今一度全てをやり直したい。これ以上国を壊させないためにも、双方の大名と傭兵部隊を始末してくれ、と。 ある意味大名らしい発言だった。全てリセットしてくれ、などとは。そんなやり方で全てが無かったことになるのなら、この世はほとほとぬるま湯だ。綱手さまは、頭を冷やして考え直せとその依頼を一蹴したが、大名の意志は変わらなかった。 結局のところ、今己が何をしようとしているのか、その後の全ての責任を負う覚悟を持っているのか、それをしかと確認した後に彼女は依頼をしぶしぶ承諾したのだった。こちらからしても相手がいくら同盟国の傘下とはいえ、一国の政治に強く関与できるほどの権限は持ち合わせていないからだ。だからこそ彼女はこの任務を、あくまで紛争地内の非戦闘員救護と命名した。それも、戦闘の見込みあり、で。きっとどこかの意外性ナンバーワンが聞いたならば激怒する案件だろう。わかる。確かにその気持ちが自分にない訳ではない。だがこの騒動は一見雑に見えるが、一般の市民からしてみれば内情はとても繊細なのだ。だから彼らを守ることが何よりも優先なのだ。 * 疲弊した傭兵集団のトップに雷切を食らわせる直前、近くの民家から大爆発が起こった。それだけなら何も気にする必要は無かった。だがしかし、予想外なことにその爆風に乗って雷切の軌道に一人の少女が飛んできてしまったのだ。術の発動を止めるか?それとも右手はこのままに左手で助けるか?だが敵も術式を組んでいる。動向に気を配らねばならない。コンマ何秒の世界でトップスピードに乗った俺は、瞬時の判断に平生らしからぬ迷いを生んでしまった。 だから一瞬の迷いにさらなる悲劇が訪れたのだ。きっと俺と敵の間に飛んできた少女が視界に入ったのだろう、次の瞬間にはが民家の方から自分の目の前に飛び出してきたのだから。 その光景が、いつかの悪夢を蘇らせた。ああ、いつかだなんて、皮肉だな。はっきりと覚えているくせに。そう、リンの心臓を貫いた、あの日だ。 それ―俺の右手が彼女の衣服を切り裂き、その奥の肌に爪の先が触れたその一瞬―は、まるでスローモーションのようだった。 特有の肉の感触と、彼女の顔が歪む瞬間と。 「・・・ッ」 世界が真っ白になった頃には全ての時間が正しく動いていた。 雷切の衝撃で吹き飛んだが、少女を抱えたまま地面に力なく倒れている。 色褪せていく。何もかもが。 オビトよ。お前は俺の目になって世界を見てやると言っていたのに。 なのに俺ときたら。 こんなありさまばかりをお前に見せている。 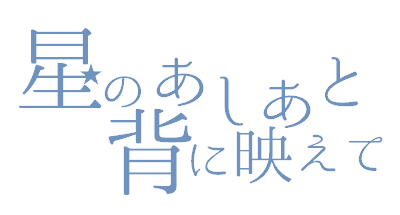 「・・・」 どうやって任務を終わらせたのかも、どうやって里に帰ってきたのかも覚えていない。ドアを開けたのも、血まみれのベストを脱ぎ捨てたのも、そのあとまた外に出たのもそうだ。 気が付けば街を歩いていた。恐らく、病院に向かって。 「・・・・・・」 白み始めた空が微かな空虚を孕んでいるのか、それともそれを見ている人間側の精神的空虚か。 夢と現実の界隈を行き交うその混交を嘲笑うかのように、明るみと共に次第に鮮明に浮かび上がる家々の輪郭は、確かにこの世界を存在させている証人だった。世界はとても偉大だと、その大地に生を成す我々人間はとても幸福だと、どこかの誰かが言っていた。それを証明するかのように、今頭上に広がる空は果てしない。薄い雲の間から百群色が儚さを引き立て、薄れゆく星々が情感を刺激した。また一日が始まろうとしている。これからやってくるだろう朝日の眩い光を伴って。 明けない夜は無いのだと、そんなことを思えば、それはまるで希望に溢れているかのよう捉えることができるのかもしれない。けれど真逆だ。夜明けは前日の唯一の肯定者だ。 時計の針を左に回して、時間を戻すことができたなら。 そう、いつだって俺は後悔ばかりで上手く生きれない人間だった。大切にしたいと、守りたいと思う物事の全てが嘲笑うかのように指の間から零れ落ちていく。オビトとリンを救えなかったように。班の子たちを、ナルトとサスケとサクラを、ばらばらにしてしまったように。あいつらはまだ子供で、小さくて、太陽に向かって一心に背を伸ばす草花のように尊い存在だ。しっかりと大地に根を張り、上を目指す手伝いをするのが俺の役目だったというのに。 今回もそうだ。俺が隊長を務めていながら、咄嗟の出来事に対応できなかった。結果、に怪我を負わせてしまった。 (どの面下げて、俺は、) 彼女を酷い目に遭わせたのは他の誰でもない、自分自身だ。大切な仲間を守るためのこの右手は、奪ってばかりだ。救うことなどできやしない、血塗れの凶器だ。 脳を、あの光景が支配する。身体を、あの感覚が支配する。 が瞬時に高密度のチャクラでガードしていなければ、発動を止めようとしていたとはいえ、俺はあのまま彼女の皮膚どころか肉の奥まで抉っていたに違いない。そんな俺がどんな顔をして彼女に会うというのだろう。 病院の入り口から先は、次元が歪んでしまったかのように重苦しい圧迫さを放っていて、今の自分にはとてもじゃないがこれ以上前に進めなかった。何も救えない自分には、誰かを救おうと必死に働く者の集まる世界の中に、入ってはいけないような気がしてしまったからだ。だから不甲斐なさが襲い来る頃には俺は病院を通り越し、昇り始めた朝の光を受けながら当てもなく重たい足をのろのろと引きずるのだった。 「私ね、いーっぱいお魚さん見るんだあ!もーすっごく楽しみ!」 「木の葉にはいないお魚さんがたっくさんいるんだって、ママも凄く楽しみだわ」 「俺はどっちかっていうと刺身で食いたいなあ・・・」 「パパサイテー!」 「ほんとほんと、パパサイテ〜!」 道中、沢山の荷物を持った家族とすれ違った。楽しそうにきゃっきゃと笑う姿がぼんやりと視界に入る。あの話と身なりからして、彼らはこれからきっとどこかへ旅行にでも行くのだろう。三人仲良く、手を繋いで。朝日に照らされた彼らの顔は一際眩かった。優しい温もりと、零れんばかりの愛に包まれた誰もが羨む理想の家族。そんなものは無縁だとばかり思っていたのに。 (と、あんな風になれたらと、思ったっけな) いつしか自分が愛されることを、考えてしまうようになるなんて。 けれど俺には命が見えなかった。生きていることの核が無くなって、ゆらゆらと水面を漂うかのような、はたまた綿菓子のように、ほんの一滴の水で瞬時に消えてなくなるかのような。でも死ぬことも見えない。だってこの体の中にはオビトがいるのだ。俺には彼への果たさねばならない責任があって、まだ何一つとしてそれは達成できていないのだから。 そう、それなのに。 ―あなたが、生きていて、くれてることが、私は嬉しいの。 気付けば彼女はいつも俺の心にいた。暗部でツーマンセルを組んだ時も、彼女が長期の任務で居なかった時も、四代目の死の時も、慰霊碑の前で幾度となく語り合った時も、俺が上忍師になると決めた時も、そして、今この時も。いつだって彼女は俺の支えになろうとしてくれていた。なろうと、なんて失礼だ。事実そうなのだから。 そんな彼女だからこそ、その慈しみに溢れた彼女だからこそ、平凡で幸せな将来を垣間見たのかもしれない。前線に出るような任務は辞めてもらって、夕方には帰れるような任務に就いて貰い、夜は一緒に食事を取る。ああでもないこうでもないと話をしながら風呂に入って、そして川の字で寝るのだ。子供を挟んで、寝顔が可愛いね、なんて親バカなこと言ったりなんかして。そしてとクスクスと笑ったりなんかして。 昔の俺が今此処にいたなら、腑抜けたな、なんて蔑んでいるかもしれない。 年を重ねたせいなのか、彼女と出会ったせいなのか、どちらにせよ思うのだ。人は温もりの中でしか生きられないと。 でも同時にこうも思う。俺にはそんな資格、あるはずがないと。愛を想い幸せを願う度に、心の奥底で俺が今まで守れなかった人々が言うのだ。 (お前にそれができると思うのか?これまでに何を守ったって言うんだ) (私のこと、救ってくれなかったじゃない) (カカシ、君は何も分かっていないよ) (なんでサスケにあんな技教えたんだってばよ) (仲間を守る為?ふざけたこと言ってんじゃねーよ、お前はその右手で何人殺したんだ) (大丈夫って言ったじゃない、前みたいになれるって言ったじゃない、先生のうそつき) そして最後に俺自身が言う。お前はいつもに与えられてばかりだ、それなのにお前ときたら、に何をした? 彼女の幸せを願うなら、傍にいるべきはお前じゃない。幸せなんて言葉、お前には無い、と。 確かにそうだ。 ああ、身体が、冷えてゆく。 * 街が活気を取り戻そうとしていた。木々は光に照らされて葉の青さを増していたし、川の水面は美しく澄んでいた。時折魚が跳ねては波紋が広がっていく。どこかでは目覚まし時計の音が鳴り、どこかではヤカンの笛が音を立てている、早くから仕事がある者はもう外に出ていたし、商店を営む者は庭先の掃除を始めてもいた。 俺はといえば当ても無く、里をぐるりと一周してしまった気がする。結局病院に入る勇気は無いままに。いっそのことこのまま任務が入ってしまえば良いとさえ思えるほどだった。情けない。 とはいえそんな都合の良いこと起こるはずもなく、相変わらず重たい歩を進めながら再び家へと帰ってくれば、扉を開けた瞬間に風が頬を撫で去った。どういうことだろう。窓を開けた記憶は無いのに。何故風が吹きぬけたのだ。しかしどうやって家に帰ったかの記憶がないのだから、もしかしたら頭を冷やすために窓を開けたのかもしれない。それで、閉めるのも忘れ外に出たのかもしれない。 だが靴を脱ぎ捨て部屋に入った瞬間、鼻を掠めたのは。そして、瞳が捉えたのは。 「・・・!」 ベッドに腰を降ろしている彼女の髪は、ふわふわと風のそよぎに揺らめいていて、柔らかな陽の光が彼女の身体に降り注いでいる。穏やかに映し出される様とは裏腹に彼女の表情は険しくて、その眼光に俺は動くことができなかった。 「、どうして」 「誰かさんが迎えに来てくれないからでしょ」 返す言葉が見つからなかった。 「カカシ、ここ」 ぽんぽんと、彼女が布団を叩いた。隣に来いという意味だろう。 ぎこちない動きで、彼女と目も合わせられぬまま。ぴたりと横に付く勇気もなく、彼女の左側に腰を沈めれば不自然にできた間隔が際立った。その高だか三十センチ程の隙間が、今の俺には何メートルにも感じられて仕方がない。 「・・・、ご」 「言ったら怒る」 かぶせるように彼女が放った言葉はとても強かった。謝ることすら俺には許されていないのだろうか。行き場を失くした言葉の続きが、唾液と一緒に体内へと消えていった。 「飛び出したの、私だから」 「そんな、違う、あれは俺の判断が・・・!」 「嫌な思い、させちゃったね」 そう彼女が言うや否や、体の右側がじわりと温かくなった。 この間隔を、ものの一秒でいとも簡単に飛び越えてくるなんて。どうやら彼女にとってこの三十センチは三十センチではなかったらしい。伏し目がちに彼女を見やる。したらばあの険しい顔はもう消えていて、変わりに目を細めた、もの柔らかな表情が俺をじっと捉えていた。 「・・・寝てないの?酷い顔してるわ」 彼女の苦笑いすら、美しくて。 「・・・・・・たまに、一日が始まるのが怖くなる。大切な誰かが、またこの手からいなくなるんじゃないかって」 ―大切な人たちが、一人、そしてまた一人といなくなっていく。 なのに俺は生きている。この世界に。何が成せるわけでもなく。いや、むしろ成せないことだらけだ。救えないばかり。そして、失っていくばかりだ。そのくせ奪うことは簡単で、壊すことも簡単で。なのに何かを築いたり、何かを結びつけることはちっとも簡単じゃない。 サスケが里を抜けてもう半年だ。ナルトは自来也さまと修行に出かけたし、サクラは綱手さまと修行の毎日。オビトの教えてくれたあの大事な言葉を胸に俺は日々生きてきたつもりだったけれど。 、俺は、・・・俺はさ、口先だけの男にはなりたくなかったんだ。 だから昔里に戻ってきた自来也さまがナルトを預かると言った時、正直不服だった。教え子の成長を近くで見てきたのは俺だったからね。だからこそ班内の不穏な空気を消し去るのも自分の役目だと思っていた。なのに、俺ときたら。何にもしてやることができないただの力不足な男だったんだ。 サスケにもう一度よく考えろと言い放った。あの言葉は適切だったんだろうか。もっと広い心と熱い胸で、泣いていいと言ってやることができたなら。分かるように愛してやれたなら。だって涙は慰めじゃなく優しい心の行為なんだから。あいつは班で生活する内に自分に変化が訪れたことを感じた筈だ。仲間と競い合うことを楽しいと感じた筈だ。仲間が怪我をした時には心が痛かった筈だ。ナルトにだってそうだ。もっとあいつと多く話をしてやったなら。終末の谷でボロボロになったナルトが溜め込んできた胸の蟠りの全てを、俺は理解していなかった。サクラにも、大丈夫、だなんて軽率なことを言った。安心させて、落としたんだ。 俺のせいだ。俺がもっとしっかりしていたなら。何が口先だけの男にはなりたくない、だ。下らない。反吐が出る―・・・。 「カカシ・・・」 「なのにお前まで、いなくなったら、俺は」 指先の震える手をゆっくりと彼女の頬に伸ばす。うっすらと血の滲んだ絆創膏が痛々しく映った。 触れるまで、あと僅か。一センチもない。けれどそれ以上は進めなかった。俺から彼女に触れるなど。そんなことが、許されるのか。 「私は生きてる、生きてるよ」 はそんな俺の手を掬い取り、そのまま自身の頬に宛がわせた。 触れた瞬間、条件反射で手が引き攣る。しかし躊躇うように、繊細なガラスに触れるように、指先に少しだけ力を込めれば。 「・・・ッ」 弾力を返し、血液のめぐりを伝えてくるその確かな質感が、俺の指先を通って全身に痺れのように流れていった。頬に触れ、瞼に触れ、鼻に、唇に、額に触れる。ああ、生きている、確かに彼女はここに存在している。 鼻の奥がじんと熱くなるのを感じた。込みあがるあの滴。 「カカシ」 柔らかな声と共に、は翳るような俺の背中にそっと手を回してきた。そしてそのまま引き寄せられる。壊れ物を扱うように。優しく、繊細に。そう、ガラスは彼女ではなく自分の方だった。 ふわりと当たる彼女の胸元は酷く安心した。彼女の持つ香りが安定剤のように肺に落ちてくる。あやすように、とんとんと。心臓の鼓動を模したリズムが身体に染み渡った。 どうしてお前は俺を掴む。どうしてお前は俺を離そうとしない。 「・・・、俺で良いわけ?」 「どういうこと?」 「俺はいつも、から貰ってばかりだ」 刹那、今朝方の家族が脳裏に浮かんだ。三人仲良く手を繋いで旅行へでかける、あの微笑ましい家族の姿が。 「朝、を迎えに行こうと思ったけど、勇気が出なくて、それで里の中を歩いてたんだ。そしたらとある家族とすれ違ってさ。これから旅行に行くみたいだった」 「うん」 「子供は沢山魚を見るんだって。そしたら母親が私も楽しみだって。でも父親はさ、俺は刺身の方が良いって言っちゃって。それで二人からサイテーとか言われててさ。そんなやりとりを聞いてて思ったんだ。ああいうのも、良いなあって。そしたら頭の中で、子供を抱っこするお前の姿が浮かんだよ。凄く良かった。はきっと、良い母親になって、良い家庭を築いていくんだろうなって」 「・・・あなたは、そこにいないの?」 「・・・どうかな」 はたと、背中をたたく彼女の手が止まった。 「・・・・・・俺はさ、何もできない人間なんだ。約束だって守れない、仲間だって守れない」 数え切れぬほど繰り返した自問自答。でも答えなんて出やしない。 「お前はこうして俺の傍にいてくれるけど、でも本当は、温もりとか、愛とか、家族とか、幸せとか、俺には触れる資格がないんだ」 いつの間にか、独り善がりの独白の数々に酔いしれていたのかもしれない。だからの身体が震えていたことに、ちっとも気が付かなかったのだ。 「なによ、それ」 頭上に何かが落ちてきて漸く彼女の異変を感じ取った。はっとして上体を起こせば、そこには眉根を寄せて、目に涙を一杯に溜めた彼女の顔があった。唇を噛み締めわなわなとさせ、先ほどの怒りよりもさらに凄みを利かせた怒りの眼だ。自制できないほどの憤懣が肌に、産毛にひしひしと伝わってくる。 窓から降り注ぐ光が彼女の頬の縦に入った一線を照らし出した。そして理解したのだ。頭に落ちてきたのが、彼女の眼から零れた涙であったことを。 「本気で言ってるの?」 こくりと、頷きかけようとしたその時。 彼女の両の手が伸びてきた。かと思えば次の瞬間には激しい痛みが。 「・・・いッッ!!」 「ねえ、幸せになっちゃいけないなんて、誰が決めたの」 「そ、それは、」 「一人で抱えて、一人で生きて、一人で死んで!そんなの誰も、望んでない、そんなの貴方が勝手に創り上げた水鏡じゃない!カカシ、さっき言った、ああいうのも良いなって。それがあなたの心の叫びじゃない。どうして殻に閉じこもってしまうの、望んでるのにどうして幸せを拒むの、私はなんなの、ただのお飾り?あなたの悲劇を満たすための脇役?」 「・・・!」 彼女の零れ落ちる涙が俺の服に染みを作った。布地がそれを吸収したと思ったら、すぐさま次の水滴が落ちてくる。 抓られた頬は日常生活で負ってきた痛みのどれよりも痛く、同様に彼女の表情も出会ってから時を過ごした中で最も怒りに満ち、侘しく、切なかった。溢れ出る彼女の涙が俺の胸中をどんどん熱くさせる。とうに落ち着いたと思っていた筈の鼻の奥も再び熱を取り戻し、自覚してしまえば最早とどまるところを知らない大波のようにそれが目元までこみ上げてきて。 「あなたは、波間の砂みたいに、いつも崩れそうな道を行ってしまう」 ああ。もしも。 「沢山苦しんで、沢山もがいて。だから想いを残すことを、怖いって思ってる」 もしも。 「でもね、カカシ」 俺の思いが未来に対する呪縛なのだとしたら。 「・・・っそれでもわたしは、カカシと、幸せに、なりたい」 「、」 人生において様々な物事に答えを示すことは怖く、難しく、勇気もいる。それに時はその場にとどまることも許してはくれない。けれどもし、根無し草の俺にも、居場所を望むことが許されるのなら。その夢を織り成す世界はきっと、優しいのかもしれないと、そう思わせてくれる人が目の前にいる。 の前では中途半端な考えも価値観も、捨てたと思っていた筈だったのに。 「もし、あなたの未来に、私がいるなら・・・来て?」 「・・・ッ!」 力なく頬から離れていった彼女の手が、横に大きく広げられた。そこからはとても早かった。 磁石のエヌ極とエス極のように、引力に引き寄せられるかのように。溢れた涙が落ちるより早く。 それは居心地のいい枝木を見つけた鳥のごとく。赤子を抱く母の腕の中のごとく。 「名前、呼んで?」 「・・・」 「もっかい」 「」 「もっかい」 「」 「・・・聞こえる?心臓の音」 「・・・ああ」 トクリ、トクリ。規則的な感覚で繰り返される、生の律動。この世で最も優しい音楽。 ああ、彼女は、いつだって。 「カカシ、私はここにいるよ」 「・・・っごめん」 「今度私の前であんなこと言ったら、許さないんだからね、ばか」 「ごめん、、ごめん、ほんとに、ごめん」 「ちがうよ、ごめんじゃない」 「・・・ありが、とう」 「ん、よくできました」 よしよしと頭を撫でる彼女の手のひらは偉大だと思う。 もう迷わない。今まで何度も決めたのに。その度に彼女はいつも上を向いては夜空の星を数えていた。でも俺は下を向いて自分の過ちを数えていた。弱い自分を必死に隠すかのように。 夜明けは前日の肯定者だと、そればかり見てきて青い空には何も描こうとしてこなかった。どうしてお前は俺を掴むのだと、そう思った俺を許してほしい。が俺を抱き上げて、堕ちないように救い上げてくれたんだ。弱い俺を包むように愛してくれたんだ。 「私から貰ってばっかりって言ってたけど、それは違うよ。カカシが人に与えすぎなの。あなた自身が磨り減るぐらいに」 愛おしい人の御胸に隙間が無くなるぐらいに擦り寄れば、俺の頭を抱えるようにさらにぎゅっと抱きしめられて。 「だからね、私からぐらい、与えられてて」 もしも彼女がこの先も俺と歩いてくれるなら。昨日を忘れない以上に、明日を思って眠りにつきたい。きっと色んな日がやってくる。どうやっても不安に駆られる日は、いつもより長く彼女を抱きしめたい。 いつか二人で道を根ざしていけるように。 そしていつか二人でそれを思い出して語り合えるように。 「ありがとう、、愛してる」 (2014.12.11 Yさんに!捧ぐ!) (2017.5.20) CLOSE |