|
腹が減った。今日はひどく疲れた。朝から晩まで一日中外を駆け巡り、胃に入れたものといえば十秒チャージが売りのゼリー飲料とミネラルウォーターのみ。がっつりしたものが食べたいといえば食べたいが、それ以上に一刻も早く寝てしまいたい気持ちの方が強かった。 逸る気持ちからついアクセルを踏み込んでしまう。わずかに開けていた窓の隙間から入り込む、湿度を帯びた初夏の風。昼間の生ぬるさとは違い、夜のそれにはまだそこはかとなく冷たさが残っていて、疲れた体に染み入るかのような心地良さで肌を撫で去っていく。 街灯や建物の光が次第に線を描くように後ろへと流れ始めた頃、ふと胸ポケットの携帯が唸りを上げた。疲れている時ほどとどめを刺されるというものだ。路肩に止まり電話に出たらば、探偵業のクライアントからだった。今の案件とは別にもう一つ頼まれてほしいこととやらがあるらしい。社長夫人も中々気が休まらないものだと思いながら快諾して通話を切ると、無機質な機械音とは打って変わって夜の街のやかましさが視界と耳を奪った。 なに、問題はない。大した仕事ではないのだから。再度発進しようとしたその時だった、見覚えのある顔が、一つ先の横断歩道を横切って行ったのは。 「え?」 あの顔は。まごうことなきあの横顔は―…。 「・・・」 徹夜明けの死んだ顔が嘘のようだった。とても楽しげに歩いている。それも誰だか見知らぬ男と。手こそ繋いではいないものの、普段仕事の時に見せる顔と全く真逆だ。目を細めて優しく笑う姿は、いつもつっけんどんな態度を取ってくる彼女からはまるで想像もつかない。自分の前ではあんな表情、しないくせに。 (・・・女の顔) 柔らかな笑顔と、それを引き立たせる春を思わせるような化粧。高いレストランにでも行ったのだろう華やかな衣服に身を包む彼女はとても、そう、何かで形容できるようなそんなことを考えさせないくらい、ただただ綺麗だった。 (なんだかんだで器用に生きてるんだな) なんとなく、安心していたのだと思う。自分と同じように大量の仕事と戦いながら、死んだ魚の目を浮かべた顔で朝日を浴び、インスタントコーヒーを口にして、そしてまたデスクに戻って仕事と向き合い、日本を守るという同じ目標を掲げていたことに。 けれどどうやら同期は知らぬ間に恋をして、知らぬ間にどこぞのだれかと二人で出かける仲になっていたらしい。もちろん誰かと付き合いたいだとか、結婚したいだとか、そういうことはまだまだ自分にとっていつだかも分からない未来の話に近いものがあったし、というよりもそもそもその気すらなかったわけで、だから誰かが恋人を作ったからといって嫉妬なんてする筈もなかった。 それはきっと、自分にとっては犬を飼い始めたとか引っ越しをしたとか、新しい定食屋の味が良いとかそういう類と一切変わらない話なのだが、なぜだろう、彼女だけは、そう、だけは、何かが違うのだ。同期だからだろうか。じゃあ、松田たちがまだ生きていて、それで彼らに恋人ができていたら?そりゃあ素直に嬉しい。ならばどうして彼女にだけこんなに重石がのしかかるような想いを?妹が嫁ぐ気分がこれか?いやいや、妹って。あんな妹いてたまるか。 (・・・なぜって、そんなの) 触れたからに決まってるじゃないか。あの唇に。 フラッシュバックするのはいつかのエレベーターでの事故。多忙を極めあの後彼女と二人きりで話をする機会はほとんどなかった。だからこそ余計にあの時の光景が脳裏に焼き付いてしまっている。 今までただの同期で異性として何とも思ってこなかったくせに。急に可愛く見えてきただなんて勝手で都合の良い思いを抱いただけのくせに。なのにあの一回のキスは互いにとってきっとなにか特別なものだったんじゃないかなんて思いながら、素知らぬ顔で仕事をしていたのだ。それが彼女じゃなければ、なんてことはないただの事故で終わっただろうに。 (・・・恋なんて) 誰かに恋をすることは、この仕事をする上での足枷だ。当たり前のようにできる恋は自分には許されない。身分を明かすこともできなければ、有事の際に恋人を一番にしてやることもできないのだから。だけれども、その相手がならば―…。 (・・・) 共有できるものの多さは確かにある。だがそれは本当に純粋な恋なのか。しがらみのない恋ができるからというだけではないのか。もしあのキスが無かったら、自分たちは今も昔も変わらないただの同期のままだった。いつからこんなに流されるようになったとは思うものの、現にあの日は起きてしまったし、意識するようにもなってしまった。そうして今は目の前で彼女の横を歩く男の存在が気になって仕方ない。自分は彼氏でも保護者でもないのに、だ。 本当にその通りだ。彼女がどう生きようと自分にはなんの関係もない。にもかかわらず、男が彼女の肩を抱く光景から目が離せないでいる。 (あんなにも簡単に、彼女に触れてしまえる人間がこの世にいる) ああ、やはり自分は。そう、何かに気が付く時は大抵、何かを失う時だ。 バーの入り口へとエスコートされる彼女の姿。続いて男も消えていく。今日は金曜だ。一杯やって、そのあとどうするのだろう。雑音の中、遠くで響く乾いたベルの音だけが、やけに強く耳に残った。 (・・・いやいや) 考えるだけ無駄だ。強くハンドルを握って、ペダルを踏み込んだ。 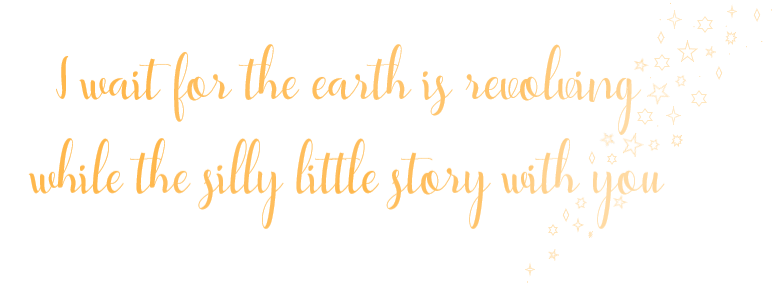 「」 「あれ、珍しいですね、降谷さんが喫煙ルームから出てくるなんて」 「やあくん。いやね、たまたま通りかかった降谷くんを世間話ついでに呼び寄せてしまったんだよ」 「そういうことだ」 「あ、佐川さんお疲れさまです。そうだったんですね」 「それじゃあ降谷くん、またな」 「はい、お疲れさまです」 他部署の上司が角を曲がるのを見届けるや否や、からぼそり、煙草くさ、と小言が漏れる。当たり前のことを言うな、と小突くと彼女は口角を上げ笑った。 「なんでまたここに?」 「喫煙ルームにライター忘れたから取ってこいって鬼上司がね」 「鬼・・・ああ、あいつか。なあ、今時間は?」 「少しだけなら」 ここじゃなんだと非常階段の扉に手をかけた。人がいないことを確認して、適当に階段に腰を下ろす。西日に照らされたそこは心地良い暖かさになっていて、午後の気だるい体を包むように臀部から熱が伝わった。 人々が行き交う足音、車の走行音、工事の騒音に、夜の訪れを予感させる飲食店の香り。扉の向こう側が外だなんてことは思うのがおかしいぐらいに当たり前のことだ。だけれども、扉を開けていつも感じるのは、街を形成する雑多な事物の一つに、自分も知らぬ間に飲み込まれているということだった。 「・・・」 「・・・」 とんとんと人差し指で隣を指す。すぐさまこくりと頷いた彼女がやってくる。並んで座るシチュエーションに、ふとあの日のことが蘇った。なんとなく似ている。あの時とは違って太陽の光も、暖かさも、出口もちゃんとあるけれど。 大きさの異なる二足の靴に目を落とす。ストッキング越しの踝が視界に入った。そうか、今日はスカートか。相変わらずヒールのすり減ったパンプスだと思えば、彼女がぽつりと口を開いた。 「なんか、久しぶりだね」 「部署が一緒なのに久しぶりだなんてな」 「私はずっと庁舎にはいたけど」 「引きこもり」 「出たがり」 顔を見合わせてお互いくつくつと笑うと、傾きかけた陽の光を吸い込んだ彼女の瞳がきらきらと輝いていた。最近の仕事はどうだと聞けばぼちぼち思った通りの成果は得られていると彼女は答えた。反対に同じことを聞かれ、同じようなことを答えれば、本当は少し疲れてるでしょ、と言われてしまった。そりゃあ君はデートもして潤ってるのかもしれないが、こっちはその時間も働いているんだから、なんてこと、言えはしないが少しでもそう思ってしまった自分に酷く嫌気が差す。 「今度杯戸三丁目辺りで張り込むそうだな」 「うん、でもターゲットの家の近くで急に道路工事が入るらしくて。ちょっとやりづらいのよね」 「工事の延期は?」 「無理。工事するってチラシを近隣住民に配ってた。それこそターゲットの家にも。今の段階ではまだ警察が動いてるって工事会社にも知られたくないから、延期はしない方が無難だわ」 「人が多ければいい目眩しにはなりそうだが、音が拾えるかは工事の音次第だな」 「そうなの、イヤホンがあてにならなそうで」 「策は?」 「もちろん練ってある。でも雨で工事が中止になってほしいっていうのが本音かな」 ふふ、と諦めがちに笑った彼女に、ふと時が止まる。今自分たち、普通に会話していなかったか?顔を合わせばつっけんどんな態度でお互いの揚げ足を取るような自分たちが。いや、昔から普通に会話はしてきたのだけれど。ただ配属が一緒になり、同期だからこそ仕事の成果を比べられ、負けてたまるかなんて気持ちを抱えたまま何年も過ぎてしまった。そりゃあ同じ釜の飯を食ったなんちゃらというのが育む絆はやはり強いもので、この部署にいる誰よりも彼女には絶対的な信頼を寄せているし、口喧嘩こそすれどお互いを陥れるような行為は絶対にない。ただやはり、同じ部署ながら違うアプローチで目的を果たそうとするからこその、譲れない何かがあるのは確かなのだ。 「・・・どしたの?顔になにか付いてる?」 「いや、徹夜じゃないとこんなに穏やかに話ができるんだな、と」 この感じは久々だ、と付け足すと彼女は「そうだね」と言った。頬が膨らみ、形の良い唇の隙間から白い歯が覗いている。細められた瞳のなんと優しいこと。この柔らかな微笑みは、徹夜明けではないからだと願いたかった。もしそうでなければ一体誰がそんな顔を、いや、その先は考えないことにしよう。 「金曜日の夜、君を見たよ」 「え?どこで?」 「米花デパート前の交差点」 「声かけてくれたら良かったのに」 「男と歩いていたのに声なんかかけれるわけないだろ」 君もなんだかんだで女だったんだな、と言おうとした、のだが。 「・・・なんだその顔は」 彼女は眉間にこれでもかと皴を寄せて、お世辞にも綺麗だとは言えない顔をこちらにぐいと向けた。顔に力を入れすぎるとあれだぞ、隠しきれない隈が浮き彫りになるぞ、なんて言ったら殴られそうだから言わないものの、この顔から彼女がなにを言おうとしているのかは読み取ることができなかった。盗み見してたなんて最低、な顔といえば顔だし、紹介ぐらいしたいんだからスルーしないでよ、な顔にも見えなくない。 「デートだと思ってたの?」 「違うとでも?」 「あの観察眼に長けた降谷さんが、あれをデートとはねえ」 「観察眼って・・・あのなあ」 「上司のご友人の息子さん。一度会ってやってくれないかって。顔を立てて会ってきただけ。分からなかったのかあ」 分かるかばか、と言うと彼女は眉根を下げて困ったように微笑んだ。それから数秒と経たずに宙を舞ったのだ、私、楽しそうだった?という言葉が。この時、彼女からは責任を背負って立つあの凛とした顔つきは消えていて、それはただの、そう、ただの昔馴染みの、他の誰でもないの顔をしていたのだった。 「良い笑顔だったよ」 「そんなこと、ないと思うけど」 「俺といる時はあんな顔しないだろ」 拗ねた子供みたいな台詞は案の定彼女の顔をきょとんとさせた。俺といる時は、だなんて一体何目線の言葉だろう。まずい一言にこそばゆさが背中を襲った。間を持たすために河岸を変えようかとも思ったが、動揺を気取られたくないという下らないプライドがそれを阻んだ。ああそうさ、結構な衝撃だったさ、男といる時の君の顔なんて。 「・・・すまない、忘れてく、」 「降谷さんといる時の私がどんな顔してるかは分からないけど、なんていうか、降谷さんはさあ・・・」 食い気味に彼女の声が重なった。思わずハッと上げた顔が彼女のそれとかち合うが、すぐに続きが紡がれることはなかった。言葉の続きに好奇心がぐいぐいとそそられて、視線を外すことができない。そんなに見つめるなとばかりに彼女から引き気味に、あはは、と乾いた笑いが溢れる。 「・・・止まるな先を言え」 「・・・やっぱり上手く表現できないからいいかな」 「それは俺が決める」 「げ、ますます言いたくないな」 いいから早く、と肘で小突くと、彼女は恥ずかしげに手先を遊ばせながら、観念した表情で口を開いた。刹那、南から一塵の風が吹く。二人の間を通り過ぎたそれは生暖かく、あの日からの時間の経過を如実に物語っていた。 外れてしまった視線を追う。彼女はどこか遠くの景色を眺めていた。風に掬われた髪を直す指先にはたと目を奪われれば、薄く色づいた柔らかな唇が形を変える。 「・・・降谷さんはさ、こういう感じ、なんだよね」 「こういう感じ?」 「そ。疲れたーって窓開けたら吹いてた風、かな。あとはほら、すごく暑い日に、あ、気持ちいいなって思う風があるじゃない?ちょっとだけひんやりっていうか、一瞬暑さを忘れる涼しい風っていうか。ああいう感じ」 「随分と抽象的だ」 「だから上手く表現できないって言ったじゃない」 彼女のジト目が向けられると同時にまた風が吹く。目には見えねども、肌を撫で去る瞬間の、そして髪をくすぐる瞬間の軌跡を感じながら、心地良さを享受した。この気持ち良さが、自分? 「冬の肉まんもそう、寒い日にコンビニで肉まん買って食べるときのあの幸せな感じ。おでんの大根もね」 「俺は肉まんで大根なのか」 「悪かったわね上手く言えなくて」 風や肉まんや大根に例えられたのは初めてのことで、その衝撃はもちろん大きかったが、なにより具体的な話は何一つとしてないのに、分かる気がしたのが面白かった。 心が満たされるあの喜びの感覚。何気ない日常の合間にある心が安らぐ瞬間。彼女らしいといえば彼女らしい表現だ。その感覚を自分に対しても抱いているというのだから、それはなんて、なんて―…。 「同期だから降谷さんが良い成績上げたら嬉しいけど、それと同じぐらい悔しさもあって、負けたくもないから時々酷いこと言っちゃうけどさ」 「時々?」 「うるさい」 「で?けどなんだ?」 「・・・なんかさ、どれだけ自分がお金を稼いでるかとか、次はこの限定モデルの車買って飾るんだとか、社交界での付き合いがどうのとか、そういう上っ面の話しかしない人の近くはどうも疲れちゃって。降谷さんとこうやって話してる方が私は自然体でいられるから好き」 「・・・おい、そういうの」 そういうの、男は勘違いするぞ、と言おうとした矢先のことだった、彼女から「だったんだけどね」と零れたのは。 (え?) その一言に、時が止まる。それだけじゃない。今しがたの言葉がやけに鋭い刃となって胸を貫いていく。それは鏡に亀裂が入るあの感じに似ていた。 (・・・) だったんだけどね。だった。過去形。それが意味するのは過去と現在での感情の変化。そう、つまり昔は自然体でいられたのが、今はそうではないということ。上げられて落とされたみたいに胸に重石がのしかかる。それを感づかせまいと平生を装うと、彼女から強い視線を感じた。 「な、なんだ」 「・・・」 「?」 穴が開くほど見つめられるとはまさにこのことで、きゅっと唇を結んだ彼女の固い眼差しが、けれどもどこか悔し気で、それでいて切なそうな、そう、複雑な感情が眠っていそうな、そんな眼差しが一心に自分だけを捉えている。 「・・・あんなこと、するから」 「・・・!」 どくりと、胸が鳴った。 あんなことするから。それが何を言わんとしているのか分からないほど耄碌しちゃいない。だからこそ何も返すことができなかった。だってあれは、急に君が可愛く見えたんだ、仕方ないじゃないか。そんな子供じみたことしか浮かばない。けれどもそれが言える筈もなく。何か他の言葉を考えるが、脳裏にあの日の光景が幾重にもフラッシュバックしてくるおかげで全く思い付かなかった。そうこうしている間に彼女は自分との間隔を詰めているじゃないか。なんなんだ、一体何を考えている。 増える瞬き。逸る呼吸。ごくりと嚥下した生唾。彼女から紡がれた「ねえ」の一言が、ねっとりと耳に絡みつく。 「今から悪いこと、するね」 「え?」 言うや否や、彼女がぐいとこちらへ身を乗り出した。澄んだ声音が耳を貫く速さとは打って変わって、その動きはスローモーションのようだった。どこかの工事現場のかしましい金属音が共鳴しているみたいに、鼓動とリンクする。うるさい、どこまでも心臓がうるさい。それでいて息苦しいほどの浮遊感が胸の奥底にある。想像もつかない次の何かへの期待と不安。 近付く彼女の瞳が次第に伏せられて、顔が傾いて。こんなの、答えは一つしか―…。 「ッ」 成す術もなく、気付いた時には唇が重なって、離れていくのを微動だにできずにただ見ることしかできなかった。瞬きも呼吸もすべて忘れて、なのに唇に残る肉感と彼女の香りだけはありありと脳に焼き付いて離れない。瞼を開けた彼女の瞳はにわかに熱を孕んでいて、西日の反射がその潤みを強めていた。俺はきっとこの顔を、一生忘れないと思う。 「降谷さんの間抜け面ゲット」 不敵な笑みに浮かぶのは、自分と同じ頬の赤。してやられたと思うよりも、体が動く方が早かった。 「わ、」 「二回目は、確信犯じゃなかったのか」 離れそうになった腰をぐいと引き戻し、抵抗を試みる細腕も制して、返事も待たず強引に唇を奪った。この自分が、懐を許すだなんて。そんな気持ちをどこかに感じながら。 「んっ、ぅ」 吐息の重なる距離を一気に越えて、口内を懐柔する。噛みつくようなキスにこわばった彼女の体も、熱の絡み合いに次第に力が抜けていく。腰に回した腕に力を込めて、隙間も何もないほどに唇を合わせて、仕返しとばかりに好きなままに彼女を堪能すれば、くぐもった甘声が南風に溶けていった。 忘れもしないこの感触を、もう一度味わうことができるとは思いもしなかった。しかも自分からでなく彼女からとは、誰が予想できただろう。 「自然体でいられるから好き、だったんだけどね」の言葉はきっと、エレベーターに閉じ込められた日までそうだった、の意だ。あの日以降、彼女も意識していた。それだけで、まるで火傷でもしたみたいに体中の血が沸騰しそうだった。 「っはぁ、は・・・」 「・・・っ」 上気した互いの息が交じり合っては消えていく。手のひらから伝わる彼女の肺の収縮。掴んだままの手首を開放すれば、それは力なく項垂れるように落ちていった。 「・・・こういうの、もう絶対、ないと思ってた」 「なぜ?」 「仕事の方が優先順位高いじゃん、降谷さんは」 「なんだその理由」 「・・・ごめん、うそ。だってもう一回しちゃったら、戻れないから、同期に」 自分から仕掛けたくせに、と困ったように笑うと、彼女は今にも泣きだしそうな勢いで大きなため息を吐いた。がっくりと頭を落としたかと思ったら、次の瞬間には力のない拳で胸を叩かれる。 「キスから始まるとか、そんなの、全然誠実じゃない」 止まぬ拳は心臓の鼓動に似ていた。もう引き下がることは許さないと己の理性が警告するかのようであり、同時に深く重い、そしてどこまでも甘さに満ちた毒のようでもあった。確かに。君だけをずっと見ていた、なんて恋愛ドラマみたいなものは何もないけれど、でも思うのだ、なんの積み重ねもなかった関係ではないということを。 「一時の感情に流されて、キスなんかしちゃって、全然大人じゃない」 「・・・それは、俺も言えた口じゃないが」 「降谷さんがあの時急にキスしたいとか言うから」 「言質は取っただろ、それに君だって乗り気だった」 「だから誠実じゃないんだってば」 むしろ言質を取っただけ誠実だった気がする、と良いように記憶を解釈するがそれが口から出ることはなかった。代わりに、いい加減ぽこすか殴るのはやめてくれ、と再度手首を掴めば彼女は力強く抵抗した。敵わないのはとっくのとうに知っていても、やめられないといった風だった。それで結局、拳の骨をぐりぐりと押し付けてくる。諦めの悪さ、いや、粘り強さとでも言えば警察として聞こえは良いかもしれない。 「・・・好きになっちゃったよ、ばか」 冷静を取り戻し始めた脳が、再び沸騰しそうだった。悔しそうな顔で唇をぎゅっと噛み締めて、零れそうで零れない涙を溜めた双眸が自分を捉えている。甘やかなムードなんて微塵も感じさせない告白。なんだこいつ、全然「好き」の顔をしていないじゃないか。なのに可愛くてしかたない、なんて。 「顔赤くしてんじゃないわよ」 「が好きだなんて言うから」 「でも上手くいくわけない」 「・・・だったとしても戻れるさ、ただの同期に。それでいつか、思い出して笑い合える日が来る」 「そんなの、それに、私たち」 公安だし、とか細い声が続く。何の問題があるんだと返せば、同じ部署にはいられないだの周りに迷惑がかかるだの御託を並べ始めるではないか。今まで散々一般人と付き合ってきたくせに、と言うと彼女はぱたりと口を閉じて、ハハ、と乾いた笑みとともに視線を逸らしてしまった。 往々にして言い訳を並べる時点で気持ちは決まっているものだ。確かに制限の多い生活に身を置く自分たちだが、互いの境遇を理解しているということは関係を築くにあたって非常に大きな武器だ。死んで初めて配偶者が国家のために働く人間だと知ることだって多いのだから。けれど彼女ならば、己の全てをさらすことができる。彼女ならば、背中を預けることができる。彼女ならば、この手から手放さずとも傍で供に生きていける。愛を知った人間はとても強く、それでいて酷く脆い。 「なあ、もしこれが間違いなら楽しい間違いをしよう。まあ、間違いにする気もないが」 「なんでそんなに自信満々に言えるの」 「なんで?君だからだろ」 「・・・私、口悪いよ」 「知ってるさ」 「料理だってできないよ」 「俺が作る」 「徹夜明けの顔ひどいよ」 「何を今更」 何年の付き合いだと思ってる。そんなのとっくのとうに超えた仲だろ。そんなことを思ったらまた風が吹き寄せた。薄橙の陽を吸い込んで、ただ優しく、柔らかく、たおやかな流れが、何か見えないヴェールで体を包み込むかのように通り過ぎていく。 「・・・後悔しても知らないからね」 「となら、老後も縁側でああだこうだ言いながらお茶が飲めそうだ」 「それどんなプロポーズ?毎日味噌汁作ってとか一緒の墓に入ってとかとレベル一緒じゃない?」 「・・・ま、とにかくだ、君といると落ち着く」 「やだ、嬉しい」 「やなのか嬉しいのかどっちだ」 「ふふ」 嬉しいよ、降谷さん。そう言って彼女は鼻をぐずんと啜って笑う。こんな日が来るとは夢にも思わなかったけれど、今なら完全に分かると思った。彼女の言っていたことが。 確かに。気持ちが良い。 の表現を借りるならきっとこうだ。夜が明けて、目が眩むほどの美しい朝焼けを見た時のあの安堵感、それが彼女だ。 「」 「?」 「 」 (2018.5.18) CLOSE |