の指導係が長期任務へ出てからというもの、カカシは自身の暗部での生活の傍ら、彼女ともよく任務へ出るようになっていた。彼女の水遁から繰り出される水の豊饒さは、さらに言ってしまえば彼女固有のこの特性は、言い方は悪いが何をするにしても非常に使い勝手が良いとカカシは思っていた。ミナトや先輩の暗部が仕込んだだけあってその精度は非情に高く、忍術においては文句の付けどころがなかったし、千鳥はもちろん火遁と組み合わせて水蒸気を生み出したりとそこそこの応用性もある。攻守ともにお互いオールラウンダーに動けるからこそ、フォーメーションの組み合わせを多く考えることができた。その多彩さから噂になることもしばしばだった。ただ反面体術はカカシから言わせれば正直お飾り程度だったし、体力も保つ方ではないのもネックだった。体力は大きくなればそれなりに見合ってくるので心配は要らないが、体術の方は暗部でちゃんとやっていけているのか心配になるほどだ。その意味からすれば多芸に秀でるカカシは、やはり木の葉の天才なのだった。 そんなとカカシは任務で顔こそよく合わせるものの、普段所属する班が異なるという理由から、日ごろ暗部の所属する建物内で会うことはほぼ無かった。彼が身を置く班内には、暗部の中に何やら子供がいるぞとの噂話がよく回ってきたもので、「一度は手合わせをしてみたい」だとか、「俺たちもうかうかしていられない」だとか上昇志向の意見もあれば、反対に「子供の癖に暗部なんて百年早い」とか、「会ったら痛い目を見せてやろう」なんて言葉が飛び交うのも日常茶飯事だった。しかし最近夕顔という少女が暗部に加わり―しかもカカシと同班―、話はそちらで持ちきりで、班外の子供の話はいつしか消え去っていた。 指導係の不在から、もう腕に封印術を施していないとはいえ、過度のチャクラの放出を控えるよう命令されているはといえば、相変わらず任務半分修行半分といった具合で、早く同僚に追いつきたいと思う毎日を過ごしていた。暗部では必要以上の干渉はいらないと教えられてきたが、実際に身を置くようになってから彼女が感じたことがいくつかある。素性の全てを知らずとも皆それなりに和気藹々としていること。任務時間以外でも交流を持つことがあること。そして自分のようなチビ助にも面倒くさがらずに修行の相手をしてくれる人がいること、だ。中には一匹狼を好む者もいるし、他人とわざと衝突するような態度を取る者もいる。しかし「班」という力が結束力を高めるのか、普段表の世界で組むような班員の絆と似たようなものがここにもある気がした。その結束の強さからか、他所の班とは折り合いが悪いこともよくある。すれ違うときは、まるで火花が散るような目を面の下に隠し持つこともしばしばだ。暗部はやはり暗部たる特殊な空気感を持つ世界なのだった。 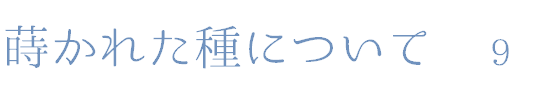 ひっそりと佇む慰霊碑には、先客がいるとなると自然と空気を読み時間をずらす人々が多かった。誰もがここでは自分の世界に浸りたい。そのため、人の足がよく訪れる場所ではあるが、この時分も石碑の前にはカカシと以外誰もいはしなかった。 そんな彼らは近頃は二人での任務を終えると、どちらからともなく慰霊碑の前まで足を運んでは、他愛の無い話や反省会をするのを常としていた。あの対応は良かったとか、あそこで不意を突かれたのはまずかったとか、今度は新しいフォーメーションを取ってみようとか、それこそ話は尽きない。 「お前って、いつもビクビクしてた」 「そ、れは・・・ええっと」 「そんなに怖かった?」 「・・・う、怖かった、です。でも今考えると怖さの種類が違うと思うんです、よ?」 の発した言葉が何故疑問系だったのか、それはカカシには読み取ることはできなかった。日に日に自分たちの身に起きた話をあれやこれやとしたものだが、かつての仲間の話をするのはどこか憚られた気がしていたのか、両者共にそこに触れることはほとんどなかった。とはいえ慰霊碑に来れば、どうしたって目に入ってしまう彼等の名前。その名前を二人とも意識し、知覚しては頭の中で思い出しているのだ。 自分の左目を失う瞬間。親友の目が体内に組み込まれるあの瞬間。そして何より絶対に守ると誓った親友の想い人の、皮膚と肉を突き破る瞬間。カカシはあの禍々しい光景を思い返す度に、右手がぴくりと反応してしまうのだった。瞬間的に血に染まった右手を見る時はいつも、身体全体から嫌な汗が沸々と湧き上がり鼓動を早くしていく。 一種のトラウマでさえあるその彼の症状の全てをはじっと見つめていた。だから余計に思うのだった。彼らの名を話題に取り上げてはいけないのだ、と。そう思った筈なのに、今日という日は何故か過去寄りの話になってしまった気がする。直接的ではないにしろ、昔を想起させるようなことをは最終的に言ってしまったのだった。彼女から放たれた言葉から、カカシはいつだったか彼女に「冷たい目じゃ、無くなった」と言われたことを思い出した。今ならその意味が分かるかもしれない。そう、それは友人が教えてくれた忍道を受け継いだからに違いない、と。父のことで非情になりきった心に、彼女はきっと恐れを抱いていたのだ。とはいえ今はその種類が違うと彼女は言う。それこそがつまりあの「色んなことがわかるようになった」の中身なんだろう。 「でも」 そこでの言葉は途切れてしまった。 「でも?」 カカシが聞き返す。同時に彼女の顔を覗けば、さっと視線を横にずらされてしまった。 「・・・気になるだろ」 その言葉に返事が来ることはなく。 は立ち上がると、「ごめんなさい」と一言残して消えてしまったのだった。ぽつりと残されたカカシは、煙が消えるまで彼女が居た場所を眺めていた。 ―でも。その続きは何だったのだろうか。居なくなってしまうぐらいだから、きっと聞かないほうが良かったのだ。そうして再び慰霊碑に目をやった。削られた文字でしか今は相手を見ることができないが、遠い空にいる友は何を思っているのだろう。 「・・・オビト、リン」 カカシは右手を沈みゆく夕日にそっと翳した。 「言いたいことが、山のようにあるんだ」 橙が映える背景に、影のように真っ黒になった手の甲。爪先だけは光を通すようでそこだけ半透明に浮き上がる。その黒さはカカシに血を連想させた。この手で奪い去ってしまった大切な人の命が、自分に襲い掛かってくる気さえしてしまう。いいやそうじゃない。知っている。だって彼女は自ら死を望んだのだ。自分が拒んだことは彼女だって知っている。それが真実だ。でも深層心理ではそうではなかった。親友を奪った自分を彼女は憎んでいたのではないか。そう、馬鹿な自分を。今なら分かる。誰かの命と引き換えに里を守ることは、英雄でもなんでもないのだ、と。勿論その名は代々伝えられ守られていくだろう。でもそうじゃない。そんな悲しみの元に里の幸せがあるだなんて、本当の意味の幸せではない。けれどどうにかできるだけの力は自分には無かった。非力なのだ。結局それが現実だ。 (正直、を見てるとリンを思い出して仕方が無い) 辛かった。苦しかった。と共に過ごす時間は自分にとって良いものと自覚しているものの、それと同じぐらい「リンを殺した自分」が浮き彫りにもなってしまうのだから。 カカシに出口など無かった。否、望んですらないのだった。 * (逃げてしまった・・・) カカシから背を向けて走り去ってしまったは気まずそうな顔を浮かべながら帰路を辿っていた。幼いながらに彼が抱えるものが巨大であることを知っている彼女としては、自身が言わんとしていることが、良くないことのように思えて仕方がなかったのだ。 昔はカカシに関して、怖くて威圧感の強い人間だという認識しか持っていなかったし、オビトやリンとは違いぶっきらぼうな人間だとも思っていた。他の人とは違う影を纏っていることを薄々感じてはいたが、こうして任務に出るような間柄になると思っていなかったために、彼について深く知ろうなど考えもしなかった。しかし久方ぶりに病棟で顔を合わせたあの日のカカシは、川辺ですれ違ったのと同一人物かどうか疑うほどに違う目つきをしていて。冷たいのでもないが、優しいのでもない。どちらかに区別できるような眼差しではなかったが、確かな違いをは感じていた。なにより初めてカカシと任務に出たあの日の出来事。夜の慰霊碑での一幕。自分のことを知りたいというカカシに全てを話した後に、今度は彼女の方からも話を聞きたいと言い出せば。少し渋った顔をしながらも、既に彼女から聞きだしてしまった義理があるからか、伏し目がちに言葉を紡ぐ口布越しの少年の声。生まれた場所。両親について。父の死。ミナトとの出会い。班員との毎日。会話というよりは独り言のように呟き出す音を拾い上げながら、は彼の目つきの変化についてなんとなく分かったような気がしたのだった。精神が成長したのがきっと大きかったのかもしれない。初めて会った時に感じた恐怖を彼に対してはもはや抱くことはなかった。 (最近また少し、よくない気がする、なんて) 自分の気持ちでありながら、いまいち上手く説明出来ないのがむず痒かった。 (のめり込む、とも違うような) しかし言おうとしていたことはカカシにとってプラスになるどころか、きっと傷つけてしまうに違いない。まだまだ自分の及ばない世界があるのだと。だからは早く大人になりたいと思った。両親も親友も失った彼の心情を理解し、何か意義のある言葉をかけてやりたかった。かけてやりたいなどと、もしかしたらそれは驕りなのかもしれない。でもそれでも気にかけずにはいられない。彼はそういう相手だった。 (ミナト先生だったら、なんて言うかな) 大好きなミナトの姿を思い浮かべる。彼は今までカカシになんと声をかけてきたのだろう。どう手を差し伸べてきたのだろう。 「あ」 はふと思い出した。 今日は彼女の任務が夕方に終わるという理由から、夕飯を一緒に食べようとミナトが言っていたことを。ここ最近はずっと夜も任務詰めで、ミナトとクシナと食事を取るのは久しぶりだ。二人を思えば過ぎ行く景色に花が咲く。自然と足並みが速くなったのは言を俟たない。 「・・・ん?」 ガラガラと玄関の戸を開ければ、中が何やら騒がしい。一体どうしたことだろうと脱ぎ捨てた靴もそのままに急いで居間へ向かう。すると、喜ぶミナトとそれをくすくすと笑って見ているクシナがいるではないか。はその光景から、何が起きたのかを全く理解することができなかった。 「あら、!おかえりってばね」 「どうしたの、そんなに騒いで」 「!丁度良いところに!」 よくよく見ればミナトの睫毛が濡れていた。そんなミナトはまるで子供のようにに駆け寄ると、彼女の身体を意図も簡単に抱き上げた。事の次第も掴めていないというのに、急激に変わる視界にまたも頭がついていかない彼女のきょとんとした表情。その愛くるしさ(もちろん普段から愛くるしくて仕方がない)が、ミナトの気持ちをさらに高ぶらせる。 「俺、父親になったんだ!」 彼女をしっかりがっしりと閉じ込めるミナトの腕には、これまでで一番強い力が込められていたのだった。 (2014.11.9) (2016.3.7修正) CLOSE |